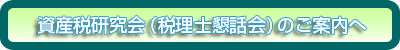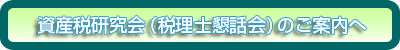|
乮侾乯堚棷暘偺堄媊偲惂搙偺庯巪乮柉朄1028忦丄1031忦乯
丂旐憡懕恖偼丄尨懃偲偟偰惗慜憽梌傗堚尵偵傛傝帺桼偵帺暘偺嵿嶻傪張暘偱偒傑偡丅偟偐偟丄憡懕恖娫偺暘攝偺峵暯傪恾偭偨傝丄旐憡懕恖偐傜嵿嶻傪彸宲偱偒傞偲偄偆憡懕恖偺婜懸姶傪曐岇偟偨傝偡傞昁梫偑偁傞偙偲偐傜丄孼掜巓枀埲奜偺憡懕恖偵偼丄嵟掅尷偺憡懕偺尃棙偲偟偰丄堦掕妱崌偺尃棙乮堚棷暘乯偑曐忈偝傟偰偄傑偡丅
丂偙偺堚棷暘傪怤奞偡傞惗慜憽梌傗堚憽偑偁偭偨応崌偵偼丄怤奞偝傟偨憡懕恖偑堚棷暘尭嶦惪媮傪峴偆偙偲偑偱偒傑偡丅
乮俀乯堚棷暘偺妟乮柉朄戞1028忦乯
丂堚棷暘偺妟偼丄堚棷暘嶼掕婎慴嵿嶻偺壙妟偺2暘偺1(捈宯懜懏偺傒偑憡懕恖偱偁傞応崌偼丄3暘偺1)偵朄掕憡懕妱崌傪忔偠偨嬥妟
乮俁乯堚棷暘嶼掕婎慴嵿嶻偺壙妟乮柉朄戞1029忦乯
丂偙偺嬥妟偼丄嘆旐憡懕恖偑憡懕奐巒帪偵桳偟偨嵿嶻亄嘇憡懕慜1擭埲撪偺惗慜憽梌亄嘊摿暿庴塿亅嘋嵚柋偺崌寁丄偱嶼掕偟傑偡丅
嘊偺摿暿庴塿偼丄偡傋偰偺堚憽丄崶堶偺偨傔偺憽梌乮寢擺嬥丄帩嶲嬥側偳乯傗乽惗寁偺帒杮乿偲偟偰庴偗偨憽梌偑奩摉偟傑偡丅憡懕惻偺壽惻壙奿傪寁嶼偡傞応崌偵壛嶼偡傞惗慜憽梌嵿嶻偺壙妟偼丄3擭埲撪暘偺傒偱偡偑丄堚棷暘嶼掕婎慴嵿嶻偺壙妟偺応崌偼丄擭悢傪栤傢側偄偙偲偵棷堄偑昁梫偱偡丅傑偨丄乽惗寁偺帒杮乿偺斖埻偼丄嵟廔揑偵偼巌朄敾抐偵側傝傑偡偑丄憡摉偵峀偔夝庍偝傟偰偍傝丄帺幮姅幃偺憽梌偼丄捠忢偼摿暿庴塿偵奩摉偡傞偙偲偵側傝傑偡丅偝傜偵丄偙偺惗慜憽梌偝傟偨嵿嶻偼丄憽梌帪偺壙妟偱偼側偔丄憡懕奐巒帪偵側偍尰忬偺傑傑偱偁傞偲偟偨応崌偺壙妟乮偡側傢偪憡懕帪揰偱偺昡壙妟乯偲側傝傑偡丅
乮係乯摿暿庴塿偑帠嬈彸宲傪慾奞偡傞帠椺
亂帠椺亃
| 憡懕恖偼巕俙乮帠嬈彸宲幰乯偲巕俛乮帠嬈彸宲幰埲奜偺幰乯偱偡丅10擭慜丄晝偐傜巕俙偵帺幮姅偺偡傋偰傪惗慜憽梌偟傑偟偨丅憽梌帪偺昡壙偼侽墌偱偟偨偑丄帠嬈彸宲幰偱偁傞俙偑搘椡偟偨寢壥丄晝偺憡懕帪偺昡壙妟偼俉壄墌偲側傝傑偟偨丅晝偺憡懕嵿嶻偼丄尰嬥偺傒2壄墌偱偡丅 |
亂堚棷暘亃
丂憡懕惻偺壽惻壙奿偼2壄偱偡偑丄堚棷暘嶼掕婎慴嵿嶻偺壙妟偼10壄墌乮亖2壄墌亄8壄墌乯偱偡丅偟偨偑偭偰丄巕俙丄巕俛偺偄偢傟偵偲偭偰傕丄堚棷暘偺嬥妟偼丄10壄墌亊1乛2乮堚棷暘偺妱崌乯亊1乛2乮朄掕憡懕妱崌乯亖2壄5,000枩墌偲側傝傑偡丅
亂堚棷暘偺尭嶦偺惪媮亃
丂壖偵丄堚尵偱尰嬥2壄墌偺偡傋偰傪巕俛偵憡懕偝偣傞偲偟偰偄偰傕丄俛偼俙偵懳偟偰丄偝傜偵5,000枩墌偺堚棷暘尭嶦惪媮傪偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅側偤側傜偽丄俙偑晝偐傜惗慜憽梌傪庴偗偨嵿嶻偼8壄墌偱偁傝丄俛偼2壄墌偟偐憡懕偟偰偄側偄偐傜偱偡丅俙偑帺幮姅幃偺壙抣偺憹壛偼帺暘偺搘椡偺寢壥偱偁傞偲庡挘偟偰傕丄擣傔傜傟傑偣傫丅
乮俆乯堚棷暘偵娭偡傞柉朄偺摿椺惂搙偺昁梫惈
丂忋婰乮係乯偺帠椺偺応崌丄帠嬈彸宲幰偺搘椡偵傛偭偰摼傜傟偨帺幮姅幃偺壙抣偺憹壛偑丄帠嬈彸宲幰埲奜偺幰偺堚棷暘偺妟傪憹戝偝偣傞偙偲偵側偭偰偄傑偡丅偙偺傛偆側帠懺傪旔偗傞偨傔偵丄堚棷暘偵娭偡傞柉朄偺摿椺惂搙偲偟偰丄帠嬈彸宲幰偵惗慜憽梌偝傟偨姅幃摍偵偮偄偰偼丄堚棷暘嶼掕婎慴嵿嶻偵嶼擖偟側偄慬抲乮彍奜崌堄乯傗嶼擖偡傞嬥妟傪帠慜偵屌掕偡傞慬抲乮屌掕崌堄乯偑憂愝偝傟偨偺偱偡丅 |