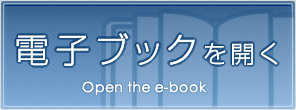税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 page 1/16
このページは 税務サンプル|判例裁決から見る交際費の実務 の電子ブックに掲載されている1ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
iはじめに~本書の目的~たとえば、ある法人の従業員が取引先の担当者と食事をするとしましょう。もちろん、食事をすることそのものが目的ではなく、何らかの営業上の意図があってのものです。人間が食事をするとい....
iはじめに~本書の目的~たとえば、ある法人の従業員が取引先の担当者と食事をするとしましょう。もちろん、食事をすることそのものが目的ではなく、何らかの営業上の意図があってのものです。人間が食事をするということは、理屈としては、そこには何らかの「所得」が発生しているはずです。しかし、フィリンジ・ベネフィット課税における「使用者の便宜の論理」のように、この食事は言ってみれば「仕方なく」(場合によっては嫌々)したものであるから、そこに課税するのはおかしいという理屈もあります。では、こんな場合はどうでしょうか。ある法人の業務上、自己の得意先の担当者を接待する目的で、銀座や北新地の高級クラブに招待したとします。そして、実際に得意先の担当者が接待の内容に満足し、結果的に歓心を得ることができ、取引関係の円滑な関係を築くことができ、新たな受注を得ることができたとします。まず、この場合、法人が高級クラブに支払った金額については、原則は(交際費等課税の制度がなければ)損金の額に算入されます。そして、対価を受け取った高級クラブの売上は所得税か法人税の課税対象とされます。同時に接待を受けた得意先の担当者は、接待内容に満足したのであるから、理屈としては、そこにはなんらかの「所得」が発生しているはずです。しかし、法人が支払った直接の相手先は高級クラブです。「法人」は飲み食いしないし感情もないから、「満足」もしません。現実世界では、法人の従業員や役員が「満足」しているに過ぎません。だが、このままだとこの「満足」には課税されない。つまり、理屈としての「所得」は2種類あることになります。飲食店の所得と従業員・役員