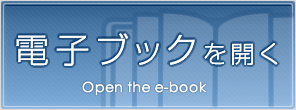税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで page 14/20
このページは 税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
税務サンプル|Q&A税務調査から租税訴訟まで
22すなわち、この犯則調査では、その調査に当たる収税官吏は、犯則事件を調査するために必要があるときは、犯則嫌疑者(犯則調査の対象となっている者をこのように呼びます。)若しくは参考人に対して質問し、犯則嫌疑者の所持する物件、帳簿、書類等を検査し、又は、これらの者が任意に提出したものを領置したり、参考人の所持する物件、帳簿、書類等を検査したり、あるいは、官公署や公私の団体に照会して報告を求めたりすることができるとされています(国犯法1)。このような行為は、任意調査と呼ばれていますが、犯則調査では、このような任意調査に止まらず、収税官吏には、犯則事件を調査するために必要があるときは、さらに、裁判官の許可を得て(例外的な場合を除く)、現場に立ち入る臨検をし、犯則事件の証拠となる帳簿や書類その他の物件を捜索するとともに、これを差し押さえることができるという権限が認められています(国犯法2・3)。これを強制調査といいます。4この点、犯則調査の場合とは異なり、税務調査においては、当該職員には任意調査の権限が認められているだけで、臨検、捜索・差押えなどといった強制調査の権限は認められていません。当該職員は、納税義務者等に対して質問し、帳簿書類その他の物件を検査したり、その提示若しくは提出を求めることができ、さらには、提出された物件を留め置くことができるとはされていますが(通則法74の2ないし74の7)、これはあくまでも任意調査にとどまり、相手方がこれに応じなかった場合には、帳簿類等を強制的に取り上げて検査したり、差し押さえたりなどすることはできないのです。ただ、国税通則法では、このような納税者が非協力的な場合の措置として、納税義務者等に対する刑事罰を定めています。すなわち、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁