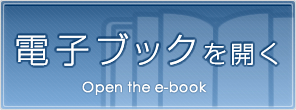退職給付会計の実務Q&A page 17/22
このページは 退職給付会計の実務Q&A の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
退職給付会計の実務Q&A
と違い事業主が自ら簡単に計算できる。通常、債務とは費用の集積であり、過去の期間の勤務費用と利息費用をすべて合計した金額が退職給付債務になる。《図表1 - 3 - 1》及び《図表1 - 3 - 2》で、勤続1年目の勤務費用Aは、2年目にはA′、3年目にはA″と金額が増加する。同様に、勤続2年目の勤務費用Bは、3年目にはB′になり金額が増加する。時の経過に伴い、勤務の対価として獲得した給付である「勤務費用」及びその集積である「退職給付債務」が増加する部分が利息費用である。このように1年経過すると割引期間が1年短くなるため、割引率分だけ勤務費用の集積たる退職給付債務に利息が付く。《図表1 - 3 - 1》及び《図表1 - 3 - 2》では、甲の勤続3年目に当たる当期の利息費用は(A″-A′)+(B′-B)となる。また、当期の退職給付費用(勤務費用+利息費用)は、3年目の退職給付債務(A″+B′+C)- 2年目の退職給付債務(A′+B)として計算できる。ⅲ長期期待運用収益期待運用収益(expected return on plan assets)とは、年金資産の運用により生じると合理的に期待される計算上の収益をいい、期首の年金資産額について合理的に期待される収益額の当該年金資産額に対する比率を期待運用収益率という。《図表1 - 1》のとおり、貸借対照表上、退職給付債務と年金資産とを相殺してネットで退職給付に係る負債(退職給付引当金)を計上する。損益計算書(損益及び包括利益計算書)上も「債務側の費用」と「資産側の費用のマイナス」とを相殺して退職給付費用をネット計上する。具体的には、退職給付債務を構成する勤務費用と利息費用から、年金資産から生じると想定される運用収益を相殺する。退職給付会計では、事業主が期首に長期期待運用収益を合理的に見積もり、あらかじめ退職給付費用から控除することで勤務費用及び利息費用と相殺する。年金資産は、将来の退職給付の支払に充てるために積み立てられているものであり、長期期待運用収益率は、保有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮して算定する。実務上は、過去3~5年程度の運用実績からポートフォリオごとの平均運用利回りを算定し、期首の2退職給付債務と退職給付費用11