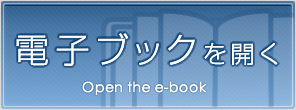四訂増補版 印紙税実務問答集 page 26/34
このページは 四訂増補版 印紙税実務問答集 の電子ブックに掲載されている26ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
42.課税文書に該当するかどうかの判断問ある文書が課税文書に該当するかどうかは,具体的にはどのように判断するのでしょうか。例えば,借入申込書の下欄に連帯保証人の署名,押印がある借入申込書は,文書全体の判断のみによって決めるのでしょうか。それとも申込書の下欄の事項だけについても判断するのでしょうか。答一の文書に2以上の異なる事項が記載されている場合には,その異なる事項ごとに課税文書に該当するかどうかを判断することになります(通則2)。契約書のような文書は,その形式,内容とも作成者の自由にまかされているところから,通常,その内容には種々の事項が織り込まれますが,印紙税の課否は,その文書の全体的な評価によって決めるのではなく,その文書に記載されている事項の一つ一つについて検討し,その中に課税事項が一つでも含まれていれば,その文書は課税文書となるのです。例えば,借入申込書に,債務者がその債務を履行しない場合に保証人がこれを履行することを約するために,署名,押印した場合,その事項は債務の保証に関する契約書(第13号文書)の課税事項に当たりますから,文書全体からみれば課税文書に該当しない借入申込書の形式となっているものであっても,その中に含まれる債務保証事項に着目し,債務の保証に関する契約書(第13号文書)として課税対象となるのです。次に,印紙税は,特定の契約や権利等それ自体を課税対象とするのではなく,それらの事項を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものです。――いわゆる文書税。このように,印紙税は文書税ですから,課税文書に該当するかどうかは,その文書に表されている事項に基づいて判断することとなり,その文書に表されていない事項は判断の要素にとり入れません。