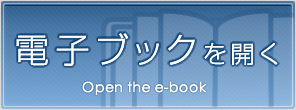四訂増補版 印紙税実務問答集 page 30/34
このページは 四訂増補版 印紙税実務問答集 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
85.課税単位である「一の文書」の意義問印紙税は「一の文書」ごとに課税されるとのことですが,この「一の文書」とはどういう意味ですか。また,どのような基準により判断することになるのでしょうか。答印紙税法では,一の文書であれば,その内容に課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されていても,そのうちの一つの事項の文書として印紙税が課されることとなっています(通則2,3)ので,一の文書の範囲を確定することが印紙税の取扱いの基本となります。一の文書の判断基準については,文書の外形すなわち物理的な形状によるものと文書の記載証明の形態によるものとの二つが考えられますが,通則2及び3の規定は,文書の物理的な形状によることとした場合の方がより素直に理解できるところから,形状を重視した取扱いによることとしています(基本通達第5条)。この取扱いを例をあげて説明しますと,1枚の用紙に消費貸借契約の成立事実を記載した上で当事者双方が署名押印し,また,同時のその用紙の下部余白又は裏面にその消費貸借契約について借入金の受取事実を記載したものは,その記載証明の形態からみれば消費貸借契約書と金銭の受取書との二つの文書とみられますが,印紙税法上は一の文書として(この場合は,消費貸借契約書として)取り扱われます。また,請負基本契約書とその契約についての付属協定書を同時に作成し,それらをとじ合わせるほか契印で結合されているようなものも一の文書となります。しかし,このような文書であっても,各別に記載証明されている部分がそれぞれ独立しており,たまたまとじ合わせているにすぎないと認められるものまで一の文書となるのではありません。すなわち,作成時には一の文書の形態をとっているものであっても,将来切り離して行使したり保存したりするようなものは,その切り離して行使したり保存したりする部分ごとに各別の一の文書