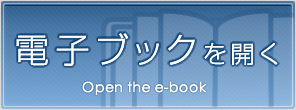四訂増補版 印紙税実務問答集 page 32/34
このページは 四訂増補版 印紙税実務問答集 の電子ブックに掲載されている32ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
四訂増補版 印紙税実務問答集
10も,日時を異にして作成される文書は,それぞれ作成された時点において印紙税の課否を判断することになります。したがって,それぞれが各別の文書となりますから,その付属覚書に課税事項が記載されている場合には,原契約書とは別に印紙税を納付しなければなりません。8.証書と通帳等の区分問印紙税の課税文書は,証書(第1号から第17号までの文書)と通帳等(第18号から第20号までの文書)とに区分できますが,この区分は,どのような基準によって行うのでしょうか。答印紙税の課税文書は,証書と通帳等に大別することができます。ごく常識的には,証書とは1枚の用紙で作成されたもの,通帳等とは2以上の複数の用紙で作成されたものと受け取られがちですが,印紙税法上の区分は,そのような紙数の単複によるのではなく,課税事項を1回限り記載証明する目的で作成されるか,継続的又は連続的に記載証明する目的で作成されるかという文書の作成目的によるのです。文書の作成目的は,文書の形式,内容等に基づいて判断するのですから,その文書の作成時に,課税事項を2回以上付込み証明する欄が設けられているようなものは通帳等となり,そのような欄が設けられていないものは証書であるといえましょう。このように,証書か通帳等かの文書の性格判断は,文書作成時における作成目的に照らして行うものですから,その後の事情の変化により証書に課税事項を追加して記載しても,また,通帳等に2回目以降の付込み証明がされなかったとしても,当初の文書の性格まで変わるものではありません。例えば,通帳(第19号文書)についてみますと,課税となる付込み証明する事項は課税物件表の第1号,第2号,第14号又は第17号についてのものに限ら