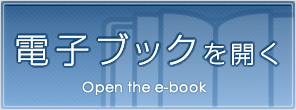月次決算書の見方・説明の仕方 page 19/22
このページは 月次決算書の見方・説明の仕方 の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
月次決算書の見方・説明の仕方
2 黒字会社が赤字会社になるパターン売上高原価率が40%、他のコストは人件費と賃借料のみとして、先ほどのA社が赤字に陥る危険性を考えてみます。(X00年月)売上高100百万円、売上原価40百万円、人件費・賃借料30百万円、営業利益30百万円(X01年月)売上高150百万円、売上原価60百万円、人件費・賃借料75百万円、営業利益15百万円このデータを見た瞬間に、危機感を覚えるようでなければなりません。これは売上高の増加がなかったことにしてでも、年前のコスト水準に戻りたいと願うほど危機的な決算データです。その理由を翌年月(X02年月)の月次データを予想することで考えてみましょう。売上高がこのまま順調に増加するとはかぎりません。年前の売上高に戻ってしまうと予想すると、営業利益はいくらになるでしょう。年前の30百万円にはなりません。雇用と人件費を維持し、オフィスの移転もしないとすれば、15百万円程度の赤字になりかねないのです。(X02年月)売上高100百万円、売上原価40百万円、人件費・賃借料75百万円、営業利益△15百万円これからも順調に会社が成長していくという前提での人員採用やオフィス拡張が赤字の要因になったのです。このケースは特別なものではありません。かつてのリーマン・ショックの影響で、一時的にせよ売上高が半分になった企業も少なくありませんでした。このように、A社における今年月(X01年月)の現状は、過去からの変化も加味して分析することが重要です。変化を読むことは、将来を予測することでもあります。4