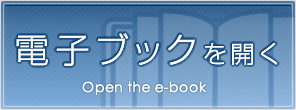逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 11/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
2 〔総論〕1 判例研究の目的 判例を研究することの目的は何であるか。 その1 つの答えは、判例研究の目的は、判決の理論の当否を検討することであるという見解である。これに対して、もう1 つの答えは、判例研究の目的は、現実に裁判所に妥当している、裁判規範を明らかにすること、さらに進んで、将来の裁判を予見することであるとする見解である。 後者の見解は、裁判過程に着目して、裁判によって具体的裁判規範が形成されるのだという考え方に立脚している。 社会的機能という観点から見ると、後者の見解は、将来の裁判を予見することによって、そのことに多大な利害を感じる市民・国民に行動の指針を与えることになる。 判例の研究によって将来の裁判を予見することが可能となるという考え方は、判例拘束の原理が制度上の要請として英米法に存在したという歴史的な事実と深い関係があると考えられる。 しかしながら、実際の裁判過程を見ると、裁判が過去の判例に完全に拘束されていると考えることは正しくない。 それにもかかわらず、判例を研究することによって裁判を予見することは全く不可能であると考えることも正しくない。 一般に、社会には多かれ少なかれ類似した事象が生起するものであり、それらの1 つについて裁判が提示した具体的裁判規範が他の類似の事件についても、原理的には「適用」されることが要請されており、また事実そうなることが相当程度期待されるから、その限度において裁判の予見は可能であるからである。 その限度においてではあるが、裁判過程は、判例によって形成された具体的裁判規範の適用によって、裁判の結論が決定されるという要素を含むと考えられ、したがってまた、その限度において、判例の研究によって具体的な先例的裁判規範を抽出するという作業が、裁判過程における決定基準を提供し、そのことによって裁判の予見可能性の程度を高めるという機能を果たすことになる。 判例の研究を行なう者が、冒頭の2 つの目的のうちのどちらの目的で判例