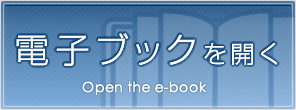逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 13/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている13ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
4 〔総論〕いうことである。 現に、裁判官は多かれ少なかれ裁判の先例に従うべきだと考えて行動しており、そのように行動しない場合には、通常はその裁判が上級審で破棄されるという形態でのサンクションが存在する。さらに裁判以外の一般社会の中で、種々のインフォーマルなサンクション(非難)が想定される。このような一般社会におけるインフォーマルなサンクションが存在するという事実は、観念の世界で抽象化されたときには「拘束力」と呼ばれる。 このような意味での判例の拘束力は、程度の問題である。「判例拘束力」の原理として言語上の表現を持っている英米法では判例が拘束力を持っており、そのような言語的な表現をもっていない日本法では判例が拘束力を持っていないというように考えやすいが、実際には拘束力はいずれの国でも程度の問題であり、英米でも実質的には判例は変更されている。 判例の法源性をこのように考えると、具体的事件の裁判を通じて具体的な裁判規範が成立するに至るという事実を認識することができる。3 判例とは何か 「判例」ということばは、「先例としての判決」という意味を持っている。かつては、判決の中で述べられている抽象的・一般的理論が判例だと考えられていたことがあり、現在でもそういう見方がある。 しかし、判決は、あくまで個別的・具体的事件の解決であり、そこで述べられた抽象的理論を広く他の事件に適用することは、不当な一般化を招きやすい。仮に、その理論が他の類似の事例を広く考慮に入れて作られたものであっても、その事例に直面した場合ほど周到な検討がなされていないことが多い。そこで、英米法の考え方にならい、判決の中で〔真の〕判決理由(レイシオ・デシデンダイ ratio decidendi)と傍論(オバイタ・ディクタ obiter dicta)とを区別し、「真の判決理由」だけが先例としての拘束力を持つのだという考え方がある。 それでは、そこでいう「真の判決理由」とは何であるか。それは、事件の中の基本的事実と判決の結論とを結びつける必要にして十分な理由である。そして、基本的事実を同じくする同種の事件は、同じように取り扱うのが妥当である(公平と法的安定性の要請)ということになる。