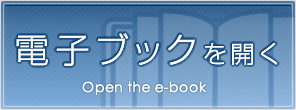逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 14/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
5 しかし、真の判決理由が先例としての拘束力をもつといっても、細かく考えていくと具体的に何が真の判決理由であるかは簡単ではない。 例えば、基本的な事実がA・B・Cからなる第一事件の結論がXであり、A・B・Dからなる第二事件の結論がYであるとすれば、CとDの違いが結論の差をもたらしたと推測することができる。そしてその差をもたらしたものが、それぞれ真の判決理由になるということになる。しかし、A・B・Eという事実をもつ第三事件が現れたときに、その結論が、Xか、Yか、あるいはZとなるかはまったく不明である。その結論は第三事件のEという事実がCまたはDと同種とみられるか、それとも、それらと異なる性質のものと見られるかによって決まってくる。 具体的に基本的事実をどう考えるかであるが、事実を質的に類型化して基本的事実の範囲を決めていくことになる。判決の妥当範囲とか「射程距離」とかいう言葉で論じられるのは、この問題である。そして、それは、単に事実の客観的認識の問題にとどまるものではなく、その判例をどこまで適用させるのがよいかという価値判断を内蔵している。 一般論としては、判例の妥当範囲をあまり広く考えないことが望ましいと考えられている。それを広くすることは、自由な判断の余地を狭めることになるのに対して、判例の妥当範囲を限定することは、具体的妥当性をめざす自由な判断の余地を広げることになるからである。それに関連して、最高裁判決が、判決理由の中で、「特段の事情のないかぎり」という注意書きをつけることがままあるが、判決の抽象的理論が判例として不当に拡大されないようにという意味の警告として解すべきであろうといわれている。 そもそも、裁判官は、常に目前の事件について具体的妥当性をもつ解決を心がけるべきであり、単に先例があるという理由で、判断を停止してよいものではないと考えられている。「判決の拘束力」ということばを、その字句どおり、判例が客観的存在として拘束力を持つというのは必ずしも正確ではない。同種の事件について、同じ結論の判決が出るのは、裁判官が具体的に検討した結果同じ結論に到達したということであり、前の判例に「拘束」されたために、判断を停止して、あるいは、別の望ましい結論を捨てて、それに従ったというのではないことが多いであろう。ただ、裁判官の心理過程を明らかにすることは困難なので、同じ結論が出され、前の判例がそこに引用