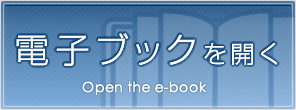逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 15/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている15ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
6 〔総論〕されているならば、その事実を前の判例が拘束力をもったと、事後的に説明しているだけのことである。 裁判官としては、もし前の判決が適当でなかった、あるいは、時代の変化のため適当でなくなったと思えば、判例を変更して、新しい判例を作り出すこともできるし、そうすることがむしろ義務でもあると思われる。あるいは、それが説明として刺激的な印象を与えると考えれば、理屈をつけて前の判例と事件が違うといったり、あるいは、前の判例を無視して衝突を回避する。あるいはまた、判例の妥当範囲を狭く限定して、広げられた余地の中でそれと抵触しない判断をするという場合もある。このようにして、判例は発展していくものであり、それを固定したものと考え、全部の判例が首尾一貫して矛盾がないと考えるのは正確でないといえる。 要するに、過去の判例が将来の判決を当然拘束すると考えるべきではなく、新しい事件を処理する場合に、判例を過去からの遺産として、法的安定性をいたずらに害しないように配慮しながら、説得力のある説明のために活用するということであろう。4 判例は実務を支配する 判例は実務の世界を支配しているといわれている。正確にいうと、判例が拘束する相手は裁判官だけである。それ以外の者は直接には拘束されないから、どういう意見を述べようと自由である。裁判官に対し自己の期待する判断を求める立場にある人々にとって、判例をまったく無視した議論をしても余り意味はなく、それよりは、裁判官が判例に拘束されていることを前提として活動したほうが実際的であり、有効である。 たとえば、民事の訴えや刑事の公訴を提起するかどうかを決めるには、どういう裁判がなされるのかの見通しが当然必要となるが、その見通しを立てるのについて裁判官を拘束している判例が重要な意味を持つことは当然であろう。そう考えると、検察官や弁護士の仕事も、間接的には判例に支配されているということができる。判例が実務を支配しているという意味はそういうことである。 判例の事実上の拘束力として、仮に、下級審の裁判官が最上級審裁判所の判断に反する判断をすれば、その裁判は上訴の結果破棄されるであろうか