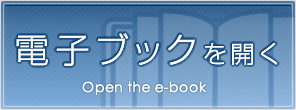逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 16/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている16ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
7ら、裁判官は判例に従って裁判をするのだといわれることがある。しかし、一般的にいうならば、判例と異なる判断をしたからといって、その判断が維持されることもあり、必ず破棄されると決まっているわけではないから、これは、あまり決定的な根拠にはならない。 裁判というものは国の作用であり、国の意思表示であって、裁判官は国の機関としてこれを行うのであるから、裁判は本来だれがそれを担当しようと同じであるべき性質のものである。この統一のための仕組みとして上訴制度がある。この仕組みを前提に考えると、上訴によって、事件は最終的に単一の最高裁判所に移り、その判断によって結局全国の裁判の統一が図られる。このことから、最高裁判所の判断が国の判断・意思表示として最終的・確定的なものであり、法律解釈についていうと国としての有権的解釈だということになる。それは、国の判断として一つの権威を持つことは事実である。そうすると、上訴審による是正はいわば次善の方法であり、本来的には、第一審段階ですでに最高裁判所が示すであろう判断がなされることが望ましいということになる。 最高裁判所がするであろう判断をどうやって発見するのか。それを予測する有力な手がかりは、その点に関してすでに最高裁判所の判例が存在すれば、その判例である。判例そのものは過去に終結した事件についての判断にすぎないが、最高裁判所の判例に限ってはこれを変更するのに特別の手続を必要とすることによってその変更に慎重であるべきことが制度上要請されているから、一般的いって変更されない蓋然性が大きく、したがって将来においても前の判例と同じ判断がなされるであろうという予測がかなり高い程度において成り立つからである。この結果、下級審の裁判官は、担当事件についても既存の判例と同じ判断がされるであろうという予測の下に、それを自己の裁判における判断とするわけで、裁判官が判例に従うということ、判例が裁判官を事実上拘束するということの意味はそこにあると考えられる。 そうすると、次のことがいえよう。? その第一は、真の意味で拘束力があるのは最高裁判所の判例だけだということである。それは、最高裁判所の判断を予測する材料となるのは最高裁判所の判例以外にないことから当然である。これに対して、最高裁判所