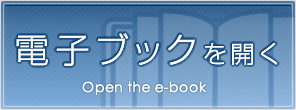逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 17/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている17ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
8 〔総論〕によってまだ是認されていない戦前の大審院の判例は、特別の手続を経ないで、すなわち小法廷で自由にこれを変更することができるから、変更されないことの制度的な保障はない。しかし、過去における最上級裁判所の判断であるから、最高裁判所も同様の判断をするであろうという予測がある程度成り立つので下級審判例とはその点で異なる。 最高裁判所によって下された法律的判断である以上、大法廷のものであろうと小法廷のものであろうと、また一回限りのものであるか繰り返されたものであるかを問わず、判例であることに変わりはない。そのいずれであっても、これを将来変更するには同一の手続を必要とし、それが維持される可能性は少なくとも制度上は同じだからです。 また、その判例が最高裁判所判例集に登載されたかどうかは、その判例としての重さに関係ない。? 判例の拘束力は事実上のものだといわれているが、その根底には最高裁判所のするであろうような判断をせよという裁判官の職務上の義務があるわけで、それは明文はなくともやはり法的な地位に基づく義務だというべきであるから、その意味では、この拘束には、間接的にではあるが、法的根拠があるといえる。事実上の拘束力とはいっても単なる事実の積み重ねが慣習法のように拘束力を生ずるという以上のものであるといえよう。? 第三の重要な帰結として、判例というものが将来の最高裁判所の判断の予測資料として意味を持つものだと考えれば、その「拘束力」は必ずしも絶対的なものではないということである。すなわち、それが「拘束」するのは、最高裁判所がそれと同じ判断を将来もするだろうと予測される(通常はそう予測してよい)限りにおいてであって、もし何らかの理由からそれとは違う判断のなされることが期待されるならば、判例は予測資料としての機能を失い、したがって「拘束」しないということになる。判例の拘束力の限界である。