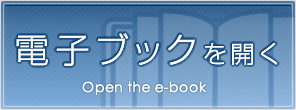逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 19/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
10 判例各論 宅地を譲渡したとして譲渡所得の申告をした後に、譲渡は措置法35条1項に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすものであるとして更正の請求をしたところ納税者の主張が認められなかった事案について、当事者の合理的意思解釈の内容で、一審は納税者敗訴となったが、控訴審では納税者が勝訴した事例〔東京高等裁判所・平成22年7 月15日判決・平成21年(行コ)第372号〕(納税者勝訴、確定)〔東京地方裁判所・平成21年11月4 日判決・平成20年(行ウ)第578号〕(国側勝訴)〔平成20年4 月18日裁決・東裁(所)平19-167〕1 事案の概要 本件は、宅地を譲渡したとしてその譲渡所得に対する所得税の確定申告をした原告が、譲渡は措置法35条1 項(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下、この章において、「旧措置法」という。)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとして、通則法23条1 項に基づいて更正をすべき旨の請求をした事案である。2 前提事実? 原告(長女)は、乙(父)と丙(母)の長女であり、兄と弟の2 人の兄弟がいた。? 父は、平成11年に死亡したところ、当時、A土地の所有権及びA土地上にある本件建物の持分4 分の1 を有していた。? 兄は、昭和40年ころ結婚し、兄夫婦には二人の子がいた。そして、兄建物の一部を取り壊してから共有持分を贈与したと認定するか、建物を分割し共有持分を相互に放棄したと認定するかで結論が異なった事例Ⅰ