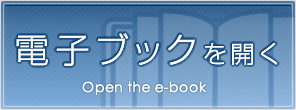逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 2/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている2ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
i推薦にあたって 本書は、数々の著名な難事件において、東京国税局の担当官という立場で国側代理人を務めた百戦錬磨の著者(ここでは親しみを込めて、安井さんと呼ばせて頂く)が、近時の国側敗訴判決について、詳細な分析を施した書物である。 私は、2000年に弁護士登録して以来、16年が経つが、その間、2011年7月に東京国税不服審判所において国税審判官に任用され(いわゆる任期付公務員)、3 年間そこで勤務した。 そこで出会ったのが、安井さんである。審判所に着任した当時、安井さんは私の左隣の席に座っていらしたので、お話を伺う機会が多々あり、担当官として数々の事件で法廷に立たれたご経験を元に、国税当局の思考が、裁判所をはじめとする法律家の目から見て如何におかしいか、周りの職員の方々にうるさがられるほどに、滔々と語られた。安井さんの議論は、法律家の端くれである私にとって、自然に頭に入ってくるものであった。 実は、私と安井さんが審判所で勤務していた時期から最近に至るまでの数年間は、国側敗訴判決、しかも、第一審で国が敗退し、そのまま控訴もされずに確定してしまう判決が多かった時期でもある。安井さんはよく、「一審で引き下がるような処分をするものではない」、「一審で負けるくらいなら、審判所でなぜ取り消さないのか」と憤慨しておられた。それは、国税組織への限りない愛情によるものであると、私には感じられた。 本書では、そうした国側敗訴判決が多数取り上げられ、どうして国側が負けたのか、そのことから何を読み取るべきなのか、様々な角度から分析されている。その広さ・深さは相当のものがある。このような質量共に卓越した分析は、「税務と法務のバイリンガル」である安井さんでなければ、為し得ない。税務専門家・法務専門家のいずれが読んでも得るところの多い、濃密な書物となっていると思う。 税の世界は今や、「税務」と「法務」、どちらの視点が欠けても成り立たない、厳しい反面で、知的意欲を持った人々にはとても面白い時代に突入している。この時代を生き抜くうえで、国税職員としての長年の課税実務