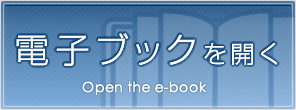逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 25/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている25ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
16 判例各論? 事実認定と適用 【争点①】について地方裁判所高等裁判所 本件建物の構造及び利用状況に照らすと、本件建物につき実質的には本件家屋部分と本件残存家屋部分の2 棟の建物であったと評価することはできず、また、本件家屋部分につき構造上区分されることにより独立して住居としての用途に供することができるものに当たると評価することもできないことに加え、本件の事実経過の下においては、本件家屋部分の取壊し後も本件残存家屋部分につき原告(長女)が持分4 分の1 を有し、これを丁(兄の妻)に贈与したと評価されることなども併せ考慮すれば、平成16年6 月から7 月に行われた本件建物中の本件家屋部分の取壊しをもって、原告(長女)がその居住の用に供している家屋全部を取り壊したと評価することはできない。 また、本件建物の各登記の状況からすると、本件家屋部分が取り壊された時点で丁(兄の妻)が当然に本件残存家屋部分につき単独で所有権を有することとなるとする合意等がされたことを認めるに足りる証拠はない。 そして、本件においては、本件建物は、その一部取壊し後もいまだその経済的効用を維持しているのであるから、原告(長女)が本件残存家屋部分に居住し続けずに転居したとしても、旧措置法35条1 項は適用されないというべきである。 原告(長女)と丁(兄の妻)の本件建物一部取り壊しに至るまでの本件建物での居住の実情とその経緯、本件遺産分割の内容、さらに、実際に本件建物が丁(兄の妻)の居住部分を除いて取り壊され、原告(長女)が本件建物から転居するに至った経緯に照らすと、本件合意がなされたとみるのが当事者の合理的意思解釈として素直な見方というべきである。 当事者間の合意としては、一棟の建物の一部についてその所有権を移転することは可能というべきであり、実際に移転部分についてこれを建物として取得し、登記上も反映させるためには区分建物としての実態を整えるための作業が必要となるところ、最終的には取り壊しが予定されていたためにそのような措置を採らず、本件建物取り壊しに関する合意を踏まえて本件のような便宜の登記が経由されたとみるのが相当である(本件合意の趣旨からすると、当事者の合理的意思解釈としては、本件建物の一部取り壊しに際しては、その部分に対する丁(兄の妻)の共有持分の放棄がなされることとの見合いで、残存家屋部分に対する原告(長女)の共有持分の放棄がされることが合意されていたとみるべきであり、贈与ではなく放棄としたほうが権利の実体に沿うものである。)。・・・(省略)・・・そうであるとすれば、土地上に一棟の建物が存する場合において、土地建