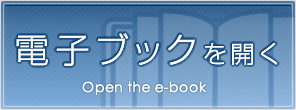逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 30/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
Ⅰ 居住用財産の譲 渡 21する証拠は存在しない。しかも、被控訴人(課税庁)もこの事実につき「不知」と述べるのみで積極的には争っていない。 以上のとおり、共有物である建物を取り壊して残存家屋の単独所有権を兄の妻に取得させ、その登記を行うことについて、当事者間に同意があったことは証拠上明らかであり、原判決には事実誤認がある。ない。? 高等裁判所内での原告の主張と裁判所の判断原告(長女・控訴人)の主張高等裁判所の判断【争 点 ②】 旧措置法35条1 項の趣旨からすると、その趣旨を達成するためには、本来、同項の要件に該当する場合にはすべて本件特別控除を適用すべきであるといえる。・・・(省略)・・・したがって、「やむを得ない事情があるとき」に該当する場合は幅広く認められるべきであり、納税者に対して本件特別控除の適用を拒否することが不当又は酷になる場合を広くいうと解するべきである。 本件において、原告(長女)は、所轄税務署を4 回訪問し、担当官に本件特別控除の適用を望む旨を伝えた上で、それが認められるか否かを相談するという慎重な対応をしたが、いずれの際も、本件特別控除の適用がない旨の回答を受けた。 また、原告(長女)は、税理士にも本件特別控除の適用について相談したが、本件特別控除の適用を受ける前提で確定申告を行った場合に更 証拠及び弁論の全趣旨によれば、①原告(長女)は弟とともに、本件確定申告書を提出するに際して、再三にわたり所轄税務署を訪れ、担当官に対して、旧措置法35条1 項の適用を望む旨を伝え、これが認められるかどうかについて相談したが、所轄税務署からは、いずれの相談に際しても、本件は建物の一部譲渡であるから認められないとの回答がなされたこと、原告(長女)は、弟を通じて、税理士とも相談したが、本件については、判例も前例もない難解な問題であるとのことであり、後に処分を受けて加算税を課せられた場合のリスクは大きいと考え、本件の特別控除を適用しての申請を断念したこと、②しかし、その後に右の税理士から、法律の解釈が不明であるために加算税が課せられることを避けるために税務署の見解に従った申告をせざるを得なかった場合にも、1 年以内であれば更正の請求を行う