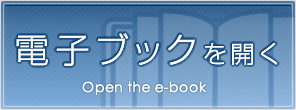逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 31/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている31ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
22 判例各論正処分を受けることがないとの確信まではないとの回答を受けた。 さらに、本件のような事例に係る判例等の先例もない。かかる状況の下で、本件特別控除の適用を受ける前提で確定申告を行えば、後に更正処分を受けることは明らかであり、訴訟において敗訴する危険性もあった。このような場合、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分がされることを承知の上で課税庁の見解に反する申告を納税者に強制することは納税者に酷であるし、いったん課税庁の見解に従った申告をした後に更正の請求を認める方が納税者の事前の納税義務の履行を確保することになり、被告の利益につながる。 現実に、過少申告加算税を支払う危険を避けるため、いったん課税庁の見解に従った申告を行った後に、更正の請求を行うことは一般に行われている。ことができるとの助言を得て、平成18年12月27日に所轄税務署長に対して更正の請求をしたことが認められる。このような本件における法律解釈の難しさに加え、上記のような原告(長女)が本件譲渡について更正の請求をするに至った経緯に照らすと、原告(長女)が、本件特別控除の適用を受けようとする旨を記載した確定申告書を提出しなかったことについては、旧措置法35条3 項が規定する「やむを得ない事情」があったと認めるのが相当である。7 解 説? 地裁判決と高裁判決の事実認定の違い① 地裁の認定 地裁判決は、ア 平成16年6 月末から同年7 月初めころまでの間に、本件家屋部分の取壊しがされ、原告(長女)が平成16年7 月7 日に本件建物の持分4分の1 につき丁(兄の妻)に対し、同月3 日の贈与を原因とする所有権移転登記をしたことを重視して、本件家屋部分の取壊後も本件残存家屋部分につき原告(長女)が持分4 分の1 を有し、これを丁(兄の妻)に贈与したものと認定する一方、イ 本件建物の各登記の状況からすると、本件家屋部分が取り壊された