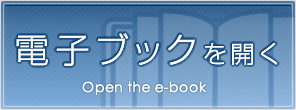逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント page 32/32
このページは 逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント の電子ブックに掲載されている32ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
逆転裁判例にみる事実認定・立証責任のポイント
Ⅰ 居住用財産の譲 渡 23時点で丁(兄の妻)が当然に本件残存家屋部分につき単独で所有権を有することとなるとする合意等がされたことを認めるに足りる証拠はないとして、そのような合意が存在したとする原告(長女)の主張を退けている。 控訴人・原告(長女)は、この点について、控訴審で、本件建物の一部を取壊し、残存家屋の単独所有権を丁(兄の妻)が取得することについて、事前の合意があったことは、多数の証拠が存在するうえ、その事実の存在を否定する証拠は存在しない。しかも、被控訴人(課税庁)もこの事実につき「不知」と述べるのみで積極的には争っていない、との主張をしている。 しかしながら、地裁判決は、残存家屋の単独所有権を丁(兄の妻)が取得する旨の合意があったこと認定していないわけではなく、丁(兄の妻)が単独所有権を取得するタイミングは本件家屋部分が取り壊された時点ではなく、本件家屋部分が取り壊された時点では、原告(長女)は残存家屋の持分の4 分の1 を取得しており、その後、原告(長女)はこの持分を丁(兄の妻)に贈与し、最終的に丁(兄の妻)が残存家屋の単独所有権を取得したと認定している。 地裁が、本件家屋部分の取り壊しの時点では、残存家屋の単独所有権を丁(兄の妻)が取得したのではなく、残存家屋の持分の4 分の1を原告(長女)が有していたと認定した根拠は、原告(長女)の持分の4 分の1 を丁(兄の妻)に贈与した旨の登記があったためである。登記があると、これを覆す証明がない限り、登記された通りの事実が存在するものとの推定が働くからである。 原告(長女)は、その控訴審における主張から、旧措置法35条1 項の適用要件は「一連の行為の結果、自己の所有する住居を失い、新たな住居の取得の必要が生じたこと」と考えていたものとうかがわれ、原告(長女)のように考えると、丁(兄の妻)が残存家屋の単独所有権を取得したタイミングが、事前の合意に基づいて本件家屋の取り壊しの時点か、あるいは、その後の原告(長女)による持分4 分の1 の丁(兄の妻)への贈与の時点であるかは問題にする必要がないということになる。そうすると、原告(長女)が「証拠が多数」あるという