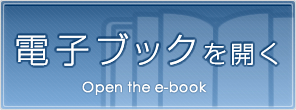税務サンプル|労務インデックス page 12/14
このページは 税務サンプル|労務インデックス の電子ブックに掲載されている12ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
税務サンプル|労務インデックス
使用者関係法条項労基法10、労契法2概要根拠条文等◆使用者とは・労働者を雇用して事業を行う者・労働関係の法律における「使用者」は、それぞれの条文によって、意味が異なる。◆それぞれの法律における「使用者」の定義1労基法「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」2労契法「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」3労組法使用者に関する定義規定なし*直接の雇用主でなくとも同法における「使用者」に当たるとされることがあるので、注意が必要である。4安衛法多くの規定で義務主体として「事業者」という概念を用いているが、それは当該事業における経営主体を意味し、個人企業にあってはその事業主個人、会社その他の法人の場合には法人そのものを指す。労基法10労契法22安衛法23○使用者とは社長のみを指すのか?上記の労基法の定義にある「事業主」とは、当該事業の経営主体、個人企業ではその企業主たる個人を、法人企業の場合は法人それ自体を、「事業の経営担当者」とは、事業一般について権限と責任を負う代表取締役や支配人を、「その他…事業主のために行為をする」者とは、人事や給与など労働条件の決定・管理、あるいは労務遂行の指揮命令などについて、権限と責任を有している者を指す。したがって、例えば、36協定を締結することなく時間外労働をさせていた会社において、労基法違反の罰則(労基法1191、32)が適用される可能性があるのは、代表者、人事担当役員、人事部長及び人事課長のすべてということになる(会社は、両罰規定(労基法121)によって処罰され得る。)。関連事項1法人格否認の法理と使用者例えば、子会社が解散した場合に、同社に雇用されていた労働者は、親会社に対し、雇用契約関係を主張し得るケースがあるであろうか。もちろん、親会社と子会社は別個の法人なのであるから、親会社が解散した子会社の労働者であった者との関係において雇用責任を負うことはないというのが原則である。しかしながら、法形式上は別個の法人格を有する場合であっても、法人格が全くの形骸にすぎない場合又はそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、特定の法律関係につき、その法人格を否認して衡平な解決を図るべきであるという法人格否認の法理は、労働関係4