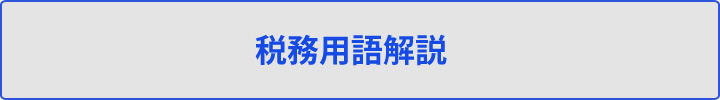
「みなす」と「推定する」の違い
税法の条文上では、「みなす」と「推定する」という用語が用いられています。
これらの言葉は、一見、同じ意味を表しているように思えるのですが、明確な違いがあり、条文上は使い分けがされています。
まず、「みなす」ですが、「本来は異なるものを法律上は同じものとして取り扱う」という意味です。
例えば、法人税法第3条では、人格のない社団等に対して、以下のような規定をおいています。
人格のない社団等は、法人とみなして、この法律( 略 )の規定を適用する。
人格のない社団や財団は、法律によって人格を与えられていないため、法人ではありません。しかし、この条文によって、法人税法上は、法人と同様に扱って各条文を適用することになります。
「みなす」という用語により、本来は異なる(法人ではない)ものをここ(法人税法)では同じもの(法人)として取り扱う、ということになります。
次に「推定する」ですが、これは「反対の事実や証拠がない限り、ある事実について法令が一応このように取り扱う」という意味です。
例えば、国税通則法第12条第2項では、以下のような規定があります。
通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
これは、通常の郵便等によって発送した書類は、通常到達すべき時に送達があったものとして取り扱う、というものです。
ただし、「推定する」ということですので、実際にはその日時より遅く送達があった、送達の事実がなかった、などの反証があれば、その事実に従うことになります。一方、先の「みなす」は、反証を許さず強引に事実を変えて取り扱うものです。ここが「みなす」と「推定する」の大きな違いとなります。