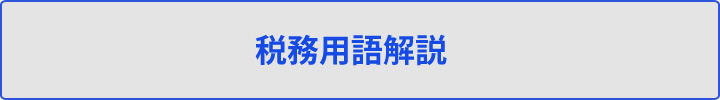
簡便法
「簡便法」とは、中古で取得した資産が、取得した時点で法定耐用年数のうち既に何年経過しているかにより、それぞれ次の算式により耐用年数を算出する方法をいいます。
①法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
②法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数 × 20%
(法定耐用年数 - 経過年数)+ 経過年数 × 20%
②法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数 × 20%
1.法定耐用年数とは
減価償却資産の耐用年数は、税法上は「減価償却資産の耐用年数に関する省令」に定める次の耐用年数表により、資産の種類や構造、用途などに応じて決定します。この法律で定められた耐用年数のことを「法定耐用年数」といいます。法定耐用年数は、新品の資産を前提として定められています。
| 別表第一 | 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 (建物・建物附属設備・構築物・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具・器具及び備品) |
| 別表第二 | 機械及び装置の耐用年数表 |
| 別表第三 | 無形減価償却資産の耐用年数表 |
| 別表第四 | 生物の耐用年数表 |
| 別表第五 | 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 |
| 別表第六 | 開発研究用減価償却資産の耐用年数表 |
2.中古資産を取得した場合の耐用年数の決め方
中古の資産を取得し、その資産の取得後の使用可能期間を見積もった場合には、法定耐用年数に代えて、その見積もった年数を耐用年数として減価償却費を計算することが認められています。
しかし、取得した資産が取得後あとどのぐらいの期間使えるかを見積もるのは、実務では難しいことです。そこで、使用可能期間を見積もることが困難な場合には、法定耐用年数のうち、取得時において既に経過している年数を考慮して耐用年数を算定する「簡便法」が認められています。
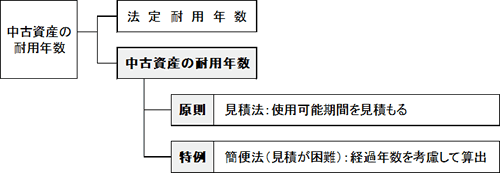
ただし、この簡便法が適用できる資産は、上記1の耐用年数表のうち別表第一、別表第二、別表第五、別表第六に掲げる資産に限定されています。つまり、別表第三に定められているソフトウエアなどの無形固定資産には適用することができません。また、中古の資産を取得した際に、多額の改良費を支出している場合にも適用することできないため注意が必要です。
【解説者】税理士 石井幸子