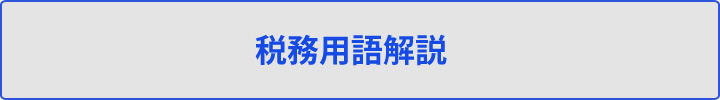
「その他」と「その他の」の違い
税法の条文上では、「その他」という文言が使われる場合、「Aその他B」と「Aその他のB」という2種類の使われ方があります。
これらの言葉は、一見、同じ意味を表しているように思えるのですが、明確な違いがあり、条文上は使い分けがされています。
まず、「その他」とは、「その他」の前に特記された事項と並列的な事項が多数予想される場合に使われます。
例えば、法人税法第34条第5項では、使用人兼務役員について、以下のように規定されています。
| 5 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員( 略 )のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。 |
次に、「その他の」とは、「その他の」の前に特記された事項が、「その他の」の後に書かれた事項に含まれる場合に使われます。つまり、例示の役割を果たすのが「その他の」です。
例えば、法人税法2条第22号では、固定資産について、以下のように定義しています。
| 22 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産で政令で定めるものをいう。 |
|
第12条(固定資産の範囲) 法第2条第22号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。 1 土地(土地の上に存する権利を含む。) 2 次条各号に掲げる資産 3 電話加入権 4 前三号に掲げる資産に準ずるもの |
【解説者】税理士 村木 慎吾