




|
|
1.受験と実務の違い
受験において配偶者の税額軽減は相続税計算上の一つの減算規定である。すなわち正しい金額を求めるというより、自分で算出した相続税の総額、課税価格合計額、配偶者の課税価格を基に計算処理することが求められる(もちろん正しい金額を算出した方が良い)。
一方、実務において配偶者の税額軽減は、一次相続における納付税額に大きく影響する規定であるとともに、配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の負担にも影響を与えることになる。
すなわち、配偶者の税額軽減は配偶者の相続する財産をどうするかにより、一次相続と二次相続の相続税の負担が変わる。相続税対策としての意味がある大変重要な規定である。
2.配偶者の税額軽減の特例
被相続人の配偶者は、被相続人の財産形成に貢献しているという点を考慮して、次の計算式により求められた金額が算出相続税額から軽減される(相法19の2)。
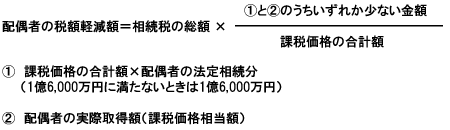
つまり、配偶者の税額軽減は配偶者の取得した財産が配偶者の法定相続分相当額以下、あるいは1億6,000万円までであれば配偶者の相続税の負担はなしという規定である。
この規定は、たとえ配偶者の税金がゼロでも相続税の申告をしなければならない。
3.配偶者の税額軽減の基礎となる財産
相続税の申告期限までに配偶者の取得することが決まっていない財産は、原則としてこの規定の適用はない。この場合は相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出する。
ただし、相続税の申告期限までに分割されていない財産が、次のいずれかに該当することとなったときには、それによって配偶者が取得した財産は、配偶者の実際取得額(課税価格相当額)に含めてこの規定の適用ができる。
・申告期限から3年以内に分割された場合
・申告期限から3年以内に分割できないことにつき、相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の一定のやむを得ない事情があるときには、納税地の税務署長の承認を受けその宅地等の分割ができることとなった日として定められた一定の日の翌日から4か月以内に分割されたとき(この場合は申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出する必要がる。)
<配偶者の税額軽減の計算例Ⅰ>
・相続人 妻と長男
・課税価格の合計額 5億円
・配偶者の課税価格 2億5,000万円
・相続税の総額 1億5,210万円
・配偶者の相続税額 7,605万円
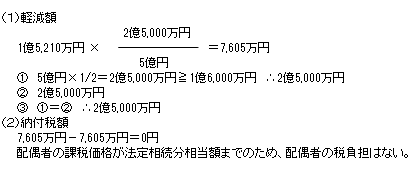
<配偶者の税額軽減の計算例Ⅱ>
・相続人 妻と長男
・課税価格の合計額 2億円
・配偶者の課税価格 1億6,000万円
・相続税の総額 3,340万円
・配偶者の相続税額 2,672万円
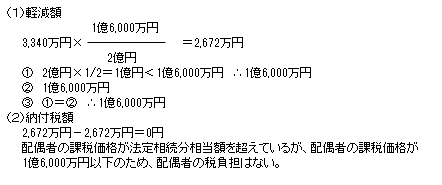
4.実務の留意点
相続税の負担に大きく影響を与える規定であるがゆえに納税者の関心も高い。納税者には早めに分割要件があることを説明した方が良いと思う。また、実務で納税者からよくある依頼は、「配偶者の相続する財産によって一次相続と二次相続の相続税はどうなるのか」というものである。税理士がこの依頼に対して回答するためには、配偶者自身の固有財産も把握しないと二次相続の税負担は分からない。したがって、一次相続の申告手続きの中で直接関係はないが配偶者の固有財産もある程度把握し対応することになる。
|
|
 |


 |



