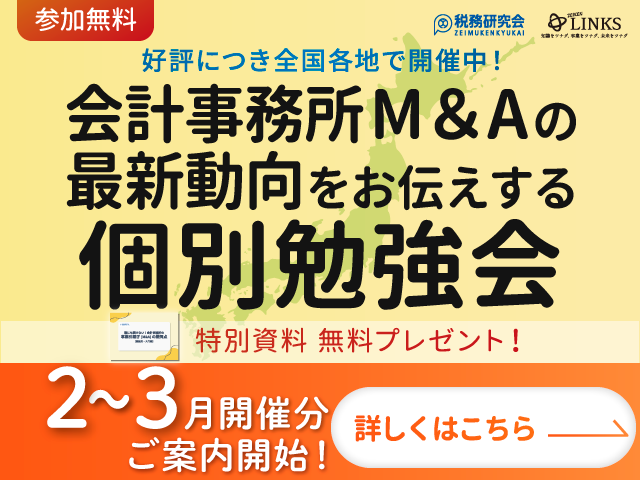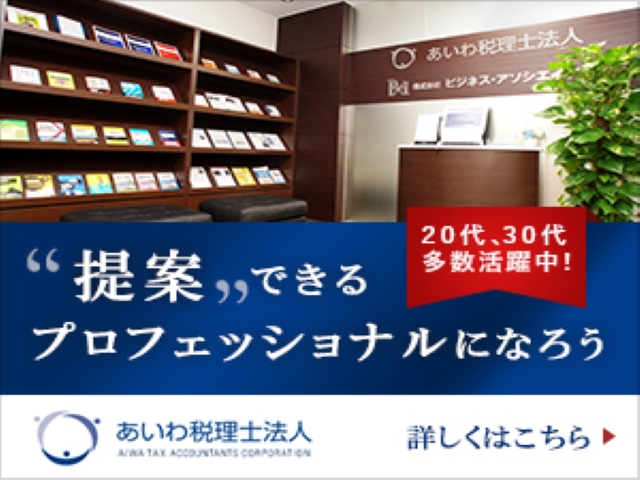【審理部】形式審査(その2)~不服申立適格~
[あいわ税理士法人 News Letter 2025.3]
2025/04/01
【審理部】形式審査(その2)~不服申立適格~
1.はじめに
国税不服審判所では、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者から審査請求書が提出された場合、まず最初に形式審査を行い、当該形式審査をクリアした場合は実質審理に入り、クリアできない場合には、実質審理に入ることなく却下処分(門前払い)が下されます。
形式審査では、審査請求書の記載事項に不備がないか、本案審理要件を満たすか否かの審査が行われ、本案審理要件には、主に、①不服申立期間、②処分該当性、③不服申立適格、④請求の利益の4つの項目が挙げられます。
本稿では、本案審理要件のうち③不服申立適格について解説いたします(注1)。
(注1) 形式審査の概略、審査請求書の記載不備と補正方法及び不服申立期間については2025 年3月10 日掲載ニュースレターを、処分該当性については2025 年1月27 日掲載ニュースレターを参照。
2.不服申立適格とは
不服申立適格とは、端的にいえば、審査請求書を提出した者が、審査請求をする資格を有しているか否かという問題です。
これに関しては、行政不服申立ての当事者適格に関する判例ではあるものの、不服申立適格を有する者について、「当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」(最判昭和53 年3月14日・民集32 巻2号211 頁。いわゆる主婦連ジュース訴訟事件)と判示されており、税務上の不服申立てについても同様であるといえます。つまり、国税に関する法律に基づく処分に不服があれば誰でも審査請求ができるわけではなく、当該処分により自己の権利や法律上保護された利益を侵害されない第三者は審査請求をすることができないのです。
この点、課税処分の場合には、処分の「名宛人」であれば、原則として不服申立適格を有し、実際の審査請求でも殆どがこのケースといえるでしょう。また、国税通則法第106 条《不服申立人の地位の承継》第1項では、(本人である)不服申立人が死亡したときは、相続人が不服申立人の地位を承継する旨が、同条第2項では、不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があったときは、合併法人若しくは合併新設法人又は分割承継法人(注2)が不服申立人の地位を承継する旨規定されているため、これらの者も不服申立適格を有していることになります(注3)。
なお、同条第4項では、滞納処分を念頭に、不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者も、不服申立人の地位を承継をすることができる旨規定されていますが、この場合は、国税不服審判所⾧等の許可を得る必要があります。
(注2) 分割承継法人が承継するのは、分割法人に対してされた課税処分ではなく、承継した財産に対してされた滞納処分となります。
(注3) この他、不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても同様です。なお、不服申立人の地位を承継した者は、その旨を国税不服審判所⾧等に届け出なければなりません。
3.源泉所得税に係る納税告知処分と不服申立適格
源泉所得税の納税告知処分について不服申立適格を有するのは、源泉徴収義務者である支払者であり、国との間で直接法律関係が生じない受給者は不服申立適格を有しません(最判昭和45 年12 月14 日・民集24巻13 号2243 頁)。
例えば、給与所得に係る源泉徴収に関して納税告知処分がされた場合(給与課税すべきものに源泉徴収漏れがあったとき)に、その徴収処分について不服申立てができる者は給与に係る源泉徴収義務者である会社(給与の支払者)であって、会社から追加徴収を求められる役職員(給与の受給者)ではないという点に注意が必要です。
4.徴収処分と不服申立適格
(1) 滞納処分
上記2.で述べたとおり、課税処分の場合、処分の「名宛人」であれば原則として不服申立適格を有し、名宛人以外の「第三者」の場合には、通常不服申立適格を有しません。
しかし、滞納処分においては、「第三者」であっても自己の権利や法律上保護された利益が侵害されるケースがあり、不服申立適格が認められるケースとして以下が挙げられます。
① 差押え財産の担保権者
差押え財産に担保権者がいる場合、担保権者は、差押えにより自己の権利、利益が侵害されるので、差押処分の取消しを求めることができるとされています。
② 差押え財産が共有財産である場合の他の共有者
差押え財産が共有財産である場合、当該共有財産の他の共有者は、その差押処分の法的効果によって権利の制限を受けることになるため、差押処分により自己の権利を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者として、差押処分の取消しを求めることができるとされています。
③ 被差押債権の第三債務者
差押え財産が債権である場合、当該債権に係る第三債務者は、本来自由になし得る滞納者への弁済を禁じられ(注4)、不利益を受けることから、債権差押処分の取消しを求めることができるとされています。
(2) 国税徴収法第39 条の第二次納税義務者
第二次納税義務とは、納税者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められる場合において、一定の要件を満たす特定の第三者に対して補充的に納税義務を負わせることをいい、国税徴収法(以下「徴収法」といいます。)では、第二次納税義務が成立するケースとして9種類を規定しています(注5)。
第二次納税義務者として納税告知処分を受けた者は、自己が受けた処分について不服申立適格を有することはもちろんですが、さらに、滞納処分を受けた本人(以下「本来の納税義務者」といいます。)の課税処分に対しても不服申立適格を有するか否かが問題になります。つまり、第二次納税義務者は、本来の納税義務者が受けた課税処分との関係でいえば「第三者」に当たるため、上記2.で述べた原則から考えれば、不服申立適格を有しないと考えられるからです。
この点について、徴収法第39 条(脚注4参照)に関する判例ではありますが、「第二次納税義務者は、主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消によってこれを回復すべき法律上の利益を有するというべきである。」(最判平成18 年1月19 日・民集60 巻1号65 頁)と判示されており、本来の納税義務者の課税処分に対しても不服申立適格を認めています(注6)。これは、第二次納税義務者の基本的内容は、主たる課税処分(本来の納税義務者に対してされた課税処分のこと)において定められるのであり、違法な主たる課税処分によって主たる納税義務者の税額が過大に確定されれば、第二次納税義務の範囲も過大となり、違法を理由に取消されれば、第二次納税義務の範囲も消滅又は減少する関係にあるためです。
また、これに続く問題として、第二次納税義務者が本来の納税義務者の課税処分に対する不服申立適格を有する場合に、不服申立期間の起算日に係る「処分があったことを知った日」とは、第二次納税義務者にされた納税告知処分の日なのか、本来の納税義務者にされた課税処分の通知日のいずれなのかという問題があります。
この点についても、上記判例では、第二次納税義務者に対する納税告知(納税通知書の送達)がされた日を「処分があったことを知った日」とし、同日の翌日を不服申立期間の起算日と判示しています。
(注4) 徴収法第62 条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項
(注5) 具体的には、徴収法第33 条《合名会社等の社員の第二次納税義務》、第34 条《清算人等の第二次納税義務》、第35 条《同族会社の第二次納税義務》、第36 条《実質課税額等の第二次納税義務》、第37 条《共同的な事業者の第二次納税義務》、第38 条《事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務》、第39 条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》、第40 条《偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務》、第41 条《人格のない社団等に係る第二次納税義務》の8種類があります。
(注6) 当該判例が他の第二次納税義務の類型にも当てはまるかは、さらに検討の余地があると考えます。
5.相続税及び贈与税の連帯納付義務と不服申立適格
第二次納税義務と似たものに、相続税法第34 条《連帯納付の義務等》に規定する連帯納付義務があります。これは、同一の相続に起因する遺産の総額を基礎として計算される相続税について、各相続人等に対し、自らが負担すべき固有の相続税の納税義務のほかに、他の相続人等の固有の相続税の納税義務についても負担させるものであり、同条第4項では、贈与税の連帯納付義務についても併せて規定しています(財産を贈与をした者は、当該贈与により財産を取得した者の贈与税について連帯納付義務を負う。)。
そして、上記4.と同様に、連帯納付義務者が、他の相続人等又は贈与により財産を取得した者に対する課税処分について不服申立適格を有するか否かという問題があります。
これについては、贈与税の連帯納付義務の事例ではありますが、「徴収法第39 条所定の第二次納税義務者と同様に、贈与税の連帯納税義務者も主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消によってこれを回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。」として、不服申立適格を認めた裁決(平成22 年2月4日裁決・裁決事例集No.79)があります(注7)。
(注7) 当該裁決は贈与税の連帯納付義務について判断したものであり、相続税法第34 条全般に当てはまるかは、さらに検討の余地があると考えます。
6.おわりに
本稿では、本案審理要件のうち不服申立適格について解説しました。
審査請求の多くは、課税処分又は徴収処分の名宛人が審査請求書を提出しているため、この限りにおいては、不服申立適格を満たさないということはありません。しかし、第二次納税義務や連帯納付義務が絡むと、その判断は複雑になり、さらにその射程がどこまで及ぶかにはなお検討の余地があります。
審査請求書を提出した者が、不服申立適格を有していないとして却下裁決が下された後に、改めて真に不服申立適格を有する者によって審査請求書が提出されたとしても、既に不服申立期間を徒過しており、やはり却下裁決が下されることも十分に想定されます。初動の判断誤りが、権利救済の途を閉ざすことになるため(注8)、くれぐれも注意したいものです(注9)。
(注8) 却下裁決の場合には、不服申立前置(不服申立てに対する行政庁の決定又は裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないという原則)を満たさないことになるため、訴訟に進むこともできなくなります。
(注9) 本稿の参考文献として、志場喜徳郎他共編『国税通則法精解』(大蔵財務協会、第17 版、2022 年)、中山裕嗣『租税徴収処分と不服申立ての実務』(大蔵財務協会、第二版、2015 年)、中里実他共編『租税判例百選(有斐閣、第7版52-53 頁、2021 年)
■本ニュースレターについて
本ニュースレターは、一般的な情報提供であり、具体的アドバイスではありません。個別の案件については個別の状況に応じて検討が必要になります。お問い合わせ等がありましたら、下記専門家まで遠慮なくご連絡ください。
審理部 税務調査総括担当(tax-investigation@aiwa-tax.or.jp)
税理士/元国税審判官 尾崎 真司
税理士/元国税審判官 村山 昌義
【あいわ税理士法人グループの概要】
◆グループ構成
あいわ税理士法人
あいわAdvisory株式会社
◆所在地
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル4F
◆URL
https://www.aiwa-tax.or.jp/
◆人員数
税理士・税理士有資格者:54名
公認会計士:13名
情報処理安全確保支援士:2名
行政書士:1名
科目合格者:8名
総務ほか:18名
合計:90名(一部重複)
◆関与先概要
上場グループ 305社 上場準備200社 非上場265社
あいわ税理士法人について
高度な専門知識と豊富な経験を持つ税務・会計のプロフェッショナル集団。約8割が有資格者と圧倒的に高い専門家比率が強み。東証一部をはじめ、新興市場に上場する企業からIPOを目指す成長企業、非上場の中堅オーナー企業を中心にサービスを提供。サービス内容は、IPO支援、組織再編、連結納税の導入、M&Aアドバイザリー、財務税務デューデリジェンス、国際税務、事業承継、役員給与設計、HD化支援等多岐に渡る。




 @zeiken_info
@zeiken_info