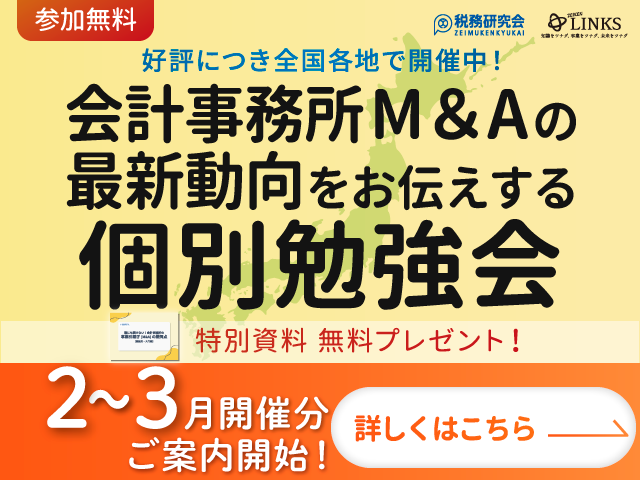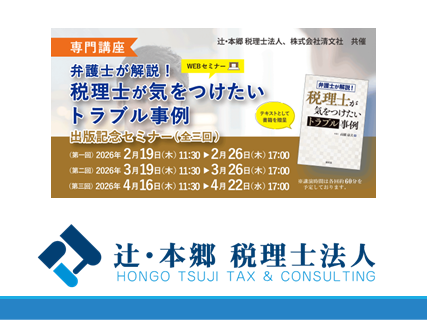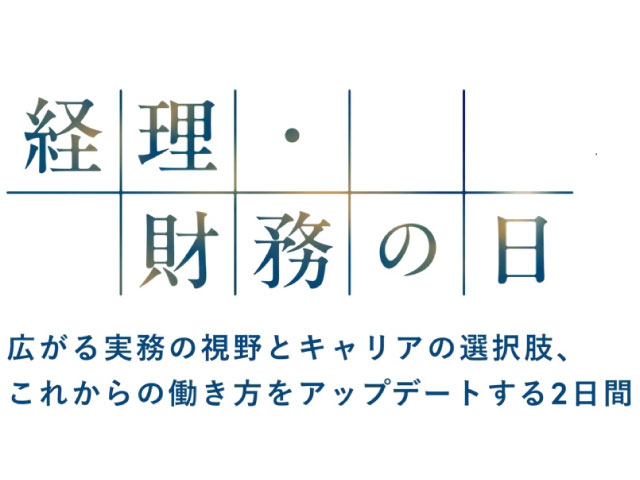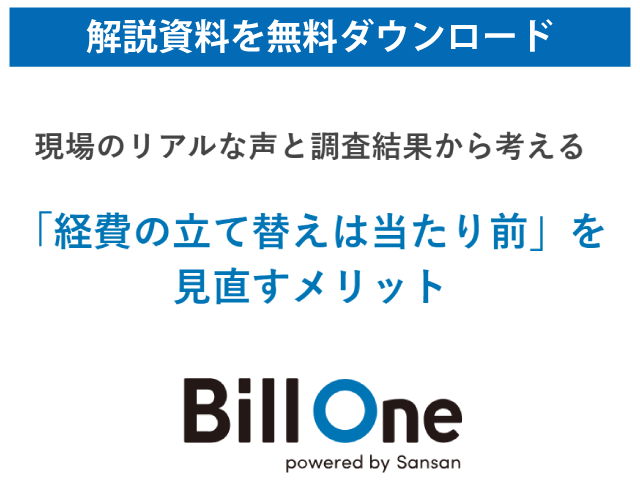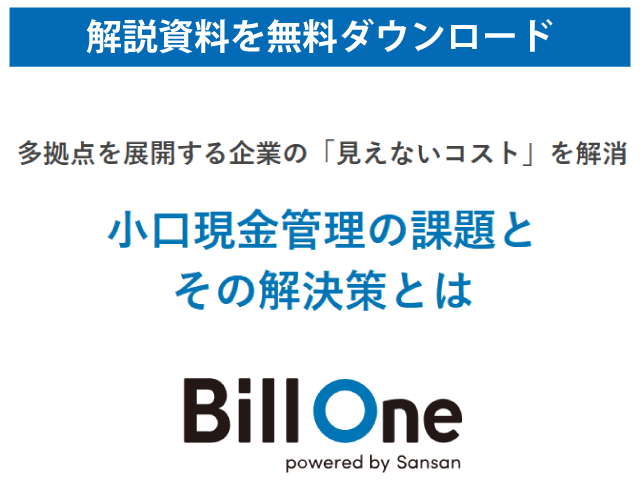第269回 新リース会計基準と税務との関係
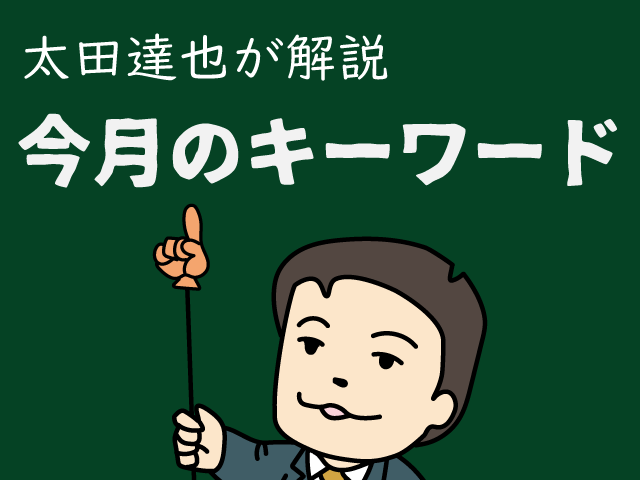
2025年5月1日
■リース取引に係る法人税法上の取扱い
リース取引に係る法人税法の規定は、次のとおりであり、今後も存置されます(法法64条の2第1項)。
|
売買があったものとして取り扱うため、従来借手においてはリース資産が償却資産として取り扱われ、利息相当額を区分する会計処理を行った場合には利息費用と減価償却費が損金算入され、利子込み法の会計処理によった場合には減価償却費が損金算入されるものとされてきました。
一方、貸手においては、リース資産の引渡しの時に譲渡があったものとして取り扱われますが、収益および費用をリース期間にわたって繰り延べて計上する延払基準が例外的に認められていました。この延払基準は、令和7年度税制改正により、経過措置が設けられた上で廃止が決定されました。
■法人税法上のリース取引の定義
法人税法上、リース取引は、次のように定義されています(法法64条の2第3項)。
|
上記の要件は、いわゆるファイナンス・リース取引に該当する要件(中途解約不能+フルペイアウト)と同様です。したがって、税務上、売買があったものとして取り扱われるのは、上記の2つの要件が満たされているリース取引(いわゆる一般のファイナンス・リース)であって、オペレーティング・リースについては、通常の資産の賃貸借と同様のものとして、賃貸借処理が適用されます。要するに、オペレーティング・リース取引は、レンタルと同様の賃貸借ととらえ、「リース取引」の定義から除外されており、賃貸借処理が当然に適用されるものとされています。
■法人税法上のオペレーティング・リースその他の資産の賃貸借に係る規定の新設
令和7年度税制改正により、資産の賃貸借で、先の2つの要件を満たすリース取引以外のものについて、次の規定が新設されました(法法53条1項)。いわゆる一般のオペレーティング・リースだけでなく、不動産の賃貸借契約等でリースの識別規定により新たにリースとして識別されるものについても、上記の2つの要件を満たすリース取引に当てはまらないものは、この規定の適用対象になります。
|
「その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」と規定されているように、債務確定した部分の金額が当然に損金算入されるのであって、損金経理要件は課されていない点に留意が必要です。
したがって、新リース会計基準を適用して、オペレーティング・リースについて使用権資産およびリース負債を計上した場合、使用権資産の償却費およびリース負債に係る利息費用を別表4で加算し、賃借料のうち各事業年度において債務の確定した部分について「賃借料認容」として減算する調整も可能となります。




 @zeiken_info
@zeiken_info