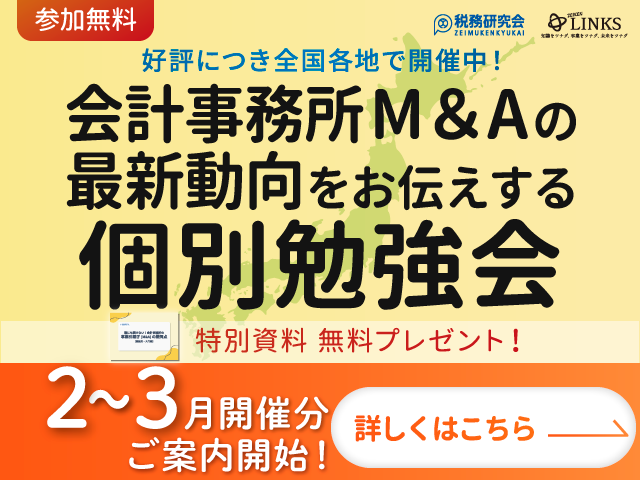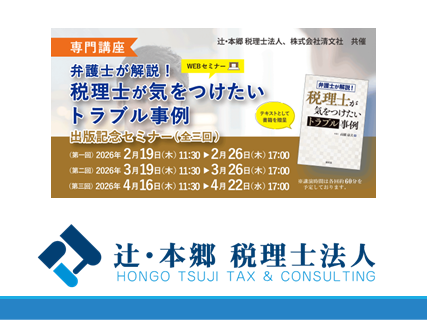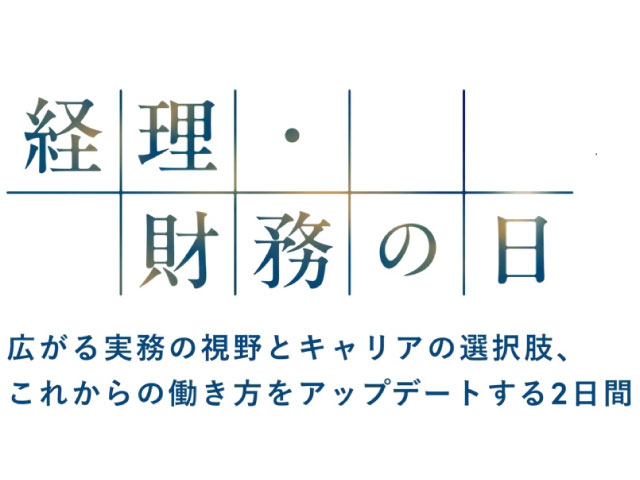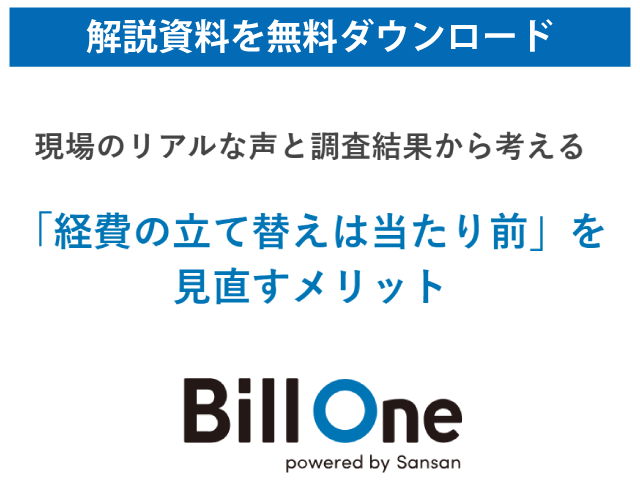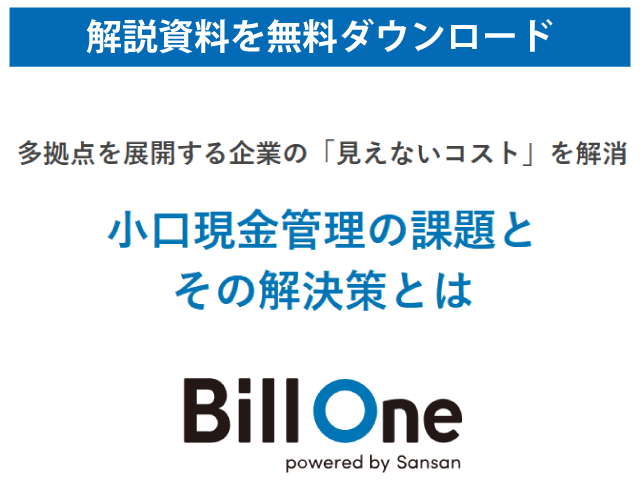第272回 新リース会計基準と税法との関係 ~法人税基本通達の公表を受けて~
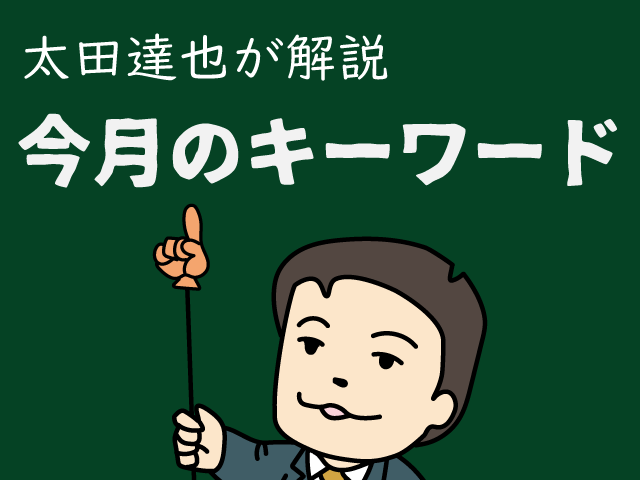
2025年8月1日
■リース税制の取扱い
税法上の「リース取引」は、従来どおり中途解約不能かつフルペイアウトの要件を満たしたもの、いわゆるファイナンス・リースです。なお、フルペイアウトの判定基準について、会計に合わせる判定方法を認める通達(法基通12の5-1-3)が公表されたため、新リース会計基準を適用する企業においては、基本的に会計上のファイナンス・リースが法人税法上のリース取引になると考えて問題ありません。
リース取引の借手の処理については、税法上のリース取引については、おおむね税会一致、それ以外のもの(オペレーティング・リース)については原則として税会不一致になります。以下、それぞれのリースについて説明します。
■ファイナンス・リースに係る会計基準等と税法との関係
所有権移転外リース取引については、法人税法上、売買があったものとして所得の金額を計算する旨の規定は、令和7年度税制改正後も存続します。会計に沿った税務処理が原則として認められます。
第1に、使用権資産に係る減価償却費は、税法上のリース資産に係る償却費として損金経理した金額として取り扱われます(法基通7-5-3)。
第2に、利息相当額の処理について、①リース料総額から利息相当額を控除し、利息法により配分する方法、②リース料総額から利息相当額を控除し、定額法により配分する方法、または、③リース料総額から利息相当額を控除しないで処理する方法(利子込み法)、以上のいずれの処理も税務上認められます。①および②については、利息相当額が会計基準等に準拠して合理的に区分されているのであれば問題ありません(法基通7-6の2-9)。
また、リース期間の取扱い、リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分の取扱いなど、基本的に会計基準等の処理を税務上認容する取扱いが示されています(法基通7-6の2-10の2、7-6の2-17、12の5-1-7)。
また、短期リース・少額リースや中小法人の取引において、借手が定額法による費用処理や賃貸借処理を行った場合であっても、賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用として損金経理した金額を償却費として損金経理した金額に含めると規定され(法令131条の2第3項)、その場合は原則として申告調整不要であり、別表16(4)減価償却に関する明細書への記載も原則として不要となります。
■ファイナンス・リースについて不一致が生じるケース(申告調整が必要となるケース)
減価償却方法について会計上、定額法以外の方法を採用した場合に申告調整が必要となります。税法上の借手側の償却限度額の算定方法は、リース期間定額法に限定されていますが(法令48条の2第1項6号)、会計基準は定額法等の減価償却方法の中から企業の実態に応じたものを選択適用した方法により算定するものとされており(会計基準38項)、会計上、定額法以外の方法を選択した場合には、税務上はリース期間定額法により償却限度額を計算するため、償却超過額または償却不足額が生じ、申告調整が必要となります。別表16(4)の明細書において、償却超過額または償却不足額を明らかにするなどの管理が必要になるものと考えられます。
■オペレーティング・リースに係る会計基準等と税法との関係
税法上のリース取引(いわゆるファイナンス・リース)以外のリースその他の資産の賃貸借取引はリース取引の定義から除外しており、当然に賃貸借処理が適用されます。令和7年度税制改正により、内国法人が資産の賃貸借で法人税法64条の2第3項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引以外のもの(以下、「賃貸借取引」という)によりその賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その賃貸借取引に係る契約をした事業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額があるときは、その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する旨の規定が新設されました(法法53条1項)。いわゆる債務確定基準です。
■オペレーティング・リースに係る申告調整の方法
「その支払うこととされている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。」と規定されているように、債務確定した部分の金額が当然に損金算入されるのであって、損金経理要件は課されていない点に留意が必要です。したがって、会計基準を適用して、オペレーティング・リースについて使用権資産およびリース負債を計上した場合、使用権資産の償却費およびリース負債に係る利息費用を別表4で加算(留保)し、賃借料のうち各事業年度において債務の確定した部分について「賃借料認容」として減算(留保)する調整を行うことが考えられます。この方法を「総額法」といいます。
なお、その事業年度における「使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額」として経理した金額が、オペレーティング・リース取引に係る契約に基づき支払う金額のうち債務の確定した部分の金額を上回る場合に、その上回る部分の金額を加算調整し、逆にその事業年度における「使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額」として経理した金額が、オペレーティング・リース取引に係る契約に基づき支払う金額のうち債務の確定した部分の金額を下回る場合に、その下回る部分の金額を減算調整する方法でも問題はありません。この方法を「純額法」といいます。
いずれの方法によるにせよ、リース契約の期間全体ではリース料として支払う金額の総額は同じになるため、最終的には会計上の費用と所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の総額は同額となります。




 @zeiken_info
@zeiken_info