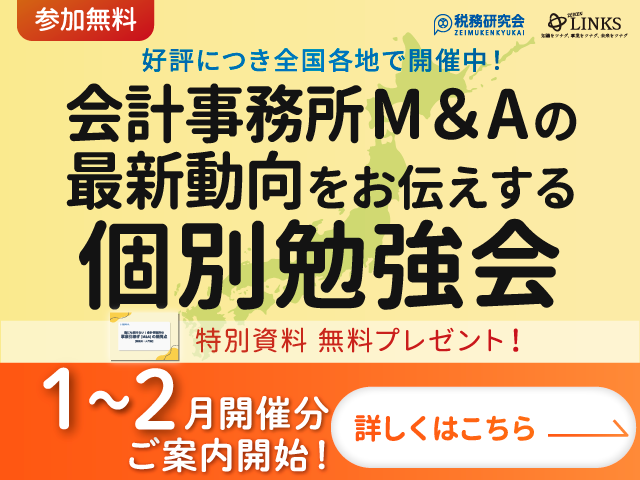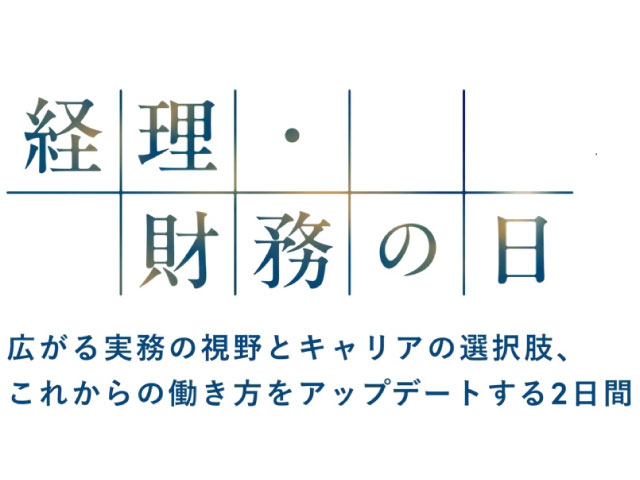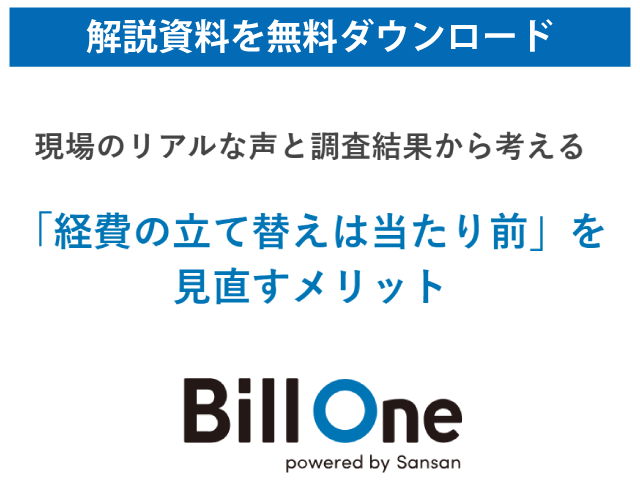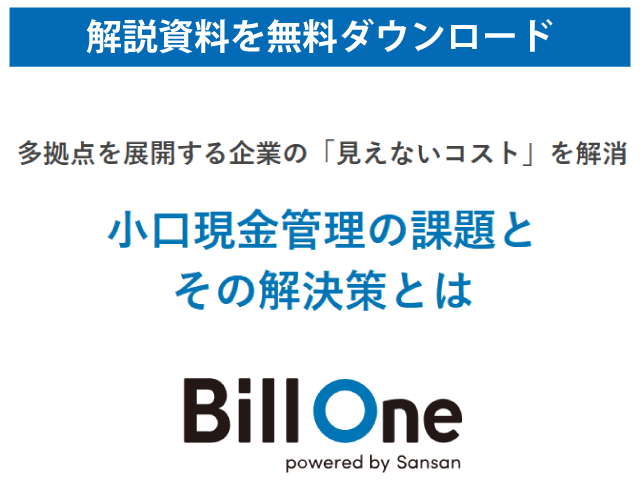取引単位営業利益法が使われる理由|税務通信 READER’S CLUB
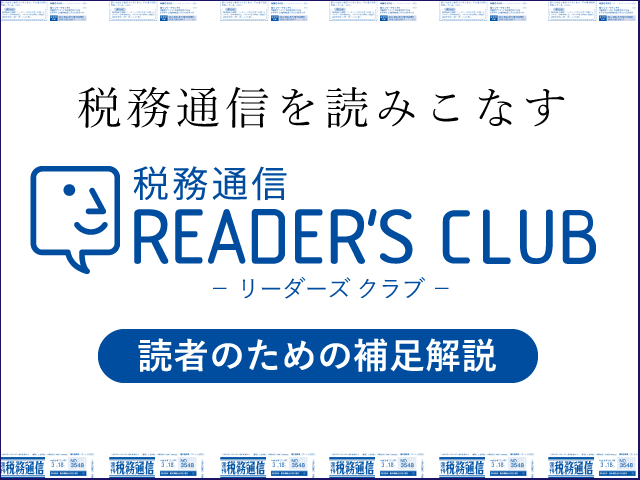
2025年9月11日
関連記事:No.3861(令和7年7月28日号) 04頁
この記事でもそうですが、移転価格税制における訴訟などでは、取引単位営業利益法(Transaction Net Margin Method, TNMM)での争いが多いように思います。独立企業間価格の算定方法はいくつかあるにもかかわらず、なぜ取引単位営業利益法を巡った争いが多いのでしょうか?
移転価格税制では、国外関連者との取引価格(移転価格)が、独立した第三者間で行われる「独立企業間価格」であるかどうかを判定するために、最も優先して適用されるべきとされる「基本三法」と呼ばれるものがあります。それが、独立価格比準法(Comparable Uncontrolled Price Method, CUP法)、再販売価格基準法(Resale Price Method, RP法)、原価基準法(Cost Plus Method, CP法)です。これらの方法は、取引の「価格」そのものに着目して比較を行うという特徴を持っているため、比較対象取引との間に非常に高いレベルの類似性(比較可能性)が求められます。
しかし、実務で利用するケースを想像していただければわかると思いますが、自社の取引と高いレベルで類似している他社事例を探すことは、非常に困難です。例えば、CUP法であれば、関連会社間取引と全く同じ製品を、全く同じ取引条件で第三者とも取引している、というケースは非常にまれです。また、RP法やCP法でも、関連会社が、その取引で担っている機能やリスク負担が、第三者と比較して完全に同じである、という証明をすることは不可能だとも思えるほどです。
一方で、適用順位では基本三法の後順位にはなりますが、TNMM法、日本語では「取引単位営業利益法」と呼ばれる方法があります。これは、関連会社間の取引から生じる営業利益率が、独立した第三者が類似の取引から得る営業利益率と比べて妥当な水準であるかどうかを検証する方法です。このように、TNMMは、取引単位の営業利益率を比較するため、取引内容や機能が完全に一致していなくても、同業種の企業であれば比較対象とできるケースが多くなります。つまり、同じ業界であれば販管費の構成が多少異なっていても、利益率が一定の範囲に収まることが期待できます。この「販管費がクッションになる」という性質が、比較対象の選定を容易にしているとも言えます。
このように、TNMMは、基本三法と比較すると、適用が比較的容易であるため、多くの企業や税務当局が、移転価格文書化や調査においてこの方法を採用しています。その結果、訴訟などに発展するケースでも、TNMMが争点となることが多くなっているのです。




 @zeiken_info
@zeiken_info