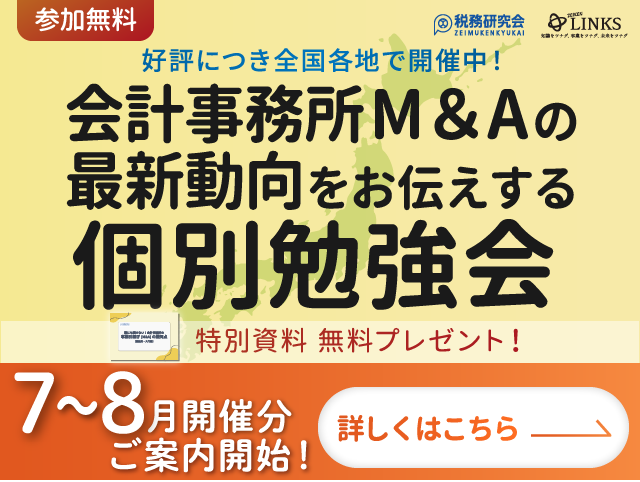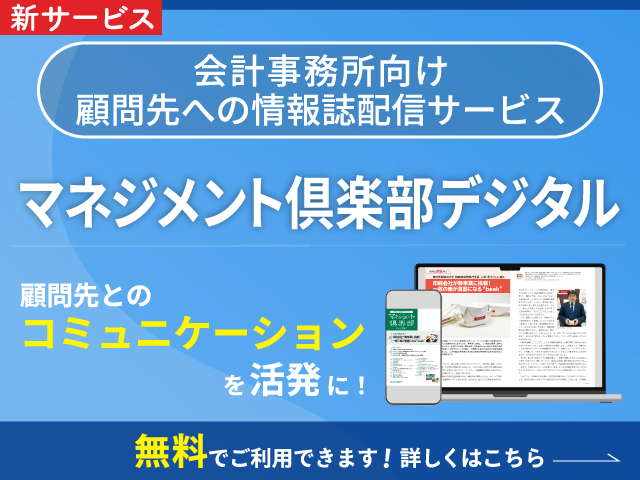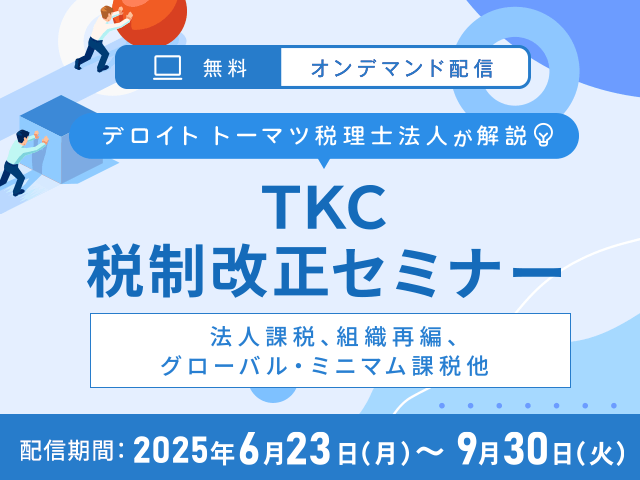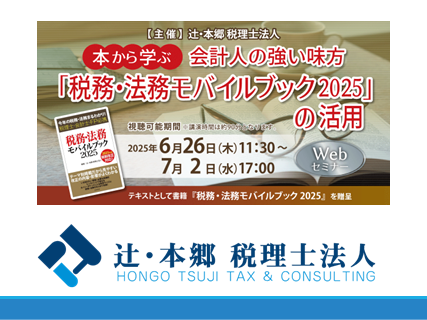区分所有するホテルの評価
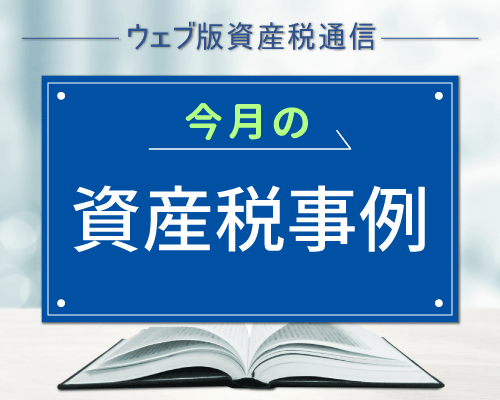
2025年1月20日
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
区分所有するホテルの評価
[質問]
近年富裕層向けに投資商品として拡大している「区分所有するホテル」についての相続評価ですが、以下のような前提条件で購入したホテル一室の相続税法上の評価はどのようになりますか。
(前提条件)
・購入者は、区分所有で登記されている物件を保有することとなる(小口化等の権利保有でなく区分1室を保有することとなる)
・謄本上の建物の表示は種類「客室」で登記されており、購入後もそのまま
・購入後所有者はホテル事業者に物件を賃貸し、ホテルとして運用している
・購入後所有者はホテル事業者に物件を賃貸しているが、優先予約等で別荘のように自己利用(宿泊)も可能
・対象は路線価があるエリア
このような場合、相続評価はどのようになりますか。
自己利用する権利がある物件であるが、建物は貸家、土地は貸家建付地の判断はどのように行うべきでしょうか。
種類「客室」であるが区分で所有なので先般のタワマン改正に当てはめて計算するのでしょうか。
(参考:タックスアンサー ※ハ参照)
No.4614 貸家建付地の評価|国税庁 (nta.go.jp)
※ハ 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。
[回答]
1 マンション通達の適用の可否
いわゆるマンション通達の制定が検討された「マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議」の資料をみると同通達において採用している評価方法は、全国の中古マンションの売買実例価額等をサンプル調査し、それに基づき算定した評価乖離率により評価対象マンションの通達評価額を補正する仕組みを採用しています。
このサンプル調査のためには、通常、多数の取引事例を収集する必要がありますが、市場で取引されている大半のものはいわゆる分譲マンションであり、それ以外のもの、例えば、区分所有者が存する二世帯住宅、専有部分が店舗及び事務所等の用途に供されているもの及び区分所有者がいない一棟の建物等については、取引事例そのものが少ないことから、マンション通達の適用対象は、いわゆる分譲マンションに限られたものと思われます。
このような制定経緯からすれば、ご照会のような分譲型ホテル(本件分譲型ホテル)は、そもそもマンション通達の適用対象外であると考えることもできます。
しかしながら、マンション通達においては、その適用対象を「居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権及び敷地利用権」と明記し、その定義について同通達に係る情報(令和6年5月14日付資産評価企画官情報第2号)では、「主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の種類に『居宅』を含むものがこれに該当します。(中略)なお、構造上、主として居住の用途に供することができるものであれば、課税時期において、現に事務所として使用している場合であっても、『居住の用』に供するものに該当することとなります。」と記載されています。したがって、評価対象物件の登記の種類が「居宅」ではなくても、構造上、主として居住の用途に供することができるものであれば、マンション通達の適用対象に含まれるものと解されます。
そうすると、本件分譲型ホテルの価額についてマンション通達の定めにより評価するか否かは、それが主として居住の用途に供することができるか否かという観点(なお、不動産登記法上の居宅とは、専ら人の居住の用に供される建物のことであり、建物所有者が自らそこに居住しているか否かは、居宅の要件として関係ありません。したがって、会社の社員寮や別荘、貸家など居住の用に供される状態にあるものは、居宅として取り扱われます。)、具体的には、本件分譲型ホテルにバス、トイレ及びキッチンなどの住宅設備が存するか否かによって判定するのが相当ではないかと考えます。
なお、ご照会の件については、公的見解が存しませんから、マンション通達の定めにより評価した価額が評価通達の定める評価方法により評価した価額を大きく上回る(又は下回る)場合には、所轄税務署へのご相談をお勧めいたします。
2 貸家及び貸家建付地として減額評価できるか
評価通達93《貸家の評価》及び同通達26《貸家建付地の評価》は、貸家及びその敷地の用に供されている宅地について減額評価する旨定めています。
これらの各定めの趣旨は、①借家権の目的となっている建物の賃借人は、一般にその建物に対する使用収益権を有するとともに、その敷地についても借家権に基づいて建物の利用の範囲内で敷地利用権を有しており、賃貸人は、自己使用の必要性等の正当の事由がある場合を除き、賃貸借契約の更新を拒絶したり、解約の申入れをしたりすることができないことから(借地借家法28)、借家権を消滅させるためには立退料の支払を要することになること、②借家人は、建物の引渡しを受けたときは、その後その建物について物権を取得した者に対し借家権の効力を対抗することができ(同法31)、建物に借家権を付着させたままで建物及びその敷地を譲渡する場合には、その譲受人は、建物及びその敷地の利用について制約を受けること等から、その建物及びその敷地の経済的価値が、借家権の目的となっていない建物やその敷地に比べて低くなることを考慮したことにあると解されます。
ご照会のケースについては、上記のような貸家及び貸家建付地の減額評価の趣旨からすれば、本件物件を貸家及び貸家建付地として減額評価することができるかどうかの可否は、本件物件に係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)により本件物件(専有部分)に借家権が生じているか否か、換言すれば、借地借家法の適用がある建物の賃貸借であるか否かがポイントになると考えます。
ご照会の文面からは、本件賃貸借契約の詳細が明らかではありませんが、貸主も本件物件を自己使用できるとされていますから、本件賃貸借契約が借地借家法の適用がある建物の賃貸借であるかどうかは、借主に本件物件の使用上の独立性・排他性があるか否か(東京地裁平成3年7月26日判決)が問題になるのではないでしょうか。
この点については、借地借家法の専門家にご相談をお勧めいたしますが、私見を述べさせていただければ、貸主の自己使用が法的に貸主の所有権に基づく使用ではなく、宿泊客として客室の利用と整理できるのであれば、本件賃貸借契約は借地借家法の適用がある建物の賃貸借と整理できることから、本件物件について貸家及び貸家建付地として減額評価して差し支えないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー




 @zeiken_info
@zeiken_info