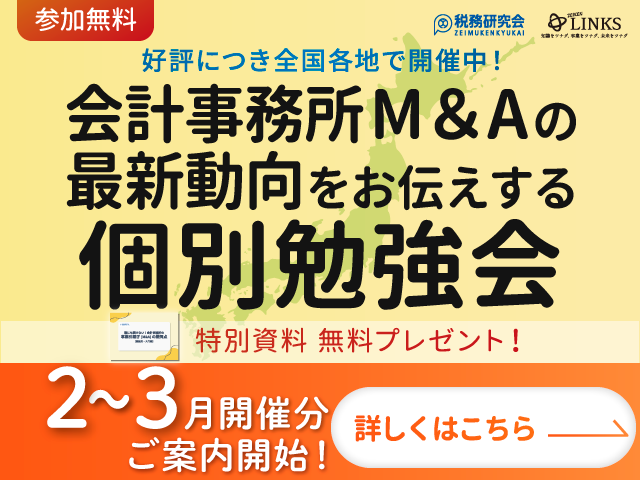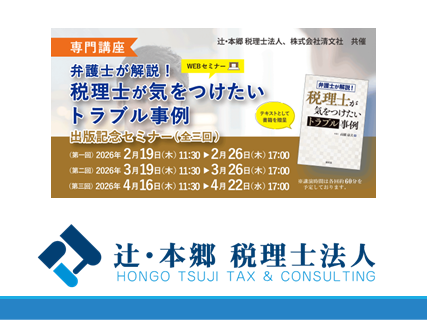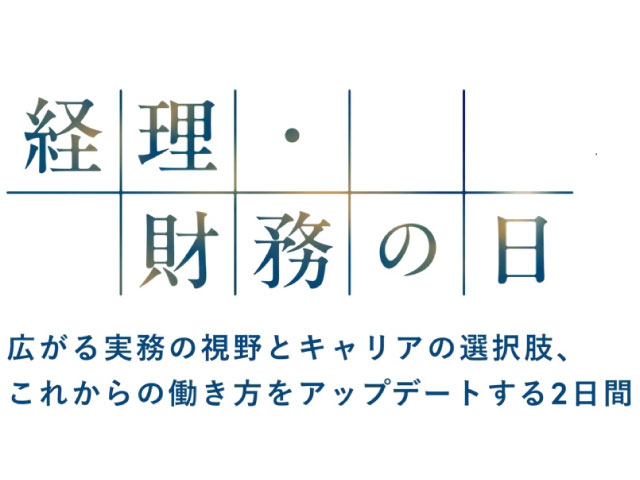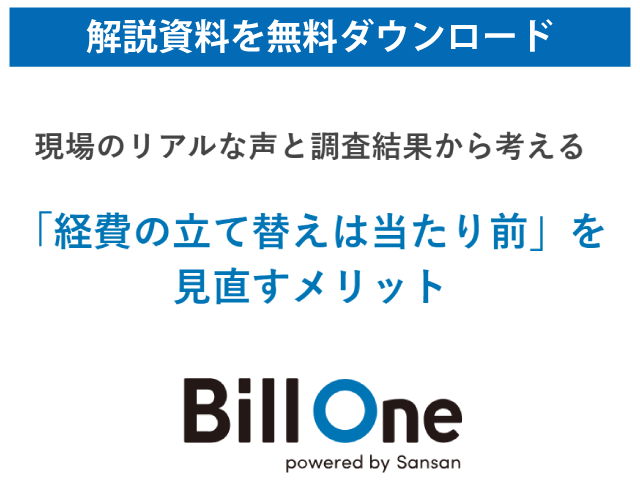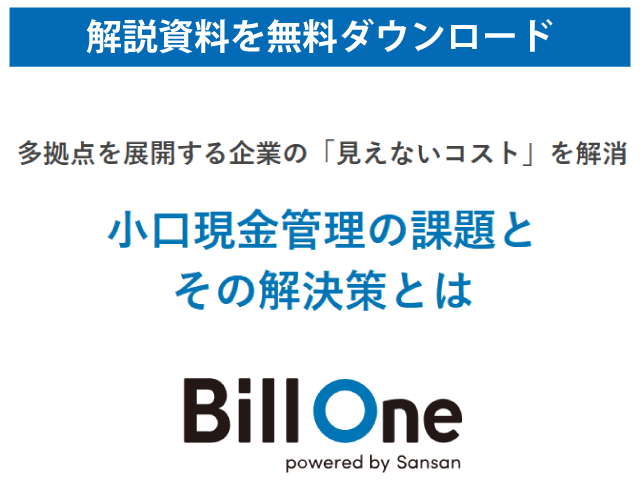事業承継税制の適用を受けた株式評価額に誤りがあった場合の更正の請求
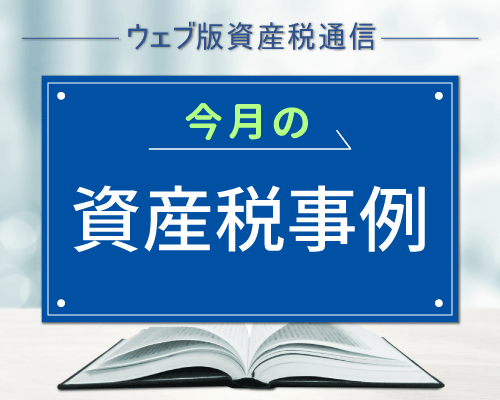
2025年7月30日
事業承継税制の適用を受けた株式評価額に誤りがあった場合の更正の請求
[質問]
(前提)
平成29年中の贈与として、歴年課税贈与により事業承継税制を適用し、贈与税について納税が猶予されていました。令和6年に贈与者に相続が発生し、相続税の納税猶予に切り替えて事業承継税制を適用し、相続税の申告が完了しています(現時点で申告期限も過ぎています)。
(照会内容)
平成29年の贈与の時の非上場株式の評価を確認すると株式評価に誤りがあり、1株当たりの価額が過大に評価されていました。相続税の納税猶予に切り替えた際にも、贈与時の株式評価額により切替申請され、相続税の申告書が提出されています。
したがって、相続税の納税額については、過大に納付している状況です。
この場合において、相続税を計算する際の株式評価額を贈与時の株式評価額とせず、適正に計算された株式評価額にて、相続税の更正の請求をすることは可能なのでしょうか。
なお、国税庁の質疑応答事例において、相続時精算課税贈与につき更正可能な期間を過ぎた場合に、相続税の申告における課税価格は是正した後の金額で申告することが可能との回答があります。
この取扱いに準じて、歴年課税贈与の更正可能期間が経過していることから、相続税の申告時にも是正を行うことは可能と考えても問題ないでしょうか。事業承継税制という特殊な特例を適用させている状況でも可能なのでしょうか。
また、これが可能とした場合、すでに相続税の申告期限は過ぎていますが、相続税の更正の請求は可能と考えても良いでしょうか。
[回答]
ご照会の事例は、平成29年に租税特別措置法第70条の7《非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除(一般措置)》の適用を受けた者が、令和6年に当該非上場株式等の贈与者の死亡により同法70条の7の3《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例》及び同法70条の7の4《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除》の適用を受けたものと思われます。
租税特別措置法第70条の7の4《非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除》は、「前条第一項の規定により同項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた対象受贈非上場株式等につき、この項の規定の適用を受けようとする経営相続承継受贈者が、当該相続に係る相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額のうち、当該対象受贈非上場株式等で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるものに係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、政令で定めるところにより、当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、相続税法第三十三条の規定にかかわらず、当該経営相続承継受贈者の死亡の日まで、その納税を猶予する。」と規定しています。
以上の規定から、当該納税猶予の特例は、期限内申告に係る相続税に限って認められるのが原則ですが、例外的に、措置法通達70の7の4-3《修正申告等に係る相続税額の納税猶予→同通達70の7-6を準用》により、修正申告又は更正があった場合でも、その修正申告又は更正が期限内申告書の提出により措置法第70の7の4第1項の規定の適用を受けた対象受贈非上場株式等の評価の誤り又は税額計算の誤りのみに基づくものであるときは、その修正申告又は更正により納付すべき相続税額(附帯税を除きます。)については、当初からこの納税猶予の特例の適用があるものとして取り扱うこととされています。
そうであれば、平成29年の贈与税の申告において対象受贈非上場株式等の評価誤りがあり、その誤った評価額をそのまま令和6年の相続税の申告において課税価額の計算の基礎に算入していますので、上記通達でいう評価誤りの範囲に含まれるものと思われます。また、この通達でいう更正は、国税通則法でいう更正(課税標準等又は税額等の増加又は減少)と考えられますので、誤っていた評価額を是正することにより令和6年の相続税の申告に係る課税価額又は税額が減少するのであれば、更正の請求により納税猶予額も含めて相続税額を更正してもらうことができると思います。
なお、平成29年の贈与税については、対象受贈非上場株式等の贈与者の死亡により免除されていますので、この納税猶予額については更正できないものと考えられます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)




 @zeiken_info
@zeiken_info