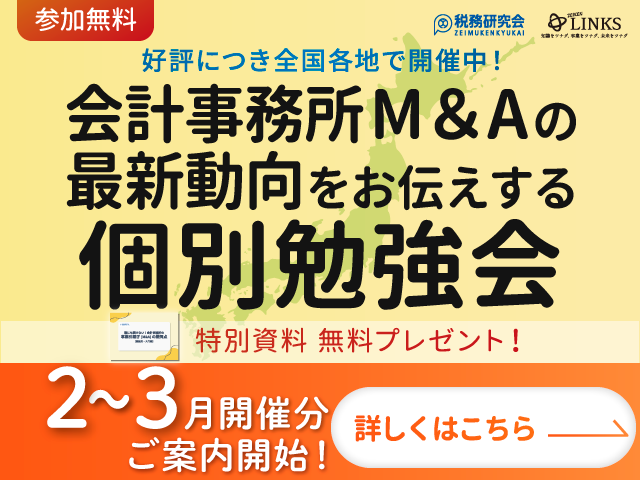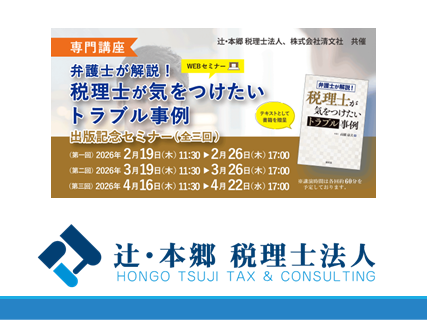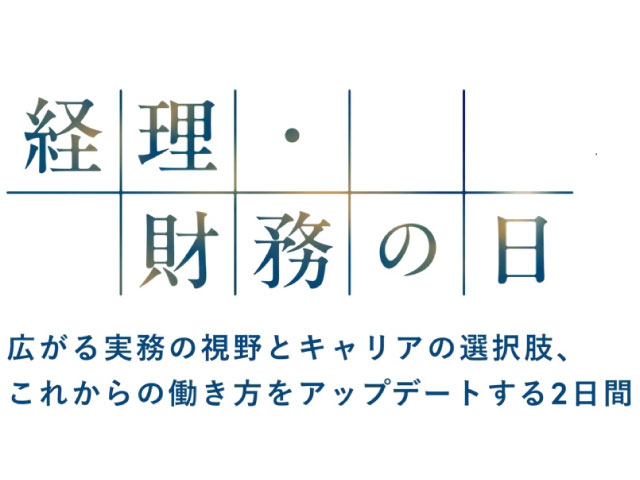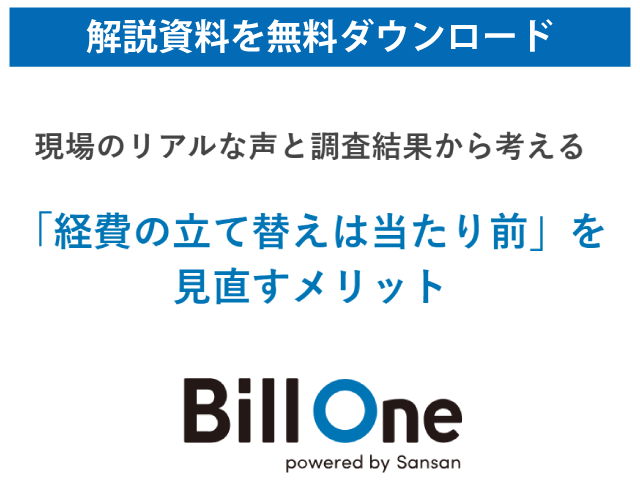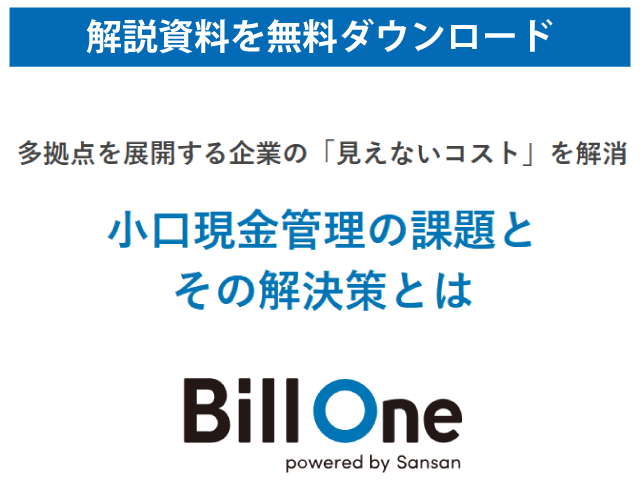農地の納税猶予について
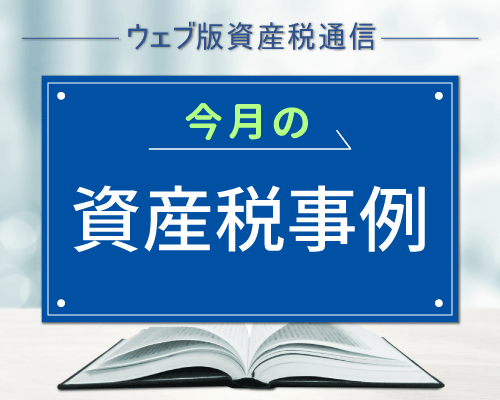
2025年10月29日
農地の納税猶予について
[質問]
【現状】
Aは、相続税の「農地の納税の猶予」を平成18年から受けています。
Aは高齢と病気により自身で耕作ができる状態でなくなり、現在は、生計を別にしている息子Bが中心となって、耕作を続けている状態です。
① この度、農業委員会から、A自身が耕作できない状態が続くと、次回(令和9年)の「引き続き農業経営を行っている証明」を出すのは難しいとの指摘がありました。
② また、農地としている一筆(猶予農地面積の20%以内)を農業資材置き場(建物や構築物はない)として利用しているため、固定資産税は、本年から雑種地として課税されています。
③ このような状況のため、AからBに対し、農地の納税の猶予を活用した「農地の贈与」を行うことを検討しています。
【疑問】
・①について、耕作放棄ではないため、ただちに打ち切り事由には当たりませんが、農業委員会の証明が出ない時点で打ち切りになってしまうと考えます。
・②について、農業資材置き場としての利用は、作業場敷地転用のため打ち切り事由の「転用」に当たらないと考えます。
・③について、②の筆は農地に当たらないため、農地の贈与税の猶予が受けられないと考えています。
農地の贈与税の猶予は、すべての農地を贈与することが条件になっていますが、②の筆は農地ではないため、贈与しなくてもよいでしょうか。
また、他の農地だけを贈与する場合、贈与の時点で耕作の放棄とみなされ②の筆は打ち切りとされ、②の筆の部分の相続税と利子税の納税が発生してしまうのでしょうか。
(措法70の4、措法70の6、措令40の7)
・このようにAが高齢で体調が悪い場合、贈与の方法ではなく、例えば営農困難の場合の農地の貸付で対応できるなど、何か検討できる方策があればご教授願います。
[回答]
1 相続税の納税猶予の適用を受ける農業相続人は、納税猶予に係る期限が確定するまでの間、相続税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、引き続き納税猶予の適用を受けたい旨の継続届出書を提出しなければなりませんが(措法70の6㉜)、この届出書には、農業相続人が農業を引き続き行っている旨の農業委員会の証明書を添付しなければなりません(措令40の763、措規23の8㉜一)。
2 納税猶予の対象となっている農地について20%以下の譲渡又は転用があった場合には、納税猶予税額のうちその譲渡又は転用があった農地に対応する部分についての納税猶予の期限が確定します(措法70の6①)。しかし、この転用については、耕作若しくは養畜の事業に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用は除かれていますから(措令40の7⑧)、ご意見のとおり、「農業資材置き場」とするための転用は、確定事由となる転用には該当しないことになります。
3 農地の贈与税の納税猶予の特例は、贈与者が、その農業の用に供している農地の全部を贈与した場合に適用されます(措法70の4①)。したがって、ご質問の「農業資材置き場」については、農地に該当しない限り、贈与者の営んでいた農業の用に供されていたものであっても、贈与税の納税猶予は受けられないことになります。
なお、農業相続人(A)が農地の全部をBに贈与する場合は、措置法70条の6第1項に規定する「当該特例農地等の一部につき当該贈与があった場合」に該当することになり、贈与された特例農地等の価額に対応する部分の相続税の額は免除され、贈与されなかった措置法施行令第40条の7第71項第2号に掲げる敷地又は用地(農業資材置き場)の価額に対応する部分の相続税の額(利子税の額を含みます。)は、その贈与があった日から2月を経過する日までに納付することになります(措通70の6-21(注))。
4 農業相続人が農地を貸し付ける方法で納税猶予を継続する制度としては、措置法70条の6第28項に規定する営農困難時貸付けの特例や、措置法70条の6の2第1項に規定する特定貸付けの特例がありますが、ご質問の場合、生計別の息子さんが中心となって耕作を続けているということですから、贈与税の納税猶予の特例を柱に検討することになるものと思われます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)




 @zeiken_info
@zeiken_info