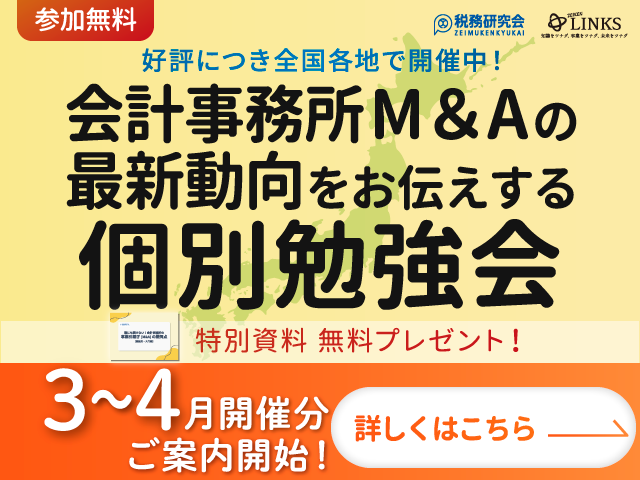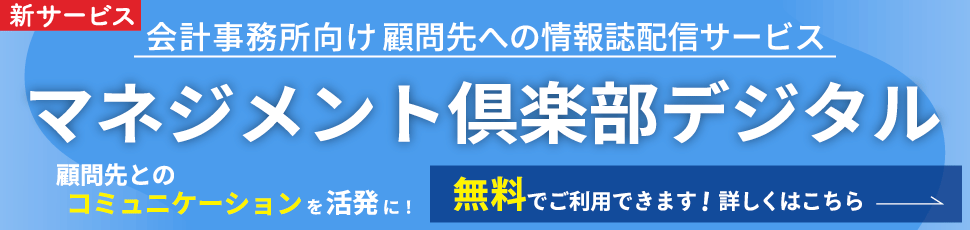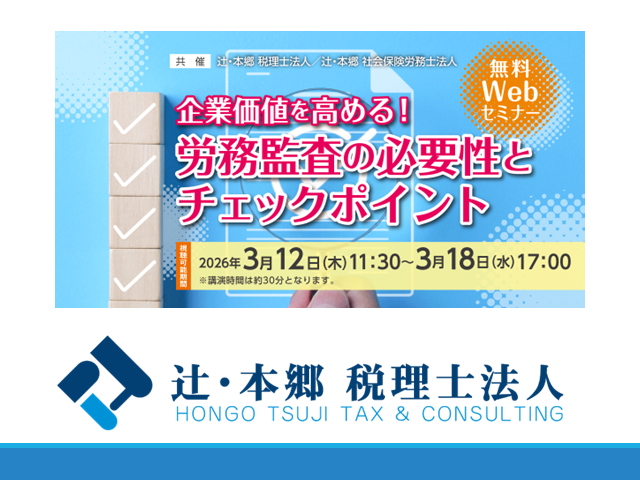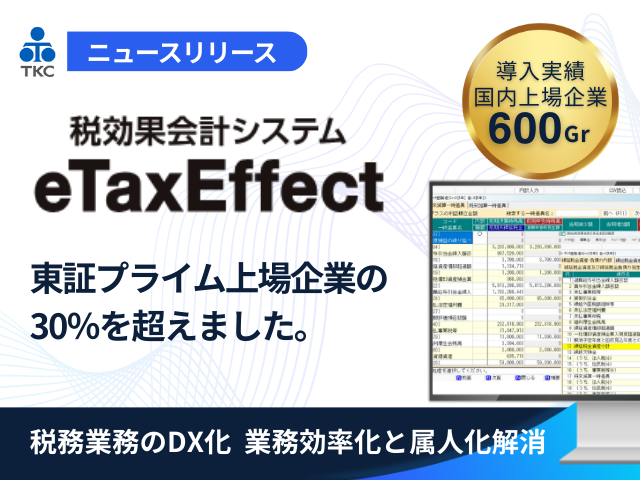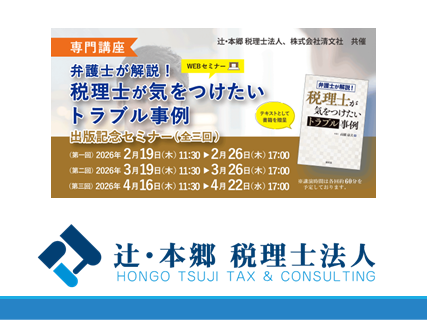リファンド方式への移行 ほか
【TAX TOPICS|マネジメント倶楽部デジタル7月号】
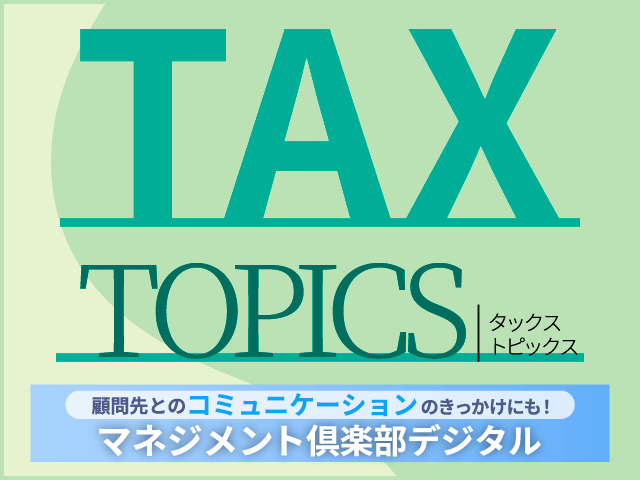
2025年7月11日
○●———————
このコラムでは、掲載月に関連する税の身近なトピックをピックアップして、簡潔にまとめてお届けしています。
毎月3〜4つのトピックを取り上げています。
※本記事は「マネジメント倶楽部デジタル」に掲載されたものです
———————●○
リファンド方式への移行
輸出物品販売場(いわゆる免税店)制度は、令和8年11月1日からリファンド方式に移行します。リファンド方式とは、免税対象物品を税込価格(課税価格)で販売し、その後、外国人旅行者等の出国時に当該物品を国外に持ち出すことが確認された場合に、消費税相当額を返金(リファンド)する仕組みをいいます。
今回の見直しにより、現行制度から主に次の点が変更されます。
- 輸出物品販売場では、免税対象物品を外国人旅行者等に対して税込価格(課税価格)で販売することになります。
- 免税購入対象者は、免税対象物品を国外に持ち出すことについて、購入日から90日以内の出国時に税関の確認を受けることになります。
- 免税店を経営する事業者は、販売情報(購入記録情報)及び税関における持ち出し確認情報(税関確認情報)を保存する義務が課されます。
- 輸出物品販売場を経営する事業者は、確認後、免税購入対象者に対して消費税相当額を返金(リファンド)することとなります。
匿名データの利用
国税庁は、保有する行政記録情報を匿名加工したデータを活用し、税・財政政策の改善に関する統計的研究を行う研究者を募集しています。この匿名データは個人の税務申告データに基づくもので、令和7年4月から利用申出の受付が始まっています。この取組みは、「オープンデータ基本指針」に基づき、有識者による検討を経て実施されたものです。
提供される匿名データは、平成26年分から平成30年分までの5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書(第一表・第三表)の情報で、申告件数全体から1%(1年分あたり約23万レコード)が抽出されています。個人を特定できる情報は削除され、CD-Rで貸与され、利用期間は原則2年間となっています。
利用できるのは、公的機関や大学等に所属する博士研究員や大学院生(博士課程後期相当)に限られます。利用目的は、税・財政施策の改善・充実に資する学術研究であることが求められ、研究成果は国税庁の審査を経て公表される予定です。
利用手続きは、仮の申出書を作成し、事前相談を経た上で正式に申出を行い、国税庁の審査によって承諾又は不承諾の通知を受ける流れとなっています。税務申告データを研究者に提供することで、税制の効果検証や将来に向けた政策提言が促進されることが期待されています。利用申出は、年中を通して受け付けています。
防衛特別法人税
令和7年度税制改正により創設された「防衛特別法人税」は、防衛力の抜本的強化に向けた安定的な財源を確保するために導入される付加税であり、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から適用される予定です。申告書様式は、令和7年4月14日付官報で公表されています。
納税義務者は、法人税の課税対象となるすべての法人(人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含みます)です。税額は、各事業年度の「基準法人税額」から基礎控除額500万円を控除した「課税標準法人税額」に4%を乗じて算定されます。基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除などを適用せずに計算した法人税額を指します。一方、防衛特別法人税については、外国税額や分配時調整外国税相当額等に対する控除が認められています。例えば、法人税額が1,500万円であれば、500万円の控除後の1,000万円に4%を乗じた40万円が防衛特別法人税として課税されます。法人税額が500万円以下の場合は、基礎控除の範囲内であるため課税されません。
この税は「当分の間」課税されるとされており、終了時期は明示されていません。東日本大震災後に導入された復興特別法人税のような時限措置はとられていないため、長期的な運用が想定されます。財務省の試算によると、令和8年度には約5,280億円、令和9年度には約8,210億円の税収が見込まれています。
電子交換所における手形・小切手の交換廃止
2027年度初から、電子交換所における手形・小切手の交換が廃止されます。これにより、電子交換所を介した手形・小切手による決済は終了しますので、郵送等による相対決済(個別取立等)を行うこととなります。手形・小切手自体の利用は禁止されませんが、金融機関の取扱方針次第では、利用に制約が生じる可能性があります。また、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の改正により、対象取引において手形払いは禁止されることとなりました。電子記録債権やファクタリング等、その他の支払手段についても、支払期日までに代金相当額を確実に得ることが困難なものは認められない方針です。この改正は、令和7年3月11日に閣議決定され、今後1年以内に施行期日が定められる予定です。
こうした流れを受け、支払実務や会計処理にも大きな影響が見込まれます。受取手形・支払手形に代わり、科目や債権管理方法の見直しが必要になります。また、貸倒引当金の設定や税務上の収益・費用認識の取扱いにも注意が必要です。企業においては、決済手段の選定・整備、社内規程の改定、システム対応等を早急に検討する必要があります。
![]()
※本コラムでは、さまざまな経営者にとって役立つ記事が集まるデジタル情報誌『マネジメント倶楽部デジタル』に掲載されている記事の一部を公開しています。
\会計事務所の皆さまへ/
マネジメント倶楽部デジタルで、
このような連載コラムを顧問先にお届けすることができます!
マネジメント倶楽部デジタルの‟ココがおすすめ!”
- 無料でお届けすることができます(有料プランもございます)。
- 顧問先への継続的なコミュニケーションツールとしてもぴったり!
- 中小企業の経営情報などが掲載されており、顧問先との話題作りとしても。
マジメント倶楽部デジタルの‟ココが安心!”
- マネジメント倶楽部デジタルの掲載記事は、税務研究会が監修しています。
- マネジメント倶楽部は紙版で刊行された1997年10月以来、多くの経営者様にご愛読いただいています。
- 顧問先の数やご予算などに応じて、最適なプランをお選びいただけます。
__今月末までのお申込みで、次月よりご利用スタート!
\まずは気軽に始められる「無料プラン」を是非お試しください!/




 @zeiken_info
@zeiken_info