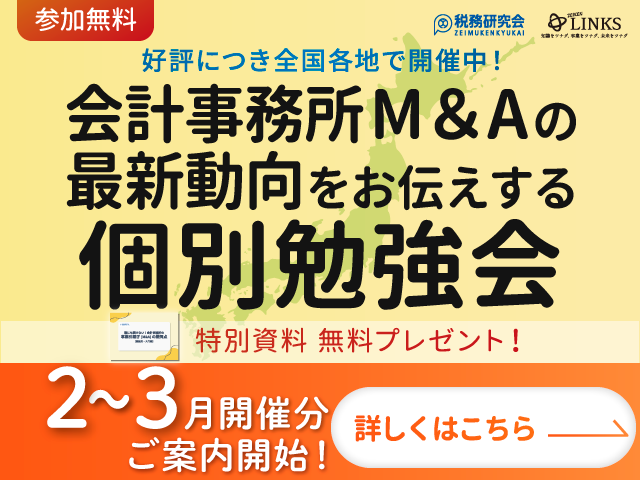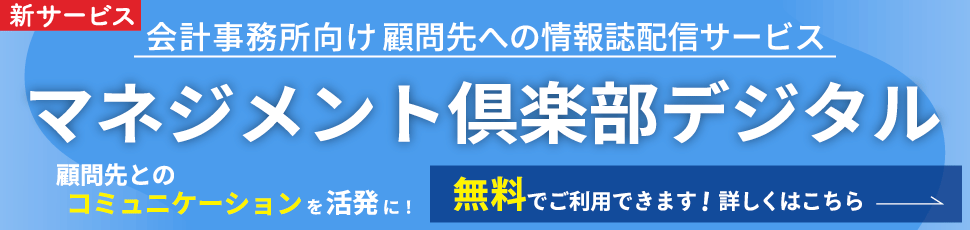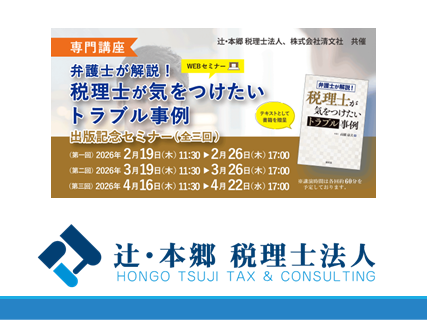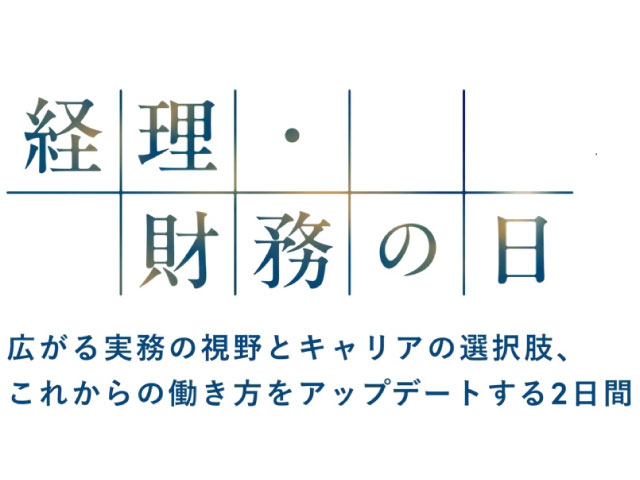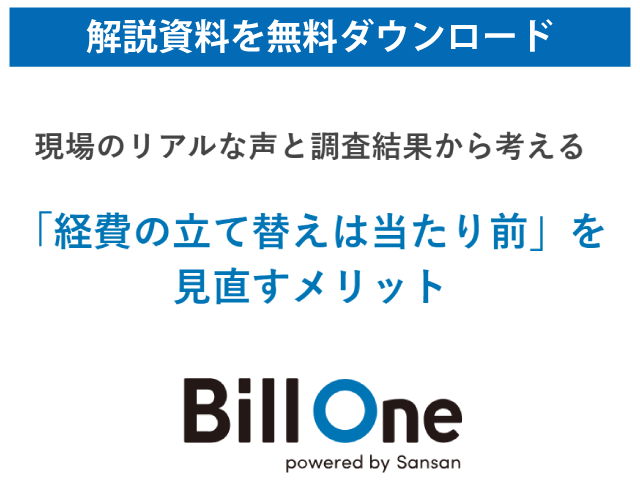退職金課税制度の改正と実務対応 ほか
【TAX TOPICS|マネジメント倶楽部デジタル11月号】
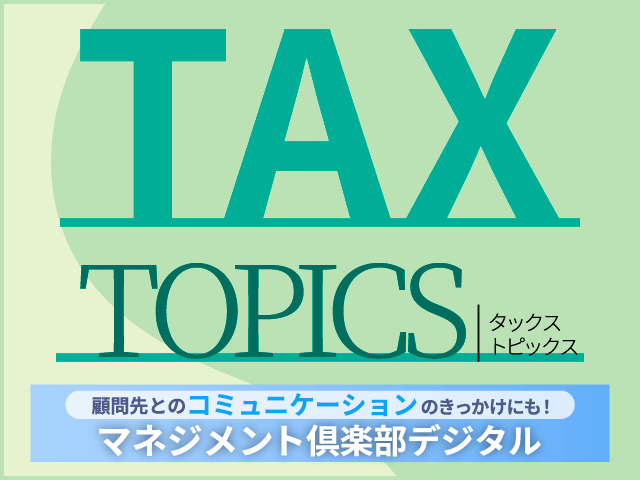
2025年11月10日
○●———————
このコラムでは、掲載月に関連する税の身近なトピックをピックアップして、簡潔にまとめてお届けしています。
毎月3〜4つのトピックを取り上げています。
※本記事は「マネジメント倶楽部デジタル」に掲載されたものです
———————●○
退職金課税制度の改正と実務対応
令和7年度税制改正により、退職手当等に関する税制が大きく変更されます。令和8年1月1日以降に支払を受ける退職金や同日以降に提出すべき書類から適用されます。今回の改正は、従業員と企業双方に実務上の影響が大きいため、早期の準備が欠かせません。
① 退職所得控除の重複排除ルールが拡大
現行では、同じ人が短期間に複数の退職金を受けた場合、控除額の重複を避けるため勤続期間を調整しています。改正後は、この対象が確定拠出年金の一時金(老齢一時金)を受給した場合にも広がり、前年以前9年以内に老齢一時金を受給している場合も調整が必要です。
② 申告書の保存期間が延長
老齢一時金に係る申告書の保存期間が、現行の7年から10年に延長されます。これは9年以内の受給履歴を確認できるようにするための措置で、文書管理の負担は増大しますが、税務当局からの照会に対応できる体制を整えておく必要があります。
③ 源泉徴収票の提出義務が全従業員に拡大
これまでは法人役員のみが提出対象でしたが、国税ではすべての居住者に係る退職所得の源泉徴収票、個人住民税ではすべての納税義務者に係る退職所得の特別徴収票の提出が義務付けられます。記載事項の見直しも予定されていますので、システム改修なども早めの対応が必要です。
事業承継税制のQ&Aが5年ぶり改訂 令和7年度改正を反映
国税庁は、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例措置(いわゆる事業承継税制)に関する質疑応答事例を、約5年ぶりに改訂しました。今回の改訂では、令和3年度から7年度までの税制改正を反映し、全14問の内容が見直されています。
更新された設問では、事業承継税制の「特例措置」と「一般措置」の違いや、手続きの流れ、贈与者・受贈者の要件、猶予税額の計算方法などが整理されています。例えば、申請の具体的な方法、複数の贈与者や会社にまたがるケースや贈与と相続の混在するケースなど、実務で迷いやすい事例が複数取り上げられています。
特に注目すべきは、令和7年度改正を反映した要件緩和です。法人版の特例措置において従来は「贈与の日まで引き続き3年以上役員であること」が必要でしたが、改正後は「贈与の直前に役員であればよい」とされました。これにより、令和6年末時点で役員に就任していない後継者であっても、贈与直前の就任で制度適用が可能となります。ただし、この緩和は特例措置に限られ、一般措置では従来どおりです。なお、特例措置の適用期限は法人版で令和9年12月31日、個人版で令和10年12月31日までとされています。
被扶養者認定収入要件の変更が年末調整に与える影響
令和7年10月から、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が一部見直され、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合、従来の「年間収入130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げられました。この改正は、令和7年度税制改正における特定扶養控除の見直しに伴うものであり、扶養控除等申告書の記載内容や年末調整の実務に影響を与えることが想定されます。そのため、実務担当者は健康保険制度と税務の双方を十分に理解しておく必要があります。
例えば、10月以降に被扶養者認定を行う場合には「150万円未満」で判定しますが、10月1日以降の届出であっても、9月30日以前の期間について認定する場合には、従来どおり「130万円未満」が適用されます。この二重基準は税法上の扶養要件とも異なるため、年末調整の段階で混乱を招きやすい点に注意が必要です。
さらに、健康保険の基準である「年間収入150万円(または130万円)」に対し、税法上の扶養は「合計所得金額」で判定されます。扶養控除等申告書に記載するのは「所得の見積額」であるため、収入と所得の違いを正しく理解した上で処理することが求められます。
実務上は、年末調整直前の改正であるため、扶養控除等申告書の確認や年末調整計算において誤りが生じないよう、マニュアルの整備や担当者研修の実施が望まれます。特に、アルバイト収入が140万円前後の大学生を扶養する世帯では、税制上は扶養控除の対象となる一方、社会保険の扶養認定では認められない可能性もあるため、両制度の違いを踏まえた慎重な対応が不可欠です。
税理士用電子証明書が第六世代へ移行 申告業務への影響に注意
令和7年8月から、第六世代税理士用電子証明書の申込が始まっています。現在利用中の第五世代証明書は令和8年3月末で失効するため、切り替えが遅れると、e-TaxやeLTAXによる申告・届出が行えなくなる恐れがあります。
第六世代では、電子証明書をクラウド上で管理し、税理士認証カードと組み合わせて利用する仕組みに変わります。これによりセキュリティは強化されますが、インターネット接続が必須となり、オフライン環境では利用できません。また、従来のICカードリーダーが対応していない場合があり、税理士側で機器更新が必要になる可能性もあります。
電子証明書の有効期間は令和12年7月末までの約5年間です。申込後は認証局の審査を経て発行され、その後はe-Tax等で証明書の差替手続きが必要となります。この間は一時的に申告や届出の提出ができない場合もあるため、企業としても決算期や申告期限を踏まえ、早めに税理士とスケジュールを調整しておくことが大切です。
![]()
※本コラムでは、さまざまな経営者にとって役立つ記事が集まるデジタル情報誌『マネジメント倶楽部デジタル』に掲載されている記事の一部を公開しています。
\会計事務所の皆さまへ/
マネジメント倶楽部デジタルで、
このような連載コラムを顧問先にお届けすることができます!
マネジメント倶楽部デジタルの‟ココがおすすめ!”
- 無料でお届けすることができます(有料プランもございます)。
- 顧問先への継続的なコミュニケーションツールとしてもぴったり!
- 中小企業の経営情報などが掲載されており、顧問先との話題作りとしても。
マジメント倶楽部デジタルの‟ココが安心!”
- マネジメント倶楽部デジタルの掲載記事は、税務研究会が監修しています。
- マネジメント倶楽部は紙版で刊行された1997年10月以来、多くの経営者様にご愛読いただいています。
- 顧問先の数やご予算などに応じて、最適なプランをお選びいただけます。
__今月末までのお申込みで、次月よりご利用スタート!
\まずは気軽に始められる「無料プラン」を是非お試しください!/




 @zeiken_info
@zeiken_info