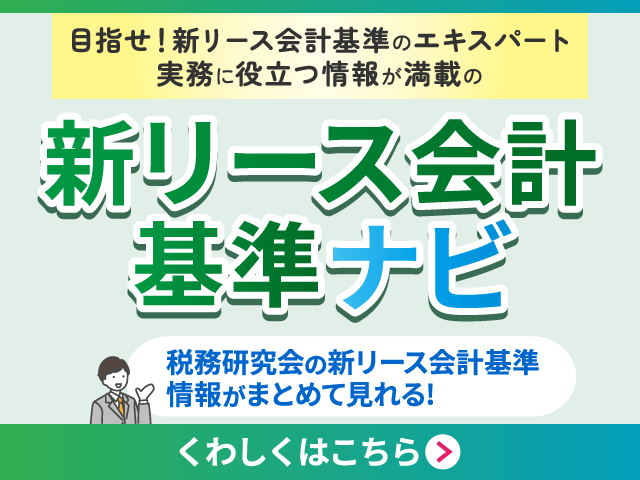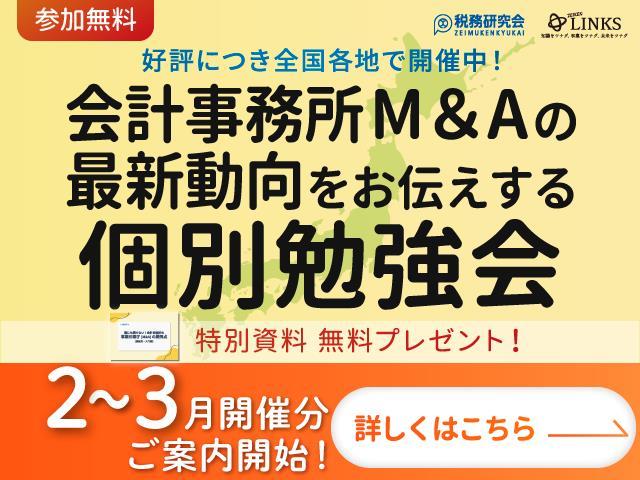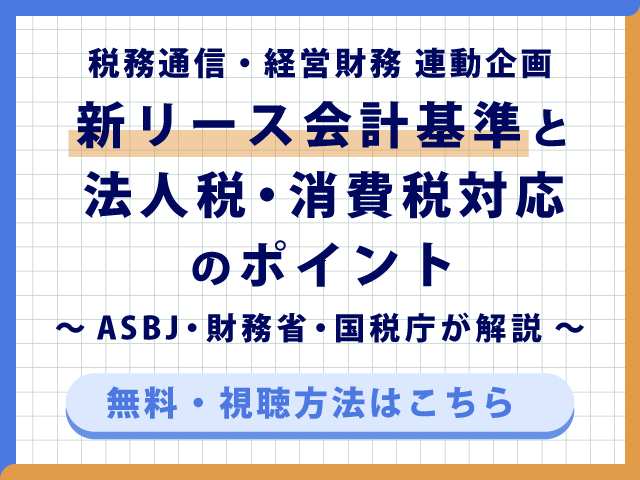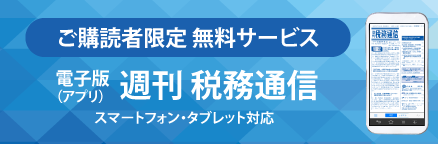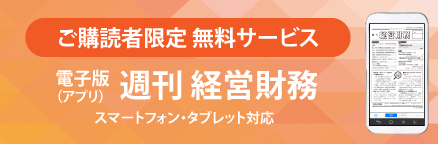派遣切り
2013/06/20 18:53
- ZEIKENPLUS
- 税研情報センター
 いわゆる派遣切りは、派遣労働者の雇用を不安定にするものとして問題視され、裁判上も様々な紛争が提起されています。今回はその代表的な例について紹介し、派遣切りに対する司法の判断を概観したいと思います。
いわゆる派遣切りは、派遣労働者の雇用を不安定にするものとして問題視され、裁判上も様々な紛争が提起されています。今回はその代表的な例について紹介し、派遣切りに対する司法の判断を概観したいと思います。
その前に、そもそも派遣に関する基本事項ですが、まず、派遣労働者の雇用形態には2種類があります。登録型と常用型です。
登録型は、派遣元と派遣先との間の派遣契約の契約期間に応じて、派遣労働者が随時、派遣元との間で有期の雇用契約を締結するというものです。一方、常用型は、派遣労働者と派遣元が無期の雇用契約を締結するというものです。そして、派遣切りは、このうち登録型において問題となります。
登録型の派遣労働者の有期雇用契約は、派遣元・先間の派遣契約の終了と帰趨を共にします。したがって、派遣先と派遣元との間の派遣契約が期間満了により終了すれば、派遣労働者の雇用契約も雇止めにより終了することになります。これがいわゆる派遣切りであり、派遣労働者の雇用を不安定にするのではないかとして問題視されました。
派遣切りに関する紛争としては、まず、派遣元・先間の派遣契約が期間満了により終了した場合につき、当然に派遣労働者に対する雇止めが有効になるわけではないとして、その雇止めの有効性が争われました。しかし、伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件(高松高判平18・5・18、後に最高裁で確定)は、常用代替防止等の観点からも、登録型の派遣労働者に関して雇用継続に対する合理的期待が生じることはないとして、雇止めは有効と判示しました。したがって、雇用継続を確約する等の特段の事情がない限り、原則として、派遣元・先間の派遣契約の終了に伴う雇止めは有効になるものと考えられます(その後も、トルコ航空ほか事件・東京地判平24・12・5等の裁判例において、登録型派遣労働者の雇用継続に対する期待は否定されています。)。
その他の争い方として、派遣切りにより雇止めされた労働者が、派遣先に対して、黙示の労働契約を締結していたと主張するものがあります。そのような紛争は多数提起されましたが、松下PDP事件の最高裁判決(最判平21・12・18)が、そのような黙示の労働契約の締結について、容易には認められないことを判示しました。その後、派遣労働者と派遣先との間の黙示の労働契約の締結を認めた裁判例はほとんどありません。
 このような流れの中、最近では、派遣切りについて派遣先の不法行為責任を追及するという紛争が提起されるようになりました。裁判例の中には、このような場合について派遣先の不法行為責任を認めた事案(パナソニックエコシステムズ事件・名古屋高判平24・2・10)もあります。しかし、派遣元・先間の派遣契約を期間満了により終了させることは、企業間の問題に過ぎず適法であり、それに伴う雇止めも、上記伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件の判旨に従えば、雇用継続に対する期待が存在しないため適法となるはずです。このように適法な行為しか存在しないにもかかわらず、不法行為責任が成立するということは、派遣先にとっては予測困難な事態といえます。今後も裁判所においてこのような判断が続くのか、注視していく必要があるでしょう。
このような流れの中、最近では、派遣切りについて派遣先の不法行為責任を追及するという紛争が提起されるようになりました。裁判例の中には、このような場合について派遣先の不法行為責任を認めた事案(パナソニックエコシステムズ事件・名古屋高判平24・2・10)もあります。しかし、派遣元・先間の派遣契約を期間満了により終了させることは、企業間の問題に過ぎず適法であり、それに伴う雇止めも、上記伊予銀行・いよぎんスタッフサービス事件の判旨に従えば、雇用継続に対する期待が存在しないため適法となるはずです。このように適法な行為しか存在しないにもかかわらず、不法行為責任が成立するということは、派遣先にとっては予測困難な事態といえます。今後も裁判所においてこのような判断が続くのか、注視していく必要があるでしょう。