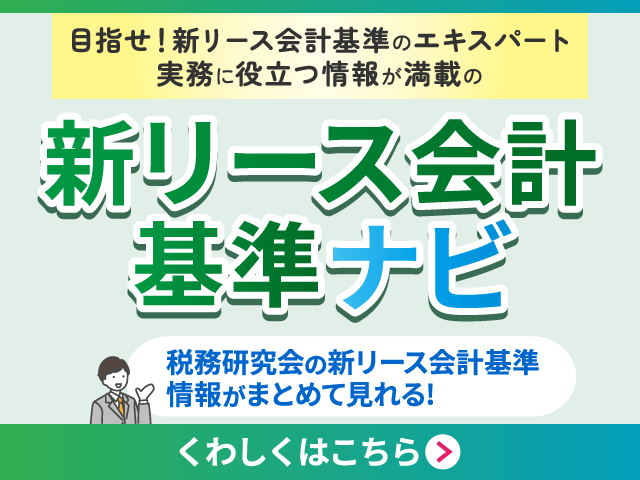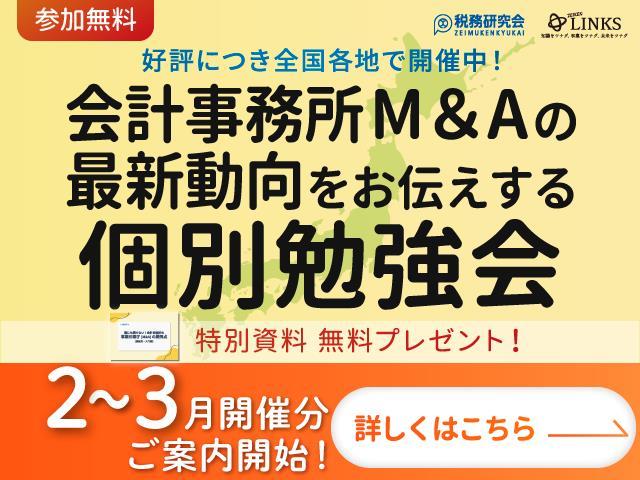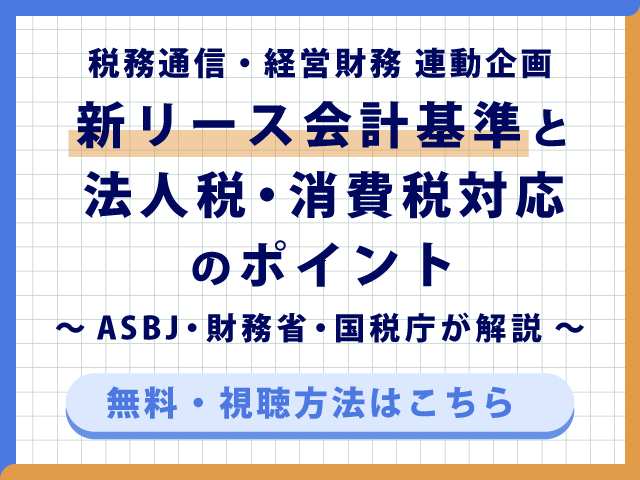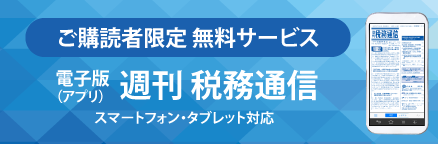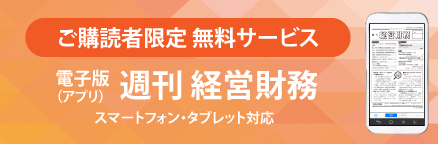更新上限ルール
2018/08/20 16:25
- ZEIKENPLUS
- 税研情報センター

今年4月から無期転換権が本格的に発生することが予想されていますが、企業の中には更新上限で対応する例が見られます。
更新上限については、すでに継続雇用している者に対して、更新時に新たに更新上限条項を付け加えることが可能かという問題があり、この問題についてはリーマンショックに伴う雇止め時にいくつか裁判で争われました。リーマンショックのような特異な事情がない現在において、無期転換対策に更新上限を設けることが可能かということはまた別途裁判で争われる可能性があるでしょう。
一方、新たに雇い入れる者に対しては、更新上限を設けることは基本的に問題ないと考えられます。しかし、更新上限が形骸化していないか(更新上限で雇止めした者を、新たに雇い入れたりしていないか等)といった運用面や、そもそも恒常的に存在する業務について更新上限を設けることは問題となり得ます。
今回紹介する高知県公立大学法人事件は、3年の更新上限に基づく雇止めの効力が争われた事例ですが、恒常的な業務であり、かつ、雇止め後に公募から再雇用されるケースもあったという事実関係のもと、はたして更新上限に基づき雇止めをすることが許されるかということが問題になりました。
判決は、一部を除き更新上限を超えて更新された例はないこと、雇止め後の公募は更新とは明らかに異なる手続きであること、恒常的で一定の専門性が必要な業務であったとしても、同一の担当者が継続的に従事する必要性が高い業務とはいえず、代替性が高いと評価できること、雇用期間の定めのない準職員への登用機会も設けられていること等からすれば、3年の更新上限が定められている以上、これを超えた雇用期間については更新期待が生じていなかったと認定しました。
このように、恒常的に存在する業務であったとしても、ルールを厳格に運用することで更新上限を設けることが可能であることが示されたことには重要な意義があるものと考えます。
人材不足の昨今、企業としては、優秀な契約社員の雇用を確保するために正社員登用制度を設ける一方で、それ以外の契約社員は更新上限で一律に雇止めにしていくといった人材管理を図ることが有用でしょう。