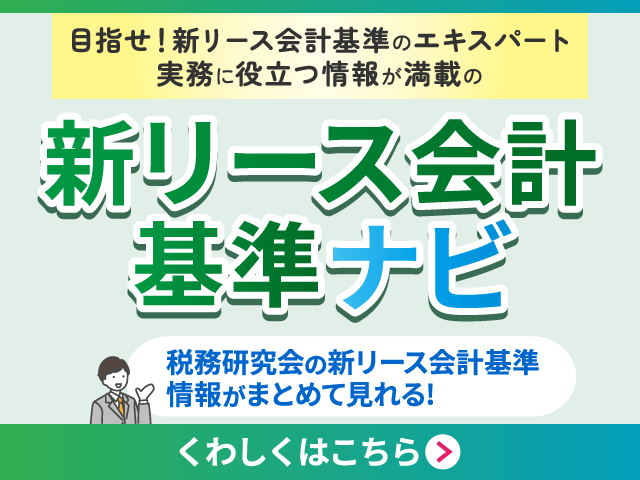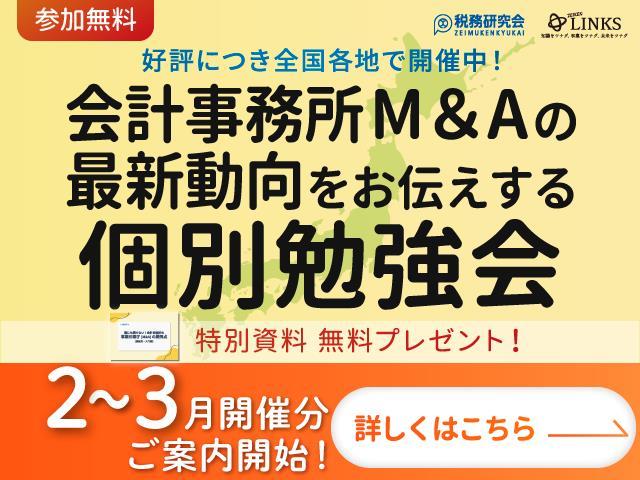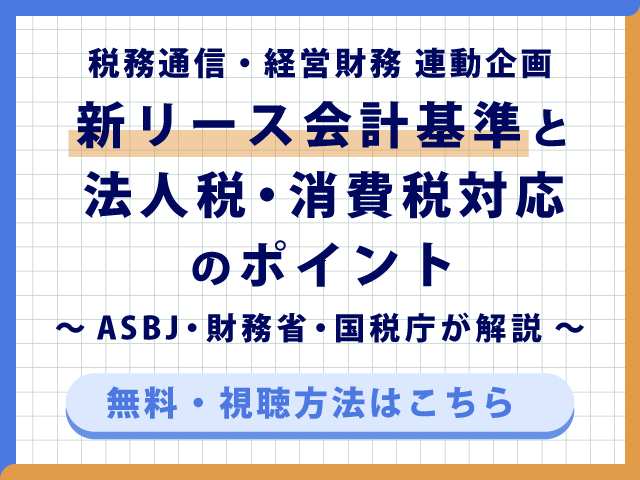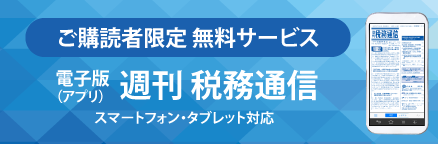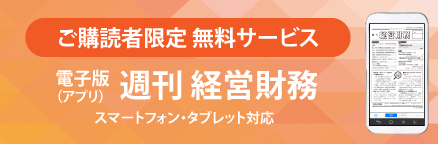同一労働同一賃金に関する最高裁判決(Vol.2)~賞与及び退職金について~
2020/11/24 15:00
- 同一労働同一賃金
- 賞与
- 退職金
先月は諸手当や諸休暇等について解説しましたが、今回は賞与及び退職金について解説します。
諸手当や諸休暇は、特定の事象に対して支給ないし付与されるという対価関係が比較的明確でした。一方で、賞与や退職金は、特定の事象に対する対価というより、有為な人材の確保・定着といった大所高所の見地に基づく人事施策としての意味合いが強まります。
したがって、いずれの最高裁判決においても賞与及び退職金の支給の有無に関する差は不合理とは認められないと判断されています。
以下、それぞれ検討します。
賞与について
これまで賞与については、そもそも有期雇用社員に対して支給されていない場合と、支給されているが金額や計算式に差がある場合の2つのパターンがあり、このうち、高裁段階で差が不合理と認定されていたのは、全く支給されていないというパターンについてでした。
しかし、最高裁は、有期のアルバイト社員に対して賞与が支給されておらず、年収の比較においても、新規採用された正社員の基本給及び賞与の合計額平均の55%の水準であったという事実関係を前提にした上で、アルバイト社員に対して賞与が支給されないことは不合理とは認められないと判断しました。
同事案では、賞与が概ね通年で4.6か月分支給されており支給水準も定まっていたことから、高裁は、賞与には算定期間における労務の対価の後払いとしての性質も一定程度含まれており、アルバイト社員に対して一切支給しないというのは不合理な差であると判断しましたが、最高裁はこれを否定しました。
もちろん、判断の前提として、正社員とアルバイト社員では職務内容やその変更の範囲が異なるという事実関係が認定されています。
高裁判決の時点では世間的にも、有期雇用社員に対して賞与を全く支給しないことについては違法とされるリスクが高いのではないかという論調もあり、対応を検討している会社もありましたが、最高裁判決はこれについて必ずしも違法ではない(不合理とは認められない)ということを明らかにしましたので、人事労務分野においては非常に意義のある判決といえるでしょう。
退職金について
高裁判決では、契約社員Bという雇用形態の者(原告ら)に対して退職金が一切支給されないことは不合理な差であり、少なくとも正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1を支給すべきであるとされていました。
その理由は、契約社員Bも定年が65歳と定められ、実際に定年まで10年前後の期間勤務していたこと及び契約社員Bと同じ業務に従事している契約社員Aは平成28年から無期雇用の扱いとなり退職金制度が導入されたことという2点のみでした。
定年の定めがあり10年前後勤務しているから、という理由は、退職金請求という重大な結論を導く理由としてはやや薄弱な感が否めませんから、どちらかといえば主たる理由は後半部分であり、契約社員Aには退職金制度が創設されたからという点が重視されたものと考えられます。
しかし、最高裁では、そもそも契約社員Aに退職金制度が導入されたのは原告らが退職した後の事情であるため、本件には関係がないものとしました。
さらに、契約社員Aと契約社員Bは職務内容及び変更の範囲も一定程度異なり、契約社員Bから契約社員Aに職種を変更することができる登用制度も存在することから、同AとBとの間に退職金制度の有無について差異があったとしても不合理な差とは認められない旨も付言しています。
したがって、職務内容やその変更の範囲が異なり、かつ、登用制度も存在する場合には退職金制度の有無について差があったとしても不合理な差とは認められない、という最高裁の判断が明示されたものと考えられます。また、当該事案では登用制度が存在していましたが、仮にこれがなかったとしても、それのみで退職金制度の有無に関する差が不合理と判断されるものではないものと考えます。
結語
最高裁判決を前提にすれば、無期と有期との間で職務内容及びその変更の範囲が異なり、かつ、登用制度も存在するような場合には、賞与及び退職金の支給の有無に関する差は不合理とは認められないものと考えられます。
登用制度が存在しない場合にはどうかという問題もありますが、それのみではただちに上記差異が不合理と認められるものではないものと思われますが、制度設計を考える上では万全の内容を整えるためにも、登用制度の存在について十分に留意する必要があるでしょう。