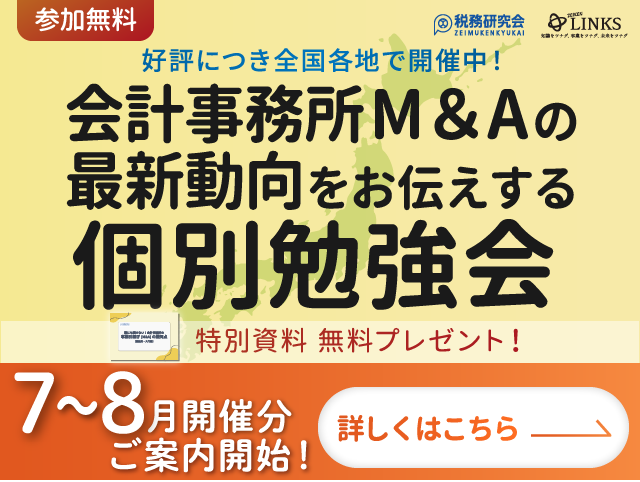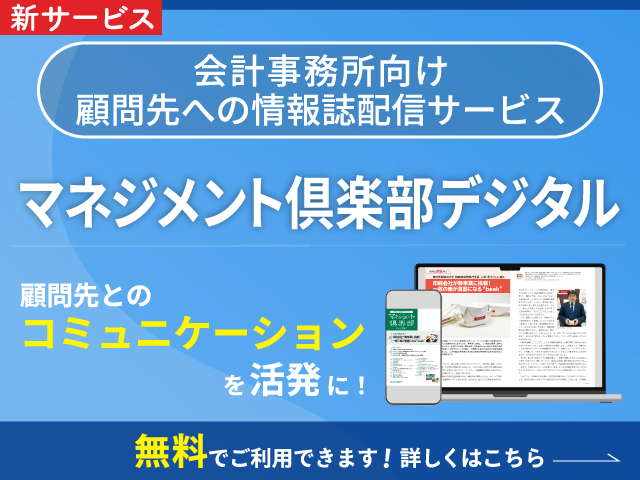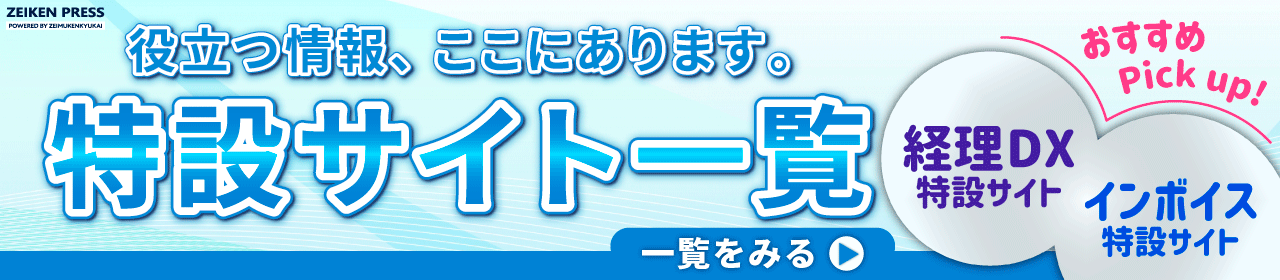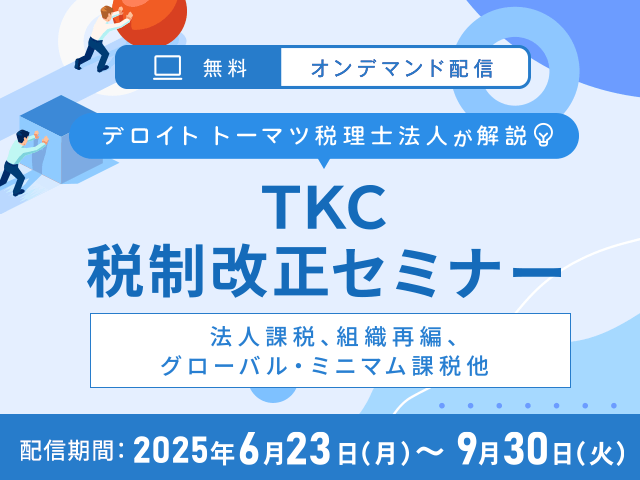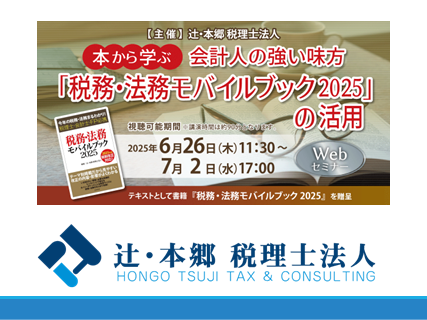暗号資産 技術的措置の意味|税務通信 READER’S CLUB
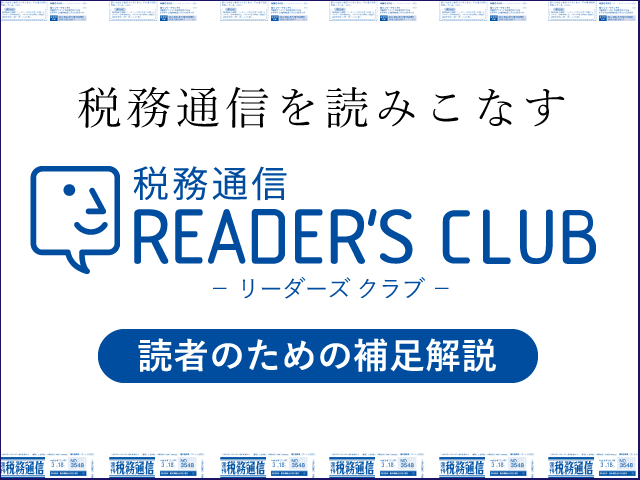
2024年3月11日
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
関連記事:No.3785(令和6年1月15日号) 58頁
記事では、期末時価評価の対象外となる暗号資産とは、「他の者に移転できないようにする技術的措置を講じたもの」とありますが、具体的にどのような措置が必要なのでしょうか?
「他の者に移転できないようにする技術的措置を講じたもの」とは、次の要件すべてに該当するものです(法規26条の10)。
|
また、ここでの「技術的措置」については、法人税基本通達2-3-67の2において、具体例が掲げられています。
|
暗号資産は、ソースコードがプログラムされることにより形成されています。そのソースコードに、暗号資産の移転に制限をかけるコード(ロックアップコード)を組み込み、一定の条件が成立するとその制限が解除されるようにプログラムします。結果、その条件が達成されるまでは、暗号資産が移転できない状況を作り出すことが可能になります。誰も、その暗号資産の移転に制限をかける、というコードの実行を止めることができないので、②の「会社関係者による解除不能」という要件を達成できます。
また、その解除される一定の条件を「一定期間の経過」とすることにより、①の「移転することができない期間が定められている」も満たすことになります。上記通達の(1)は、このようなケースを明示しています。
ただし、暗号資産のプログラムを組むに当たり、特権IDと呼ばれる管理者用アカウントを設定することも可能です。この特権IDは、通常はシステムに対する全ての操作権限を持つアカウントのため、設定されたロックアップコードすら書き換えることが可能です。そのため、このような重要な権限を持つ特権IDの設定がされている場合は、技術的措置が取られていない、ことになっています。
次に、通常、暗号資産の移転には秘密鍵と呼ばれる暗号化されたパスワードが必要となりますが、この秘密鍵を複数作成し、そのうちのいくつかの秘密鍵がなければ暗号資産を移転させることができないという設定も可能です(いわゆるマルチシグ(Multi Signature)方式)。
例えば、4個の秘密鍵を作成し、そのうちの3個の秘密鍵がなければその暗号資産を移転させることができない設定とします。この場合に、その4個の秘密鍵のうち2個以上を法人の関係者以外の第三者に渡せば、法人は、自己及びその関係者の意思だけで、自由にその暗号資産を移転することができなくなる状況を作り出せます。これが上記通達の(2)で、これで、②の「会社関係者による解除不能」という要件を達成できます。
また、譲渡制限期間を定めれば、①の「移転することができない期間が定められている」も満たすことになります。




 @zeiken_info
@zeiken_info