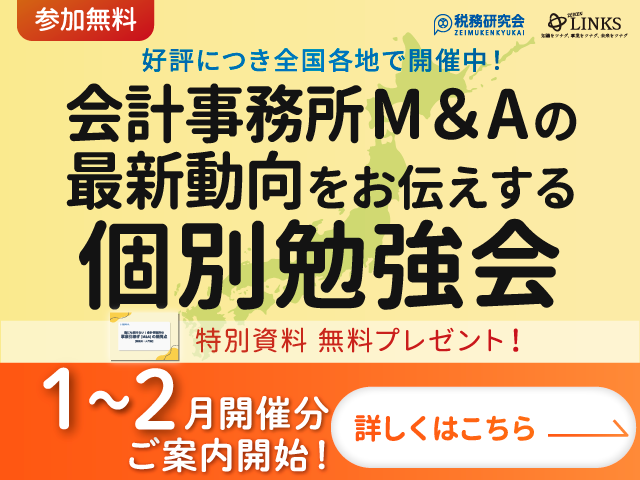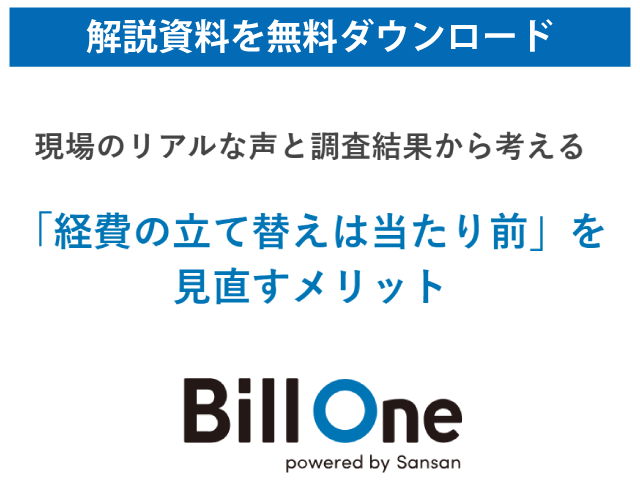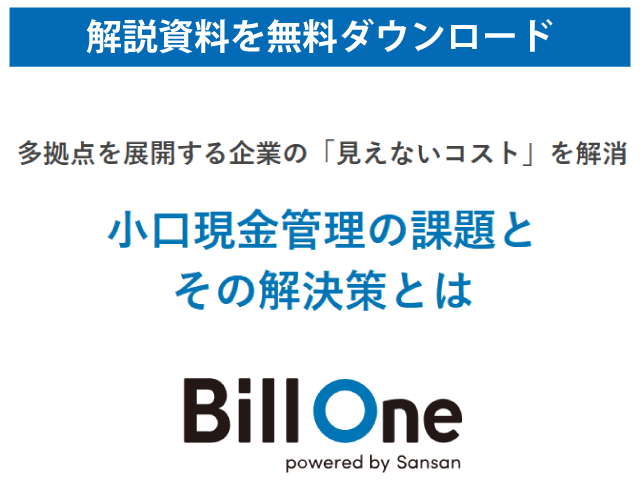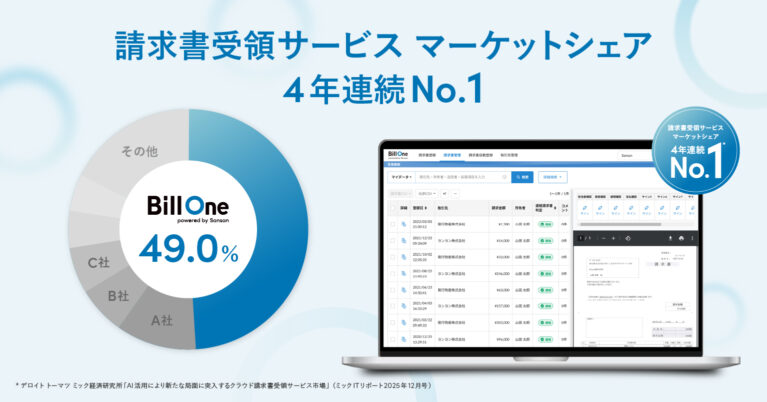特定居住用宅地等(家なき子)の特例の適用有無
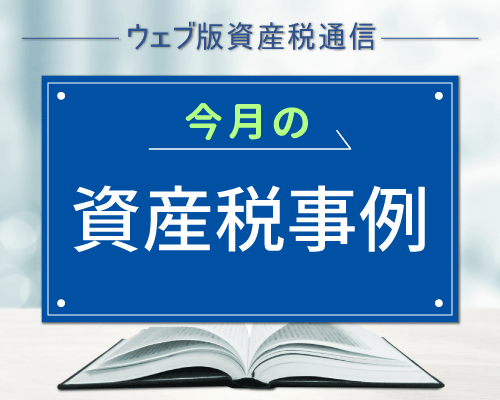
2025年8月27日
特定居住用宅地等(家なき子)の特例の適用有無
[質問]
【現況】
被相続人A
相続人は子B、子C、養子D(子Bの子)※配偶者は以前死亡
被相続人A は自身が所有する土地に一人で居住しています。
子B及びその家族は同族会社が所有する家屋に居住しています。
養子Dは高校卒業まで子Bと同じ家屋に居住していましたが、アメリカの大学進学に伴い、入学から現在4年生までの約4年間を賃貸物件(親族外所有)に住み続けています。ただ養子Dの住民票は子Bと同じままになっています。
【質問】
被相続人の居住の用に供している宅地を養子Dが遺言で相続します。被相続人に配偶者は無く、同居している相続人もいません。
養子Dは相続開始前3年以上前から賃貸物件に居住していますので特定居住用宅地の80%評価減は可能でしょうか。
養子Dの住民票が子Bと同じままであること、養子Dは子Bの扶養となっており家賃も子Bが負担していること、学校が休暇の時に子Bの家に一時的に帰るなどの要素は適用判定に影響するのでしょうか
[回答]
措置法69条の4第3項2号ロに規定する被相続人の親族(家なき子)に該当するための要件の一つとして、相続開始前3年以内に国内にある自己の三親等内の親族が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。以下「親族所有家屋」といいます。)に居住したことがないことが挙げられています。
ここにいう親族所有家屋に居住したことがないこととは、家なき子が相続開始前3年以内にその親族所有家屋を生活の拠点として使用していなかったことを意味しますから、その親族所有家屋以外に生活の拠点となる家屋があれば、その親族所有家屋は生活の拠点には当たらないことになります。したがって、照会の場合であれば、Dにとって米国に所在する賃貸建物(本件建物)が生活の拠点であれば、Bが所有する家屋は、その生活の拠点には当たらないことになります。
そして、生活の拠点かどうかは、Dの本件建物への入居目的、日常生活の状況、本件建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となる他の建物の有無その他の事実を総合勘案して、社会通念に照らして客観的に判断するのが相当と考えます(平成18年6月6日公表裁決参照)。
そうすると、相続開始時点においてDは、大学留学ため米国に所在する本件建物に3年以上前から起居しているわけですから、その生活の拠点は、たとえDがBの扶養親族であったとしても物理的にいって本件建物にあるとみるのが相当と考えます。
なお、相続開始時において現に居住していない相続人を被相続人の同居親族とみなして小規模宅地等の特例を適用することができる旨の国税庁の質疑(「単身赴任の相続人が取得した被相続人の居住用宅地等についての小規模宅地等の特例」)がありますが、これは、あくまでも被相続人の同居親族に当たらない相続人が、転勤という特殊事情が解消したときは、その相続人の配偶者等と起居を共にすると認められる家屋に限ったものであって、上記の結論に影響を与えるものではないと考えます。
(税理士懇話会・資産税研究会事例より)




 @zeiken_info
@zeiken_info