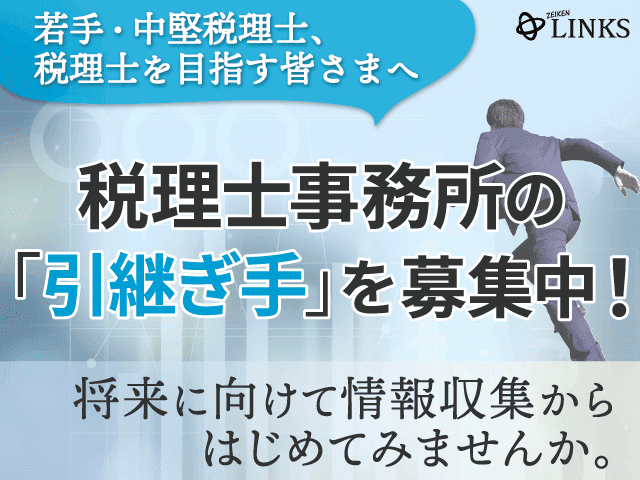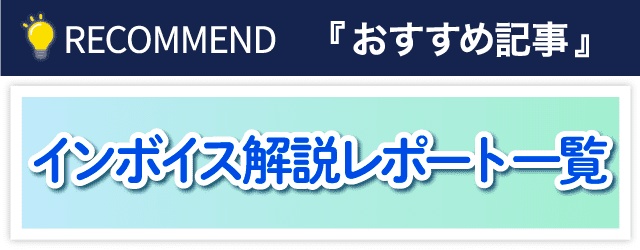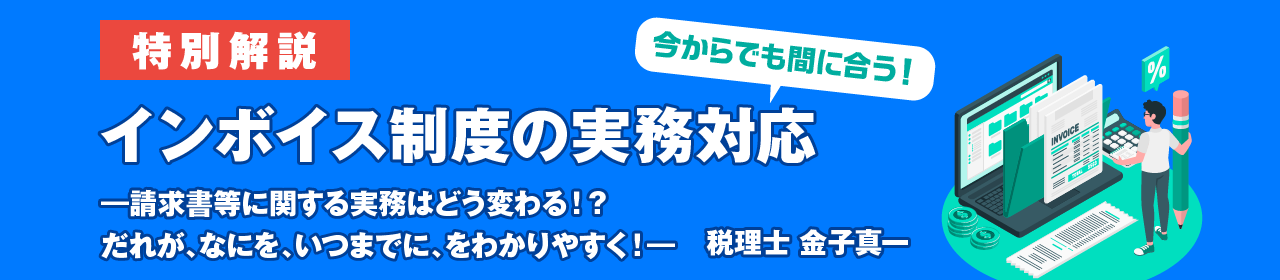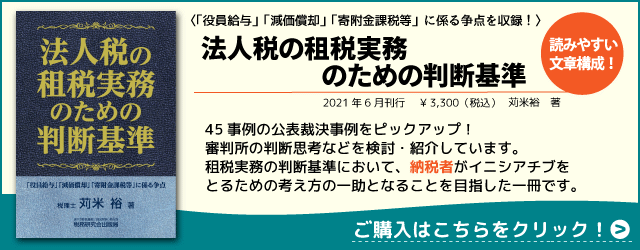『役員報酬:定期同額給与の範囲』
~役員給与に関する判断基準~
【法人税の租税実務のための判断基準】

2022年12月28日
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
審査請求事案は、身近な実務とは無関係であると思っている方が多いようです。そのお考えは、誤解されていると思います。審査請求事案は、当然と思っている税務判断について、ちょっぴり事実関係が異なっているということのみで、納税者と租税行政庁との間に行き違いが生じているものです。このコラムは、実務経験の豊富な税理士が、国税審判官の業務を経験したことを実務家にフィードバックするため、実務に直結する審査請求事案に係る論点や判断基準の整理をして、租税行政庁との見解の相違を回避するための検討を行っています。
そして、審査請求事案は、身近なテーマである法人税の「役員給与」「減価償却」「寄附金等」の3つを選定し、≪裁決事例の考察≫として「1 事案の概要」「2 主要事実と法令解釈等への適合」「3 事実認定による考察」に区分して、規則性を持った構成として事例を紹介しています。
このコラムにより興味を持たれた方は、書籍「法人税の租税実務の判断基準」にて事例を紹介していますのでご覧ください。
第一回では、「役員報酬」のうち経済的利益の供与の認定事例から、主に「定期同額給与の範囲」について、審判所の判断過程の考察をご紹介します。
| 〔 事例 〕
請求人名義の車両を代表者に対し贈与等をした事実はなく給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとは認められないとした事例(公表裁決事例:平成24年11月1日裁決) |
1 事案の概要
本件は、飲食店業を営む同族会社である請求人が、本件車両を平成20年6月期の貸借対照表の資産の部にそれぞれ計上するとともに、平成20年6月期から平成21年6月期までの各事業年度において本件車両関連費用並びに減価償却費の額をそれぞれ損金の額に算入し、法人税等の申告をしたところ、原処分庁が、本件車両はG代表取締役の妻が個人使用のために取得したものであり、本件車両取得費等は請求人からG代表取締役に対し支払われた法人税法第34条第3項に規定する事実の仮装、隠ぺいにより支給した役員給与の額であるとして、法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、本件車両は請求人名義であるので、請求人が取得したというべきであり、本件車両については役員給与ではなく、請求人の資産として処理されるべきであるとして、原処分の一部の取消しを求めた事案である。
2 主要事実と法令解釈等への適合(一部取消し)
⑴ 法令解釈
審判所は、旧法人税法第34条第3項について、「事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより役員に支給する給与の額は、損金の額に算入しない旨規定しているところ、ここにいう「事実を隠ぺいし」とは、特定の事実を隠匿しあるいは脱漏することをいい、「仮装して」とは、特定の所得、財産あるいは取引上の名義を装う等事実をわい曲することをいうものと解される。」旨、また、旧法人税法第34条第4項について、「同条第1項から第3項までに規定する給与には債務の免除による利益その他の経済的利益が含まれる旨規定しているところ、同条第4項に規定する「債務の免除による利益その他の経済的な利益」とは、役員に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額や、役員等のために個人的費用を負担した場合における費用の額に相当する金額等の法人が一定の行為をしたことにより実質的にその役員等に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもらたすものをいうと解される。」旨の法令解釈を大前提としている(アンダーライン等筆者加筆)。
⑵ 本件車両取得費について
審判所は、本件車両取得費について、請求人が、①本件車両の購入に関する注文の当事者であり、②本件信販会社を通じて本件車両の売買代金を支払い、③自動車検査証に使用者として記載されているため、本件車両の取得者は請求人であると認定しており、本件車両の納車場所や保管場所がG代表の妻の居宅であったこと、及び本件ディーラーからの連絡先がG代表取締役の妻であったことなどからすると、本件車両をG代表取締役の妻が個人的に利用していることが認められるが、上記⑴後段第4項の法令解釈によれば、請求人からG代表取締役に対して本件車両の贈与があった等、請求人が一定の行為をしたことにより実質的にG代表取締役に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらしたとまでは認めることができないとして、本件車両取得費が役員給与に当たるとはいえない旨判断をしている。
⑶ 本件車両関連費用等について
審判所は、本件車両をG代表取締役の妻が専属的に利用していたことについて、G代表取締役が実質的経営者としての権限を利用して請求人が所有する本件車両をG代表の妻に使用させていたと認めるのが相当であるところ、G代表取締役は、請求人に対し、本件車両関連費用に相当する金員の支払をしていないのであるから、本件車両は、請求人からG代表取締役に対して無償で貸与されていたと認められ、上記⑴後段第4項の法令解釈に適合するとして本件車両の利用により享受する経済的利益等が役員給与に当たる旨判断をしている。
なお、審判所は、本件車両関連費用について、請求人が、それぞれ租税公課、保険料又は支払利息等の勘定科目をもってその帳簿に記載されており、事実を隠ぺい又は仮装していたと認めるに足る証拠はないとして、原処分庁の主張を排斥している。
3 事実認定等による考察
⑴ 本件車両取得費について
本件車両は、「役員に対して物品その他の資産を贈与した場合」の適合について、請求人が、①本件車両を注文していること、②本件車両の売買代金を支払っていること、③自動車検査証に使用者として記載されていることの各事実により、審判所がG代表取締役に対する贈与がなかったことの判断要素としている。
この判断要素からすると、本件車両がG代表取締役に対する贈与と認定するケースとしては、本件車両をG代表取締役の妻が専属的に利用していることを前提として、G代表取締役の個人名義で購入した車両を実質的な所有者は法人であるとして帳簿書類等に記録する、及びG代表取締役から車両の購入資金を借り入れる等の各事実があれば、「法人が一定の行為をしたこと」と認められ、「実質的にその役員等に対して給与を支給したのと同様の経済的効果をもたらすもの」として、法人税法第34条第3項に規定する役員給与の損金不算入及び重加算税が課される主要事実になると考えておくべきであろう。
⑵ 本件車両関連費用等について
本件車両は、G代表取締役の妻が専属的に利用していたこと、また、G代表取締役が請求人に対して本件車両関連費用に相当する金員の支払をしていないことから、請求人からG代表取締役に対して無償で貸与されていたと認められたものであり、役員給与の認定のため本件車両の利用により享受する経済的利益等を評価する必要がある。
これにより、まず審判所は、所得税法施行令第84条の2※1 が法人の資産を専属的に利用することによる経済的利益の額を「通常支払うべき使用料」等と規定しているところ、本件車両を専属的に利用する場合の資産利用対価額を客観的に算定することは困難であることから、「当該資産の取得時の価値を基礎に算出するのが合理的であり、本件車両の取得価額を基礎として、その使用可能期間に占める貸与期間に相当する額を算出した上、それを当該貸与期間の月数で均等にあん分して算出される金額及び1か月当たりの本件車両関連費用の合計額を1か月当たりの資産利用対価額とするのが相当である。」旨判断している。この場合において、本件車両の使用可能期間は、「資産の使用又は時の経過による当該資産の価値の減少分を算定する減価償却費の計算における法定耐用年数を採用するのが相当である。」とし、本件車両に貸与期間の定めがないことから、「法定耐用年数と同一とするのが合理的である。」としている。具体的な「通常支払うべき使用料」の算定は、「本件車両の取得価額を基礎として、減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第一に定められている年数である6年の期間により、均等にあん分計算するのが相当である。」としている。つまり、本件車両は、仮に償却方法が定率法を採用している場合には当初減価償却費の額の方が多く算定されることになり、他方、法人税法施行令第69条《定期同額給与の範囲等》第1項第2号の規定により定期同額給与に該当するため損金の額に算入され、源泉徴収義務の課税問題のみで帰結することになろう。しかし、本件車両がG代表取締役の妻が専属的に利用しているものではなく、法人の事業と兼用している場合には、「通常支払うべき使用料」の算定が各々の使用実態に即した使用割合等による合理的なあん分が求められ、かつ、継続的に供与される経済的な利益であると認められず定期同額給与に該当しない旨認定されることも考えられよう。そのため、同様の取引を行う必要がある場合には、法人と役員等の間において、車両の賃貸借契約を締結しておくことになろう。
次に、審判所は、「本件車両関連費用のうち、自動車保険料の額及び本件ローン契約に基づく支払利息の額は、いずれも一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出されるものであり、請求人がこれらの費用を負担したことによりG代表が受ける経済的利益等も継続的に供与を受ける利益であるといえる。」旨判断している。そうすると、自動車保険料の額及び本件ローン契約に基づく支払利息の額は、資産利用対価額と同様に、定期同額給与に該当するため損金の額に算入され、源泉徴収義務の課税問題のみとなる。他方、「本件車両関連費用のうち、自動車税、自動車取得税、自動車重量税及び本件ディーラーに対する手数料等の額は、継続的に役務の提供を受けるための支出金ではない」から、定期同額給与に該当せずG代表取締役に対する役員給与の認定により損金不算入となる。上述のとおり、同様の取引を行う必要がある場合には、車両の賃貸借契約を締結して、本件車両関連費用の負担義務の精算方法も定めておく必要があろう。
本考察は、法人の実質的な損失を極力回避する余地を見出していると感じられるであろうが、専属的に利用する資産の種類及び金額等によって、更正処分の根拠法令が法人税法第132条《同族会社等の行為又は計算の否認》になることも想定されることから、取引形態として積極的に推進するものではない。
※ 1 所得税法施行令第84条の2《法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額》は、「法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。」旨規定している。
このコラムの次回更新を知りたかったら…@zeiken_infoをフォロー
税理士苅米 裕(かりごめ ゆたか)
税理士事務所勤務後、関東信越国税不服審判所(国税審判官)等を経て、現在苅米裕税理士事務所所長及び企業の社外監査役。
税理士会において、東京税理士会芝支部副支部長、東京税理士会理事等を経て、現在、東京税理士会会員相談室相談委員、東京税理士会支部会員研修講師、東京税理士会調査研究部委員、東京税理士会芝支部相談役。




 @zeiken_info
@zeiken_info