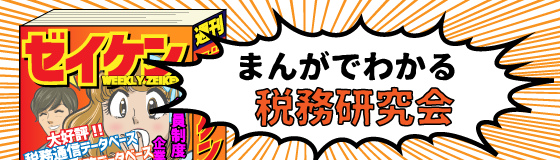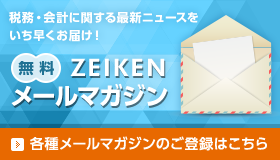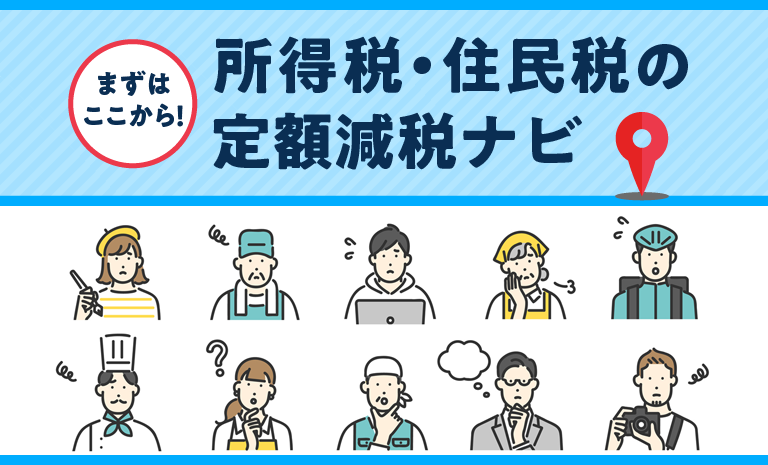

12.調整給付
調整給付について、税務通信の記事で次のように記載されています。
・個人住民税が課される市町村から支給対象者に案内がある
・納税者は当該市町村が定める期限までに給付申請が必要
・市町村は、一旦令和5年分の課税状況を元に給付する(当初給付)
・令和6年分の所得状況で当初給付に不足が生じた場合は差額を給付する(不足額給付)
・市町村は所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせ、1万円単位で切り上げて給付する
・当初給付が過大だった場合、返還は求めない
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」内閣官房ウェブサイト
各種給付の詳細
自治体によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。通常の場合、自治体の準備が出来次第、給付対象者に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している自治体においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって住民の皆さまに行っていただく手続きや具体的な給付方法は、自治体ごとに異なりますのでお住まいの自治体から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。
自治体によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。通常の場合、自治体の準備が出来次第、給付対象者に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している自治体においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。
給付金の支給に当たって住民の皆さまに行っていただく手続きや具体的な給付方法は、自治体ごとに異なりますのでお住まいの自治体から送付される申請書・確認書等の内容をご確認ください。給付ごとに各市町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。
市町村に存在する情報が正しければ、適切に対応してもらえますが、納税者側の認識と異なる可能性も出てくると思います。個人住民税の課税主体である市町村から発信される情報をチェックするという意識が必要ではないでしょうか。また、その他市町村に正しい情報を伝える手段として確定申告があると思います。
例えば給与所得者には年末調整を実施した結果、源泉徴収票が配布されますが、控除不足額がある場合は源泉徴収票の控除外額に記載され、その記載された金額を元に調整給付のうち不足額給付が算定されるとの記載があります。
令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
(令和6年2月5日国税庁)
10-7源泉徴収票の「控除外額」と給付金
源泉徴収票の「控除外額」は、所得税及び個人住民税の定額減税と併せて行われる各種給付措置の一つである「調整給付」(所得税から定額減税で引ききれないと見込まれる人への給付)のうち、令和7年に実施する不足額給付の額を算出する際に用います。
給与所得者が源泉徴収票で控除外額を意思表示するのであるならば、年金受給者や個人事業者は確定申告書で意思表示するのがベターではないかと考えます。申告納税方式では提出した情報は納税者側にありますが、特に確定申告をしていない年金受給者に関して賦課課税方式では、どのような情報が市町村にあるのかが不明です。令和6年度に関しては、適切に定額減税の適用を受けるため、確定申告をしていない年金受給者の情報を市町村に正しく伝えるためにも、確定申告という選択肢も検討してはと考えます。

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)