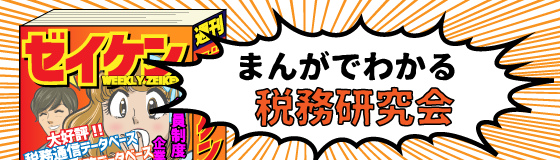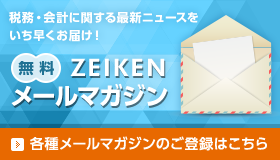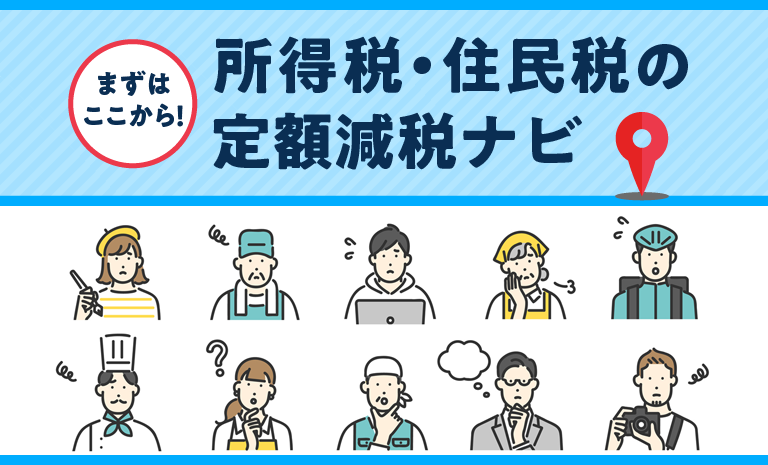

5.定額減税を難しくしている点
定額減税は、令和6年度の税金を還付する(所得税3万円、個人住民税1万円)一年限りの制度なので、一見単純に見えますが、実務に落として考えると複雑で分かりにくい制度です。定額減税のどのような部分が私たち納税者にとって分かりにくいのかを簡単に整理してみたいと思います。なお、あくまでも筆者の私見によりまとめたものであり、網羅性を担保するようなものではありませんので、一つの見方としてご理解ください。
定額減税の理解を難しくしている点
(1)対象となる納税者の範囲が異なる
- 異なる2つの税目の納税者を対象にした減税であること
- 異なる2つの税目の所得にズレがあること
- 定額減税の対象から非居住者を外し、居住者に限定していること
(2)定額減税の実施者
- 所得税(国税)と個人住民税(地方税)では定額減税の実施者が異なること
- 所得税は給与支払者等の源泉徴収義務者や事業者本人が実施(申告納税方式)
- 個人住民税は各市町村が決定し、納税者に通知(賦課課税方式)
(3)定額減税の実施方法
- 所得税の納税者は①給与所得者、②公的年金等受給者、③事業所得者等、の3つに大別され、それぞれ減税方法が決められていること
- 個人住民税の納税者は令和5年所得を元に算定された令和6年度個人住民税額に対して賦課決定されること
- 本人及び扶養親族に係る減税額が、実際の所得税額ないしは個人住民税額を上回っている場合は、自治体(市町村)から差額が給付されること<調整給付>
(4)減税額の最終確定
- 所得税については合計所得金額が年末にならないと確定しないにも関わらず、給与所得者に対しては令和5年度の実績を元に予測して6月から定額減税を実施すること
- 扶養親族の判定は令和6年12月31日となるため、そこまで最終的な減税額は確定しないこと
- 個人住民税は令和5年所得をベースに決定するため、確定値に対して実施されること
(5)扶養親族の範囲
- 今回の定額減税の対象となる扶養親族の定義が、所得税における扶養控除の定義と異なること
- 扶養親族については、納税者の所得税ないし個人住民税に対して定額減税が実施されるが、所得のある(※)扶養親族については当該扶養親族自身の給与、アルバイト料に係る所得税に対して定額減税が実施されるケースがあること
※所得の有無の判断ポイント
年間の合計所得金額48万円(給与収入のみであれば年間103万円))超であれば、所得があるとみなされます

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)