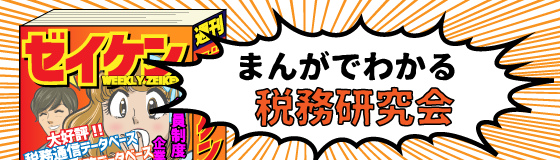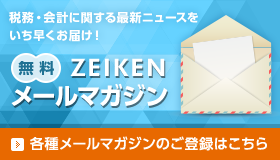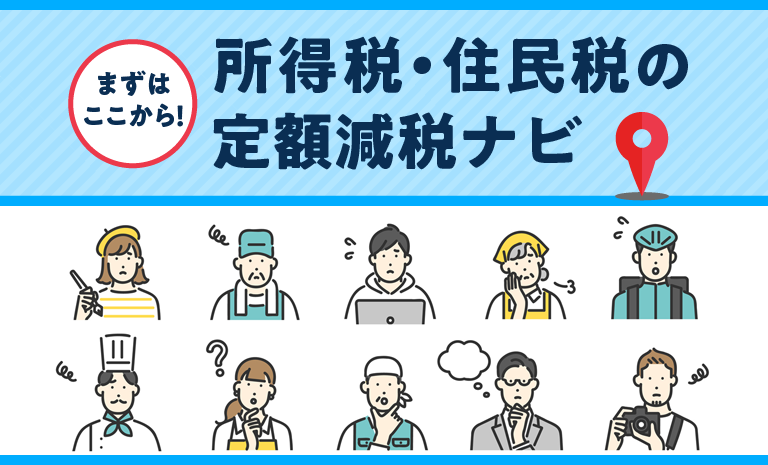

6.給付じゃなくて定額減税
コロナ禍で1人10万円支給されましたが、そこで採用された手法は給付でしたが、今回は定額減税です。今回減税という手法にこだわったのには、政府が税金の還付(還元)と位置づけたためと考えられます。
過去2年間の税収増を還元するための施策
還元する対象は税金を納めた納税者
税として直接還元=定額減税者
これまで企業内に留保されてきた利益を賃上げ税制によって給与として従業員に還元させ、定額減税により所得税等を減額することで、個人に所得が増加していることを実感してもらい、消費を喚起しようと意図が見えます。減税 による恩恵を実感できるように、給与明細に減税額を表記することが義務付けられたことからも分かります。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)
定額減税を行う趣旨
定額減税を行う趣旨
- 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和
- デフレ脱却のための一時的な措置
- 国民の可処分所得を直接的に下支えする措置
- 過去2年間の税収増を納税者である国民に分かりやすく「税」の形で直接還元
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年1月29日 総務省自治税務局市町村税課)Q1-2
賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため。
賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するには、国民の可処分所得を直接的に下支えする所得税・個人住民税の減税が最も望ましいと考えられたため。
趣旨を理解すれば定額減税を選択した理由も理解できますが、一方で実務担当者に大きな負荷が発生しているのも事実です。
定額減税は今年限りの施策なのに、給与明細に減税額が分かるような表記を義務化し、減税累計額を管理できるようにするシステム開発が必要
制度が決まった後、令和6年6月実施までの準備期間が非常に短かった
実務担当者やシステムベンダーに多大な負荷が発生しているが、そのコストの転嫁先が難しい(企業内で吸収せざるを得ない)
決して給付が良い訳でもなく、マイナンバー等での個人情報の管理が途上にある以上、適切な給付ができるとも限りません。ただ、定額減税を選択するにしても、年末調整で一律実施する方法であれば現場の混乱は最小限に抑えられたのではないかと思います。しかしながら、その場合だと少しでも早く家計が潤うことを個人に感じてもらいたいという政策の狙いが薄れるという判断もあったでしょう。今回の定額減税が適切であったのか、私たちは制度を検証し、必要に応じて声を上げる等の行動が求められるのではないでしょうか。

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)