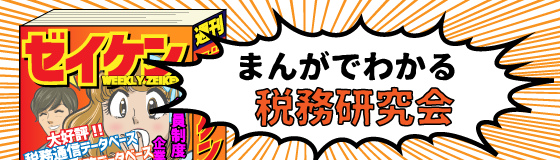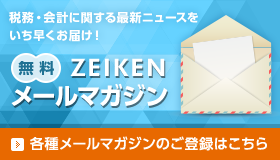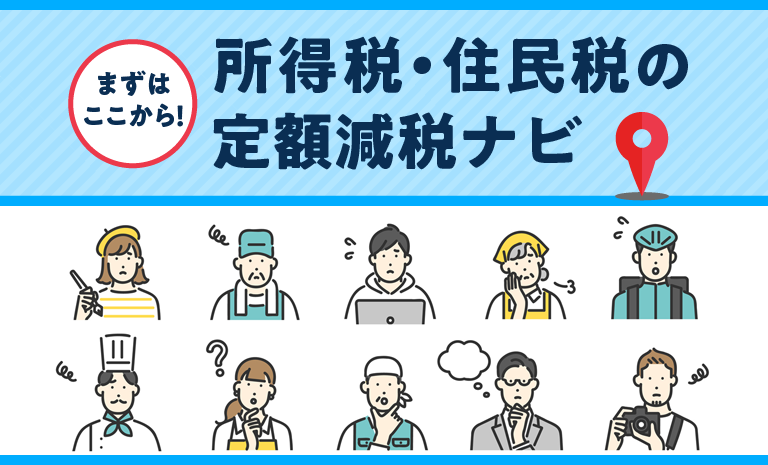

8.個人住民税における納税者
今回は個人住民税に関する定額減税の納税者を確認することにします。
ポイントは以下の3つと考えます。
①前年の所得金額を有する者が定額減税の対象となる
②居住者
③所得割から控除であって、譲渡所得等の納税者は対象とならない
個人住民税は賦課課税方式のため市町村側で計算され、通知されるため、納税者側で個別に判断しなくて良いと考えられていますが、正しく処理されているのか納税者側でもチェックしておく必要があると思います。
個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年1月29日 総務省自治税務局市町村税課)
2-1-1「定額減税の内容如何」
今回の定額減税は、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)である所得割の納税義務者に係る所得割額から控除するものであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されない。
よって、以下の者は定額減税の対象とはならない。
- 前年の合計所得金額が1,805万円を超える者
- 前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
- 所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
- 税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者
①前年の所得金額を有する者が定額減税の対象となる 令和6年度の個人住民税は、令和5年の所得を課税対象として決定されます。したがって所得税と異なり、令和5年分の所得に対して個人住民税を納税する者が令和6年度の定額減税の対象者となります。 例えば、令和5年の途中に離職し、令和6年の所得が無い者であっても、令和5年中の所得に基づき令和6年度分の個人住民税の納税義務が発生する場合には、定額減税の対象になると考えられます。
②居住者 居住者かどうかの判断基準は所得税法の基準を準用すると考えられますが、個人住民税の難しいところは令和6年度の個人住民税は令和5年所得に基づくものであり、所得税と課税所得のタイミングがずれていることです。 したがって令和6年途中に入国し、非居住者から居住者になった者については、令和5年度分の個人住民税が存在しないため、個人住民税の定額減税の適用はないと考えられます。
③所得割から控除 定額減税の対象となるのは所得割のみであり、均等割や利子割、配当割、株式等譲渡所得割しか有しない納税者は対象となりません。

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)