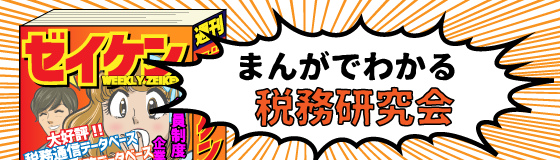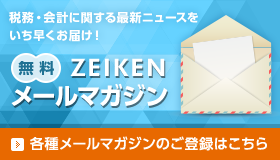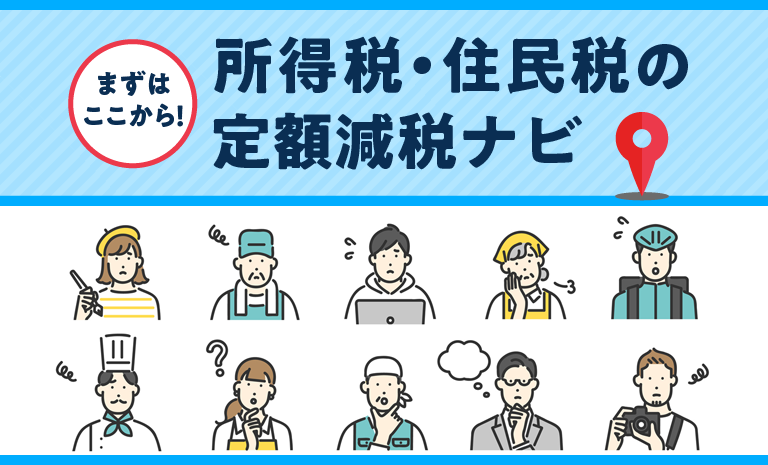

7.所得税における納税者
私たちは、所得税と個人住民税では納税者の範囲が異なるということを理解する必要があります。所得税よりも個人住民税の納税者の範囲が広いため、所得税で減税対象とならなかった納税者でも、個人住民税で減税対象となる納税者が存在します。
ということで、所得税と個人住民税、それぞれについて定額減税を理解する必要があります。今回は所得税に関する定額減税の納税者を確認することにします。 ポイントは以下の3つと考えます。 ①令和6年分所得税の納税者及び扶養親族 ②居住者 ③令和6年分の合計所得金額が1,805 万円以下
令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
(令和6年2月5日 国税庁)
1-1「定額減税の概要」
- 令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
- 定額減税の対象となる所得税は令和6年分所得税
①令和6年分所得税の納税者 令和6年分の所得に対して所得税を納税している者が対象となります。
②居住者 以下のように定義されています。
居住者
国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
非居住者
居住者以外の個人
居住者であった納税者が令和6年中に出国して非居住者となった場合でも、出国するまでは居住者として国内で納税しているため、定額減税は適用されます。 一方、令和6年中に入国し、非居住者から居住者になった者でも令和6年中に所得税の納税者になっている者は、その所得税に対して定額減税が適用されます。
令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
(令和6年2月5日 国税庁)
2-7「基準日前に死亡退職・非居住者となった人に対する定額減税」
死亡により退職した人及び年の中途で海外の支店等への転勤などにより出国し非居住者となった人
<令和6年5月31日以前>
- 令和6年6月1日以後にいわゆる準確定申告書を提出する。
- 令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合には、令和6年6月1日以後に更正の請求書を提出する。
③令和6年分の合計所得金額が1,805 万円以下 年間2,000万円超の給与所得者は定額減税の対象から除外されました。給与所得控除が195万円あるため、所得金額として1,805万円以下と表現されています。 当然令和6年度の所得が確定するのは12月末であり、令和6年6月の段階で未確定ですが、高額所得者の可能性がある者を含め全ての給与所得者を一旦定額減税の対象とすることになりました。12月末に高額所得者であるかが確定するため、定額減税の対象にならなかった者は年末調整か確定申告にて調整することになります。
令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)
(令和6年2月5日 国税庁)
2-8所得制限を超える人から定額減税不要の申出があった場合
合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれるかどうかにかかわらず、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月以後の給与等に係る源泉徴収において、控除対象者は一律に減税額の控除を受けることになりますので、控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)