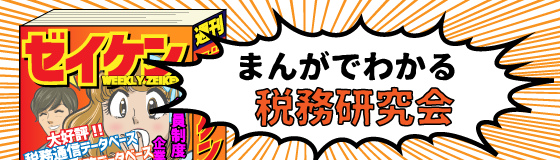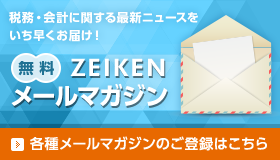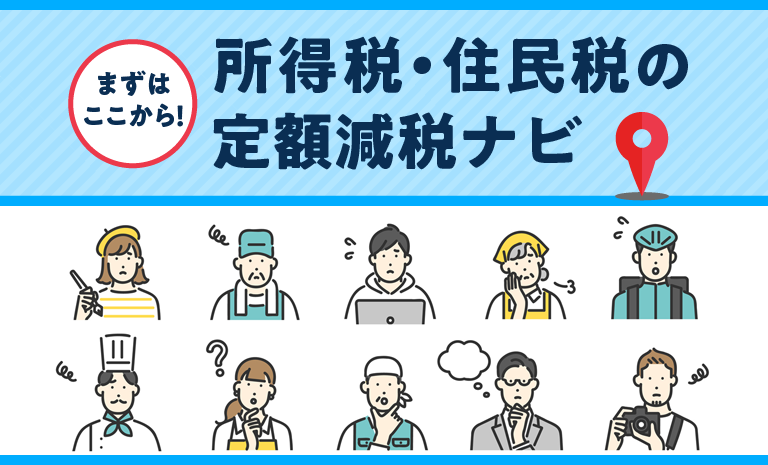

9.復興特別所得税は対象外
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。
①前年の所得金額を有する者が定額減税の対象となる ②居住者
ただし、控除しきれない額が発生する場合は調整給付の適用を受けることができます。(調整給付については、この後のコラムで記載します)
今回の定額減税は所得税が対象となります。所得税には、所得税と復興特別所得税があり、復興特別所得税は対象になっていません。一方、給与所得者が源泉徴収される所得税は、所得税と復興特別所得税が一体となっており、これを区別することはできませんので、復興特別所得税を考えることなく定額減税の対象となりました。
これを裏から眺めると、源泉徴収義務者は、月次は所得税と復興特別所得税の区分はせずに定額減税を行うけれども、年末調整では所得税に対して定額減税が行われていることの確認が必要になる可能性があります。
年末調整の対象者で、かつ、令和6年中に支払の確定した給与等を基に年末調整により計算した年調所得税額がある人については、その年調所得税額から年調減税額を控除します。この年調所得税額から年調減税額を控除した後の金額に 102.1%を乗じて、復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
したがって源泉徴収義務者は年調所得税額>年調減税額であることを一応確認し、控除不足額が生じている場合は源泉徴収票に控除外額として記載することが必要になるのではないでしょうか。

- 1.本当に終わった!?定額減税(2024年07月24日)
- 2.分かりにくい定額減税(2024年07月24日)
- 3.二重取りが発生(2024年08月26日)
- 4.二重取りでも大丈夫!?(2024年08月26日)
- 5.定額減税を難しくしている点(2024年09月25日)
- 6.給付じゃなくて定額減税(2024年09月25日)
- 7.所得税における納税者(2024年10月24日)
- 8.個人住民税における納税者(2024年10月24日)
- 9.復興特別所得税は対象外(2024年11月27日)
- 10.扶養親族(2024年11月27日)
- 11.公的年金、個人事業者(2024年12月24日)
- 12.調整給付(2024年12月24日)