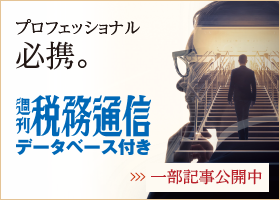第113条の2第6項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第113条の2第6項中「第57条の2第1項」とあるのは「第81条の10第1項」と、「特定支配事業年度」とあるのは「特定支配連結事業年度」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。
2 法第81条の10第1項に規定する政令で定める連結子法人は、法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。
3 法第81条の10第1項に規定する政令で定める法人は、連結子法人のうち、連結開始等(連結親法人との間に連結完全支配関係を有することとなつたことをいう。以下この項において同じ。)に基因して法第4条の5第2項(連結納税の承認の取消し等)の規定により当該連結開始等の日前に受けた法第4条の2(連結納税義務者)の承認が取り消された連結法人で当該承認に係る連結事業年度(当該承認を受けた日から当該連結開始等の日の前日までの間の連結事業年度に該当しない事業年度を含む。)において法第81条の10第1項に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものとする。
4 法第81条の10第1項に規定する支配日に準ずる日として政令で定める日は、同項に規定する連結前欠損等法人(第6項第1号及び第4号において「連結前欠損等法人」という。)が法第81条の9第2項第1号に規定する最初連結事業年度(第6項第4号及び第9項第1号において「最初連結事業年度」という。)前の連結事業年度又は事業年度において他の者との間に当該他の者による特定支配関係(法第81条の10第1項に規定する特定支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつた日とする。
5 法第81条の10第1項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定支配日以後5年を経過した日の前日まで(特定支配関係の喪失等の事実が生じた欠損等連結法人にあつては、当該事実が生じた日まで)に生じた次に掲げる事由とする。- 一 欠損等連結法人(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある欠損等連結法人及び欠損等連結法人でない連結法人を含む。次号において同じ。)の全てが当該特定支配日の直前において事業(連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人の発行済株式又は出資の全部又は一部を有することを除く。以下この項において同じ。)を営んでいない場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該特定支配日以後に事業を開始すること。
- 二 欠損等連結法人の全てが当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)の全部を当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該欠損等連結法人のいずれかが当該欠損等連結法人の全ての当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模の合計額のおおむね5倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含むものとし、当該欠損等連結法人のいずれかから受けるものを除く。第4号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
- 三 前2号に規定する場合において、欠損等連結法人である連結親法人が自己を被合併法人とする適格合併を行うこと。
- 四 法第81条の10第1項に規定する他の者又は当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係がある者(欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を除く。以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から欠損等連結法人のいずれかに対する債権(第113条の2第17項に規定する債権に相当する債権に限る。以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務の免除等(第113条の2第18項に規定する債務の免除又は現物出資に相当するものをいう。)が行われることが見込まれる場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、債務者である当該欠損等連結法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超える資金借入れ等を行うこと。
- 五 前号の特定債権が取得されている場合において、同号の債務者である欠損等連結法人が自己を被合併法人とする適格合併(当該欠損等連結法人が連結子法人である場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がない法人を合併法人とするものに限る。)を行うこと。
- 六 欠損等連結法人が特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等連結法人の当該特定支配日の直前の特定役員(法第57条の2第1項第5号(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する役員をいう。)の全てが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をした場合で、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等連結法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね100分の20以上に相当する数の者が当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合(当該欠損等連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(以下この号において「他の連結法人」という。)の業務に従事することに伴つて、当該欠損等連結法人の使用人でなくなつた場合を除く。)において、当該欠損等連結法人の非従事事業(当該旧使用人(他の連結法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資に伴い引継ぎを受けた使用人を含む。)が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。以下この号において同じ。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね5倍を超えることとなること(当該欠損等連結法人の事業規模算定期間(欠損等連結法人の当該特定支配日以後の 期間を1年ごとに区分した期間又は当該特定支配日の属する連結事業年度若しくは事業年度以後の連結事業年度若しくは事業年度をいう。以下この号において同じ。)における非従事事業の事業規模(当該事業規模算定期間において当該欠損等連結法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする合併、分割又は現物出資でそれぞれ第4条の3第4項、第8項又は第15項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する要件の全てを満たすものを行つている場合には、当該合併、分割又は現物出資により移転を受けた事業に係る部分を除く。)が当該事業規模算定期間の直前の事業規模算定期間における非従事事業の事業規模のおおむね5倍を超えない場合を除く。)。
6 前項に規定する特定支配関係の喪失等とは、次に掲げるものをいう。- 一 法第81条の10第1項に規定する他の者(第4項の連結前欠損等法人に係る同項の他の者を含む。)が有する連結親法人の株式が譲渡されたことその他の事由により、当該連結親法人が当該他の者との間に当該他の者による特定支配関係を有しなくなつたこと。
- 二 次に掲げる行為によつて欠損等連結法人に生ずる債務の消滅による利益の額が当該欠損等連結法人の当該行為の日の属する連結事業年度開始の時における法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第1項の規定の適用がある連結欠損金額に係るものに限るものとし、当該欠損等連結法人が当該連結事業年度の直前の連結事業年度又は事業年度終了の時において法第57条の2第1項又は第81条の10第1項に規定する評価損資産を有している場合には、当該評価損資産の評価損(その時の価額がその時の帳簿価額に満たない場合のその満たない部分の金額をいい、当該金額が当該欠損等連結法人の連結個別資本金等の額の2分の1に相当する金額と1000万円とのいずれか少ない金額に満たないものを除く。)の合計額(その時において有する第113条の2第6項に規定する資産を同項に規定する財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のうちにその時の価額からその時の帳簿価額を控除した金額が当該いずれか少ない金額を超えるものがある場合には、当該資産の当該控除した金額の合計額を控除した金額)を含む。以下この項において「連結欠損金個別帰属額等」という。)のおおむね100分の90に相当する金額を超える場合(当該行為によつて消滅する債務の額が当該欠損等連結法人の当該行為の直前における債務の総額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該利益の額が当該連結欠損金個別帰属額等のおおむね100分の50に相当する金額を超えるとき)における当該行為
- イ 欠損等連結法人がその債権者から受ける債務の免除(当該債権者において当該免除により生ずる損失の額が法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものに限る。)
- ロ 欠損等連結法人がその債権者から受ける自己債権(当該欠損等連結法人に対する債権をいう。)の現物出資
- 三 連結親法人について生じた第113条の2第5項第2号に規定する更生手続開始の決定等
- 四 連結前欠損等法人である欠損等連結法人についての第113条の2第8項に規定する場合における同項に規定する事由、同条第9項に規定する行為及び同条第10項に規定する事実(当該欠損等連結法人の最初連結事業年度開始の日前に生じたものに限る。)
7 第113条の2第11項から第14項までの規定は、第5項第2号、第4号及び第6号に規定する事業規模について準用する。この場合において、同条第14項中「確定申告書」とあるのは、「連結確定申告書」と読み替えるものとする。
8 法第81条の10第1項に規定する事由に該当することとなつた日として政令で定める日は、第5項各号に掲げる事由のうち同項第3号又は第5号に掲げる事由以外のものに該当する場合にあつてはその該当することとなつた日とし、同項第3号又は第5号に掲げる事由に該当する場合にあつてはこれらの号の適格合併の日の前日とする。
9 法第81条の10第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。- 一 第5項第1号から第3号までに掲げる事由に該当する場合 法第81条の10第1項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額(法第81条の9第2項の規定により連結欠損金額とみなされる次に掲げる金額を除く。次号において「対象連結欠損金額」という。)
- イ 最初連結事業年度開始の日の前日において欠損等法人(法第57条の2第1項に規定する欠損等法人をいう。)である法第81条の10第4項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の適用事業年度(法第57条の2第1項に規定する適用事業年度をいう。)前の各事業年度において生じた法第81条の9第2項第1号イに規定する災害損失欠損金額
- ロ 欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人と他の法人との間で法第81条の10第2項に規定する該当日(ロにおいて「該当日」という。)以後に当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人とする法第81条の9第2項第2号に規定する適格合併が行われる場合又は欠損等連結法人である連結親法人若しくは連結子法人との間に同号に規定する完全支配関係がある他の内国法人で当該連結親法人若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合における当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の内国法人の当該適格合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度前の各事業年度において生じた同号イに規定する未処理災害損失欠損金額
- 二 第5項第4号から第6号までに掲げる事由に該当する場合 当該事由に該当することとなつた欠損等連結法人の対象連結欠損金額に係る法第81条の9第6項に規定する連結欠損金個別帰属額
10 法第81条の10第1項の規定の適用を受ける連結法人に係る第155条の21第3項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第1号イに規定する特定連結欠損金個別帰属額並びに同号ロ及び同項第2号に規定する連結欠損金額及び連結欠損金個別帰属額には、法第81条の10第1項に規定する政令で定める金額に係るものを含まないものとする。
第113条の2第6項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、法第81条の10第1項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する政令で定める資産について準用する。この場合において、第113条の2第6項中「第57条の2第1項」とあるのは「第81条の10第1項」と、「特定支配事業年度」とあるのは「特定支配連結事業年度」と、「資本金等の額」とあるのは「連結個別資本金等の額」と読み替えるものとする。
2 法第81条の10第1項に規定する政令で定める連結子法人は、法第81条の9第2項第1号(連結欠損金の繰越し)に規定する特定連結子法人とする。
・・・