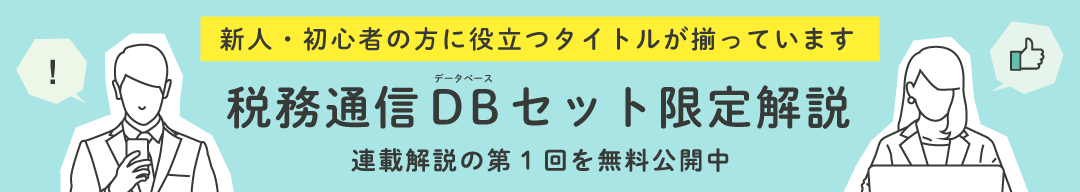実務未経験でもきちんと理解!ゼロからわかる税効果会計の入門 第1回 なぜ、税効果会計が必要なのか?
公認会計士・税理士 峯岸 秀幸
|
【略歴】
公認会計士・税理士 税理士法人タクセイド代表社員 準大手監査法人、大手税理士法人等を経て現職。青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻税法務プログラム修士課程修了(修士(ビジネスロー))。日本公認会計士協会 租税政策検討専門委員会 専門委員長、一般財団法人会計教育研修機構 実務補習講義担当講師(税務教科)(2022年期~)等 (2025年7月現在)
|
はじめに~本連載の目的
本連載は、税効果会計の実務に先立って知っておくべき(主に法人税法に関する)知識や、業務で実際に繰延税金資産の計算をする際にどのような資料を準備すべきか、何に注意すべきかといった極めて実践的な内容に重点を置くことで、税効果会計の基礎と背景を理解し、実務に臨むための土台を築くことが目的です。
法人税の負担率と税効果会計の目的
さて、日本の法人の所得に課される税金、具体的には、国税である法人税・地方法人税と、地方税である法人住民税・所得に課される法人事業税・特別法人事業税を、各法人がどれだけの割合で負担しているか、ご存知でしょうか。財務省はウェブサイトで、日本の法人実効税率を29.74%としています(※)。
(※)財務省ウェブサイト「諸外国における法人実効税率の比較」(2024年1月現在)
<https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c01.htm>(2025年4月1日最終確認)参照。この税率は、法人事業税の外形標準課税適用法人であること及び法人住民税と法人事業税について標準税率が適用されることを前提としたものである。もっとも、地方公共団体によって超過税率を採用している場合があるから、実効税率は、同じ外形標準課税適用法人であっても、その法人が所在する地方公共団体がどこかによって変わることになる。
実際には、これは一定の条件のもとで大企業が負担することになる税率で、世の大部分を占める中小零細企業の実効税率を同様に計算すると33.58%となります。いずれにしても、我が国では法人の儲けに対して実に3割の税金が課されています。
いま、「法人の所得」を敢えて「法人の儲け」と言い換えました。法人の一会計期間における経営成績を報告するための書類である損益計算書において、税金を課される前の法人の儲けは、「税引前当期純利益」として表示されます。
法人の儲けに課されるのが法人税であるのなら、損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目に表示されている金額を「税引前当期純利益」の金額で割ると、先に述べた割合(29.74%)になってよさそうなものです。
しかし、多くの場合にはそうなりません。次の表は、某社の有価証券報告書に掲載された令和6年9月期の個別損益計算書から数値を抜粋して作成したものです(【参考1】)。
【参考1】個別損益計算書の数値例

上記表を見ていただくと、税効果会計適用前の実効税率(約32.8%)と、適用後の実効税率(約28.9%)は異なること、適用後の実効税率の方が先に述べた実効税率(29.74%)に近い(しかし一致もしない)ことが見て取れるでしょう。その理由について今は述べませんが、本連載を読了していただく頃にはご理解いただけると思います。
これから本連載が扱っていく税効果会計は、一言で言えば、損益計算書の税引前当期純利益に対する法人税等の割合を、法人実効税率(29.74%)の割合に近づける、あるいは両者の対応関係を確認できるようにすることを目的にしている、とまずは理解するのがいいでしょう。
 ちょっぴり休憩コーヒーブレイク♪ ~なぜ税効果会計が必要なのか?~
ちょっぴり休憩コーヒーブレイク♪ ~なぜ税効果会計が必要なのか?~
ここまで読んだ方の中には、「なぜ税効果会計が必要なのか?」という疑問を持つ方もいるでしょう。実はその答えは、損益計算書の税引前当期純利益に対する法人税等の割合と、法人実効税率の割合の対応関係を確認できるようにするという目的と表裏一体です。
もし、法人税が「法人の儲け」であるところの会計上の利益に法人税率を乗じて計算されるものであれば、税引前当期純利益と法人税等の対応関係を明らかにするための特段の会計処理を求める税効果会計など不要でしょう。
ただ、実際には、法人税はその課税標準である課税所得に法人税率を乗じて計算することとされており、この課税所得と会計上の利益の金額が一致しないことが、税効果会計が必要とされる所以なのです。
会計基準がいう税効果会計の目的
「税効果会計に係る会計基準」(企業会計審議会、1998年)では、「税効果会計の目的は、 企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合 に、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(いわゆる法人税等)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることである」(同会計基準第一参照)と述べられています。
税引前当期純利益と法人税等という損益計算書科目の対応関係を明らかにするための会計手続ですから、問題になるのは"会計上の収益・費用の額と課税所得計算上の益金・損金の額の違い"でありそうなのに、「企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合」とされていることに分かりにくさを感じるのではないでしょうか。
ですが、ここではひとまず、資産と負債に着目した書きぶりになっていることに注意を向ける必要はありません。実務においては、税効果会計は、企業会計上の収益・費用の額と、課税所得計算上の益金・損金の額の差異に対して適用されるものであると考えておく方が、まずは理解が容易でしょう。
さて、読者の皆さんは何らかの形で経理実務や申告書作成実務に関与しているはずですから、会計上の収益・費用の額と、課税所得計算上の益金・損金の額の範囲が同じではないことはご存知なはずです。ここでは、その差異がなぜ生じ、実務上はそれがどのように把握されるか、もう少し詳しく述べておきます。
法人税法は「企業会計準拠主義」である
企業会計上の収益・費用の額と法人税法の課税所得計算上の益金・損金の額がなぜ、どのように異なるのかという話は、企業会計と税務会計の目的観の違いから始めることもできます。
端的に言えば、企業会計には会社を巡る関係者の利害を調整することや投資者の意思決定のために有用な情報を提供するという目的があり、税務会計には公平な課税所得計算という要請があり、両者の目指すところが違う以上、計算される利益と所得の内容も自ずと異なることになります。ですが、ここでは、法人税の所得計算のルールを概観することで、企業会計上の収益・費用の額と法人税法の課税所得計算上の益金・損金の額の差異を浮き彫りにしたいと思います。
法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とされ( 法法21 )、その所得の金額の計算の通則が 法人税法22条 です。引用すると以下のとおりです。
【法人税法22条】
第22条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
2 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
4 第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。
5 第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)及び残余財産の分配又は引渡しをいう。
なお、第4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」を、一般に"公正処理基準"と呼びます。本稿でもしばしばこの呼称を用いるようにします。
法人税法22条 では、まず、法人税の課税標準である所得は、益金と損金の差額として計算されるものとしたうえで、益金と損金の具体的内容について定めています(【参考2】)。その基本構造は以下のとおりです。
【参考2】法人税法22条の規定内容
(原則)益金の額=公正処理基準に従って計算した収益の額
損金の額=公正処理基準に従って計算した原価・費用・損失の額
(例外)法人税法に別段の定めがある場合にはそちらが優先される。
ここでいう公正処理基準が具体的に意味するところについては実は厚い議論があり、ここで詳しく述べることはできませんが、例えば、税法の教科書には、その立法趣旨について以下の記載があります(【参考3】)。
【参考3】公正処理基準の立法趣旨
この規定は、昭和42年に、法人税法の簡素化の一環として設けられたものであって、法人の各事業年度の所得の計算が原則として企業利益の算定の技術である企業会計に準拠して行われるべきこと(「企業会計準拠主義」)を定めた基本規定である。
(金子宏『租税法[第24版]』(弘文堂、令和3年11月24日発行)356頁)
要するに、公正処理基準とは基本的には企業会計上の基準のことであり、企業会計上の基準といえば、代表的には企業会計原則や企業会計基準委員会が公表する企業会計基準が該当します。税効果会計を適用する必要がある会社には公認会計士や監査法人の会計監査を受けているところが多いと思いますが、そういった会社が決算を組むうえで適用しなければならない企業会計基準が、公正処理基準に当たり得るのです。
こう言われてしまうと、益金・損金の額は、公正処理基準であるところの企業会計基準に従って計算した収益・原価・費用・損失の額である、ということになりますから、企業会計上の利益と法人税法上の所得は一致しそうであるし、もし一致するのであれば税効果会計は要らないように考えられますが、実際にはそうではありません。上記の規定はあくまで原則論に留まるのであって、実は例外の範囲が相当に広いのです。
「企業会計準拠主義」だが「税会不一致」である
「企業会計準拠主義」を採用する法人税法の下にあって、会計上の利益と法人税法上の所得が一致しない範囲は広く、このような状況を「税会不一致」と呼ぶことがあります(【参考4】)。
【参考4】法人税法22条の規定内容(再掲)
(原則)益金の額=公正処理基準に従って計算した収益の額
損金の額=公正処理基準に従って計算した原価・費用・損失の額
(例外)法人税法に別段の定めがある場合にはそちらが優先される。
税会不一致の理由は、第一に、【参考2】における原則に対する例外であるところの「別段の定め」が広範にわたることです。益金=収益を定める 法人税法22条 2項の別段の定めと、損金=原価・費用・損失を定める3項の別段の定めには以下のようなものがあります(【参考5】)。
【参考5】各規定における別段の定めの違い
・ 法人税法22条 2項の別段の定め
受取配当等( 23条 ~ 24条 )・資産の評価益( 25条 )・受贈益( 25条の2 )・還付金等( 26条 ~ 28条 )
・ 法人税法22条 3項の別段の定め
資産の評価損( 33条 )・役員給与等( 34条 ~ 36条 )・寄附金( 37条 )・繰越欠損金( 57条 ~ 59条 )など
例えば、 法人税法23条 には、一定の受取配当等は益金の額に算入しないことが定められています。配当金を受け取った際、会計上はその金額を受取配当金として収益計上するでしょう。会計上は収益計上されますが、課税所得計算上は益金の額から除く=益金不算入にする、ということが定められているため、この条文は会計と税務を不一致にするものとなります。
この 法人税法23条 のように、別段の定めには多くの場合に「収益・原価・費用・損失であるが益金・損金としない」と規定されており、これこそ税会不一致になる原因の最たるものです。
また、 法人税法22条 3項2号の文言も、税会不一致の大きな原因であることを知っておきましょう(【参考6】)。
【参考6】法人税法22条3項の規定内容
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 (略)
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で 当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。 )の額
三 (略)
損金となる費用の範囲から、事業年度末日において債務が確定していないものが除かれています。「債務の確定」の意味合いについても追々説明しますが、会計上、債務が確定しなくとも費用を計上することがよくあります。その典型に負債性引当金があります。
例えば、賞与引当金は、将来支給することになる賞与総額を見積り、そのうち決算の時点で既に支給対象期間が経過している分について費用と負債を計上するものです。しかし、賞与について債務が確定したというには、賞与の支給対象期間が満了しているなどの事情が必要ですから、決算日において計上される賞与引当金繰入額は、債務が確定しない費用となり、損金算入される費用の範囲には含まれません。このような債務確定の有無が決め手になって損金不算入になる費用は、実務上は多く生じます。
以上のように、法人税法は「企業会計準拠主義」を採用していると言いながら、実際には税会不一致である部分が多くあります。その原因として、「別段の定め」の存在と、「債務の確定」という概念の存在を、まずは押さえておきましょう。実際には、他にも税会不一致となる原因は存在しますが、税効果会計の実務の入門的な知識としては、この2つの原因をしっかりと理解すれば足りるところです。
さて、今回は、最初に税効果会計の目的を述べ、税効果会計が必要とされる理由は、会計上の当期純利益と法人税法上の課税所得が一致しないところにあること、その一致しない原因を所得の計算ロジックの観点から確認しました。
両者が一致しないポイントは、会計上の収益・原価・費用・損失を税務上の益金・損金に変換する過程で把握できると言えますが、この変換の過程を表現するものが、法人税の申告書です。税効果会計の実務は、まず、この申告書から税効果会計が適用されるべきポイントを特定していくことから始まるので、次回は、法人税の申告書の仕組みについて概観していきます。
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします