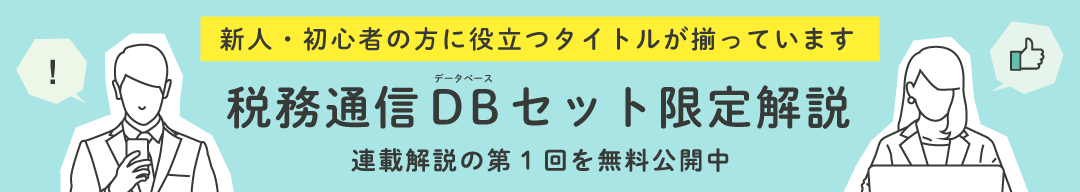[全文公開] 学ぼう! 経理マンのための源泉所得税入門 第1回 総説1~源泉所得税の概要【税務通信データベース セット限定解説】
税理士 堀腰 三知男
|
【略歴】
東京国税局課税第二部法人課税課課長補佐、麹町税務署特別国税調査官、甲府税務署副署長、税務大学校教育第一部・総合教育部教授、東京国税局総務部税務相談室副室長、小千谷税務署長、東京国税局調査第二部・四部統括国税調査官、本郷税務署長を経て、現在税理士 (2019年4月現在)
|
はじめに
我が国の所得税に源泉徴収制度が導入され、源泉所得税の納税がスタートしてから間もなく120年を迎えます。
現在の源泉所得税は幾多の改正を経て今日の姿になっています。スタートしてから約60年間は日清戦争から太平洋戦争の時期と重なり、源泉所得税の性格や改正も戦費調達の色彩が濃いものでしたが、今日では歳入(一般会計)の約3割を、また、所得税全体の約8割を占めるなど消費税に次ぐ重要な税となり、納税の平準性から予算の執行にも大きな役割を果たしています。
源泉所得税に求められる役割は多様です。今後も求められる役割を果たすため、社会構造や経済の変化に応じた改正がなされ、時代のニーズに的確に応えていく重要な税であり続けるものと思います。
この度、機会をいただき「学ぼう!経理マンのための源泉所得税入門」をスタートさせていただくことになりました。週刊税務通信の読者の皆様、特に会社において源泉所得税を担当される新人の皆様の知識の習得と日ごろの業務にお役に立つことができれば幸いです。
第1回は、源泉所得税の沿革や源泉徴収制度の仕組みなどについて説明いたします。
なお、文中意見にわたる部分は、個人的見解に基づくものであることを念のため申し添えます。
Ⅰ 総説
1 源泉所得税の概要
【1】 源泉所得税の沿革
我が国の所得税は明治20年(1887年)に創設され、特定の個人の所得を課税の対象としていましたが、民間企業の増加に伴い、明治32年(1899年)の所得税の全面改正によって第1種(法人の所得)、第2種(公社債の利子)、第3種(個人の所得)に分類して課税されることとなり、併せて第2種の公社債の利子について源泉徴収制度が導入され、源泉所得税が誕生しました。
その後、昭和13年(1938年)には退職給与(現在の退職所得)に、昭和15年(1940年)には勤労所得(現在の給与所得)に、昭和19年(1944年)には丙種事業所得(現在の報酬・料金等)に源泉徴収が導入され、昭和22年(1947年)には年末調整の仕組みが源泉徴収制度に導入され、現行の源泉所得税の体系が確立されました。
【2】 源泉徴収制度の仕組み
源泉所得税は源泉徴収制度に基づいて徴収・納付される所得税で、その源泉徴収制度は源泉徴収の対象とされる所得の支払者を源泉徴収義務者とし( 通法2 ①五)、その支払者が源泉徴収の対象とされる所得の支払の際に、所得者(受給者)が納付すべき所得税を国に代わって支払額から天引き徴収し、徴収した所得税を納付する制度です。
源泉徴収の対象とされる所得は次の表のとおりです。
<源泉徴収の対象とされる所得>
| 所得者 | 源泉徴収の対象とされる所得 |
| 居住者 | ①利子等、②配当等、③給与等、④退職手当等、⑤公的年金等、⑥報酬・料金等、⑦生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金、⑧定期積金の給付補てん金等、⑨匿名組合契約等に基づく利益の分配、⑩特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等、⑪懸賞金付預貯金等の懸賞金等、⑫割引債の償還差益 |
| 内国法人 | ①利子等、②配当等、③定期積金の給付補てん金等、④匿名組合契約等に基づく利益の分配、⑤馬主が受ける競馬の賞金、⑥懸賞金付預貯金等の懸賞金等、⑦割引債の償還差益 |
| 非居住及び
外国法人 |
国内源泉所得のうち特定のもの |
なお、源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間、所得税の徴収の際、所得税の額に100分の2.1の税率を乗じて計算した復興特別所得税を併せて徴収し、納付することとされています( 財確法28 ①②)。
| (注) | 以後記載の所得税や源泉所得税には、復興特別所得税が含まれているものとします。 |
【3】 源泉徴収制度の性格
源泉徴収制度の性格については、「『源泉徴収義務者は、既に確定している源泉所得税額を、単にその支払額から徴収して納付するのみであるから、 源泉徴収制度は課税制度ではなく、租税の徴収制度 であり、 源泉徴収義務者に対する告知処分は、 国が行う納付すべき税額の 課税処分ではなく、 既に確定した国税債権につき納期限を指定して納税の履行を請求する 徴収処分である 』(最判昭45.12.24)」とされています。
【4】 源泉徴収制度の特長
我が国の源泉徴収制度には、次のような特長があります。
イ 長所とされるところ
|
|
|
| A | 支払額を源泉徴収の対象とすることから、課税標準等の把握が容易で正確である。 |
| B | 徴税上の手数が集約化されて徴税費が少なくて済む。 |
| C | 所得税の徴収が確実になされ、かつ、1年を通じて平準化される。 |
| D | 天引徴収、分割納付により、納税義務者の痛税感が少ない。 |
ロ 短所とされるところ
|
|
|
| A | 支払額がそのまま課税標準となるので、原則として必要経費を計算に織り込むことができず、担税力に応じた源泉徴収にならないことがある。 |
| B | 給与所得と退職所得以外の所得については、原則として累進課税を適用せずに比例税率としているので、応能負担の原則を十分に貫けない。 |
| C | 個々の所得についての適用であり、総合課税ができない。 |
| D | 所得税の特質ともいうべき、本来の個人的事情を完全には勘案することができない。 |
【5】 源泉所得税をめぐる法律関係
源泉徴収制度においては、次の三つの法律関係を考えることができます。
| ① |
国と源泉徴収義務者(所得の支払者)との関係
支払者は国に対して源泉徴収義務を負いますので、この関係は公法の関係にあります。 |
| ② |
源泉徴収義務者と所得者との関係
所得者は支払者に対して源泉徴収を受忍する義務を負いますので、この関係は私法の関係にあります。 |
| ③ |
国と所得者との関係
所得者は源泉徴収制度上、国に対して直接的には義務を負いません。 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします