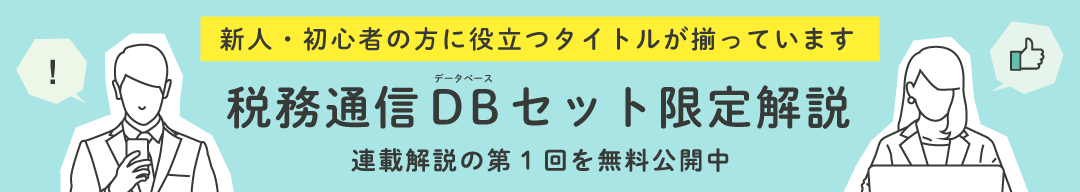[全文公開] 消費税初心者のためのインボイス教室 第1回 インボイス制度の概要【税務通信データベース セット限定解説】
あいわ税理士法人 税理士 佐々木みちよ
税理士 市川 光大
|
あいわ税理士法人
2002年11月、藍和共同事務所を母体として設立。会計・税務コンサルティングをはじめ、株式公開支援、事業承継・相続コンサルティング、組織再編に関するアドバイス業務、グループ通算制度導入支援サービスなどを提供。 【執筆者略歴】 佐々木 みちよ 税理士 2002年藍和共同事務所(現あいわ税理士法人)入所。大手・中堅企業への税務コンサルティング業務に従事するほか、税務専門書籍の執筆、税務専門誌への寄稿、税理士及び事業会社経理・税務担当者向け各種セミナー講師の業務に従事。 市川 光大 税理士 大手税理士専門学校の講師を経て、2016年あいわ税理士法人に入社。上場会社及びそのグループ会社の税務顧問業務を中心に、オーナー企業の相続・事業承継対策なども手掛ける。税務研究会Webセミナー「消費税超入門」の講師を担当。 (2022年1月現在)
|
はじめに
令和5年10月1日からインボイス制度がスタートします。国税庁からはQ&Aが公表され、巷ではインボイス制度に関する情報があふれていますが、消費税の基礎知識なしで理解するのは、なかなか難しいものです。
そこで本連載では、消費税初心者の方々を対象に、消費税の基本的な用語や制度内容とともに、インボイス制度について解説していきます。
| 凡例 |
|
インボイスQ&A
...消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A (平成30年6月(令和3年7月改訂) 国税庁軽減税率・インボイス制度対応室)
|
1.消費税の負担と納付
(1)負担は消費者、納付は事業者
消費税の負担者は、商品を購入したり、サービスを利用したりする最終消費者です。しかし、 消費税の納税義務まで消費者に課しているわけではありません。納税義務は、 商品の販売やサービスを提供する 各事業者に課されています 。
(2)事業者とは
事業者 とは、法人と、事業を行う個人(個人事業者)をいいます。 事業者には消費税の納税義務が課されていますが、 消費者に直接商品の販売等を行う事業者(例えば、小売店)だけに課されているわけではなく、 小売店に商品を卸す卸売業者や、その商品を製造するメーカー、商品の配送を担う運送業者など、 取引の上流に位置する事業者にも課されています 。
(3)消費税の負担と納付の流れ
税抜き10万円の商品を消費者が小売業者から購入したケースで、消費税の負担と納付の流れを見てみましょう。

① 消費者の負担額
消費者は、小売業者から10万円(税抜き)の商品を購入します。負担する消費税1万円との合計で、11万円を小売業者に支払います。
② 小売業者の納付額
小売業者は、消費者から預かった消費税を国に納付しますが、この商品を仕入れる際に支払った消費税を控除した上で納付します。したがって、小売業者は、消費者から預かった消費税1万円から、卸売業者に支払った消費税7千円を控除した3千円を国に納付します。
③ 卸売業者の納付額
卸売業者は、小売業者から預かった消費税7千円から、生産・製造業者に支払った消費税5千円を控除した2千円を国に納付します。
④ 生産・製造業者の納付額
生産・製造業者は、卸売業者から預かった消費税5千円を国に納付します(支払った消費税は控除することができますが、ここではないものと仮定します)。
⑤ 消費者の負担額と、事業者の納付額の関係
事例の各事業者(小売業者、卸売業者、生産・製造業者)が納付する消費税額の合計は1万円となり、消費者が負担した消費税額と一致します。
このように、消費者が負担した消費税額は、商品の生産・製造・流通段階でかかわった各事業者が、それぞれ預かった消費税額から支払った消費税額を控除して納付することで、国に納付される仕組みになっています。
事業者にとっては、預かる消費税は収益ではなく、支払う消費税もコストではありません。仮受金と仮払金のような意味合いしかなく、国に消費税を納付することで全て精算される性質のものです。
2.課税売上げと課税仕入れ
事業者は、モノの販売やサービスの提供時に消費税を預かりますが、どんな取引でも必ず消費税を預かるというわけではありません 。消費税が課される取引と課されない取引が存在します。
消費税が課される取引のことを 課税取引 といい、消費税を預かる側では「 課税売上げ 」、消費税を支払う側では「 課税仕入れ 」といいます。
3.仕入税額控除とその要件
(1)仕入税額控除とは
事業者は、預かった消費税額から支払った消費税額を控除して納付税額を計算します。この控除する仕組みのことを「 仕入税額控除 」 といいます。消費税は、課税仕入れを行った場合に支払いますから、課税仕入れに係る消費税額につき仕入税額控除を受けるということになります。
|
|
(2)仕入税額控除の要件
仕入税額控除を行うための要件のひとつに、「請求書等の保存」があります。 仕入税額控除を行うことで、納税額が少なくなりますから、その取引を行った証拠書類の保存が必要というわけです。
4.インボイス制度とは
(1)仕入税額控除の要件が変わるインボイス制度
令和5年10月1日以後は、仕入税額控除を受けるために保存すべき請求書等が インボイス に変わります。 これがいわゆる「 インボイス制度 」です。インボイスのことを消費税法では「 適格請求書 」といいます。
(2)インボイスとは
インボイスとは、売手が買手に対し、取引に適用される税率や消費税額等を伝えるために交付する書類(又は電子データ)をいいます。
とはいえ、インボイスは、従来の請求書等とは全く別物というわけではありません。これまでの請求書等の記載事項に、3つの項目(登録番号、適用税率、消費税額等)を追加したものがインボイスです。請求書、納品書、領収書、レシートなど、名称も問いませんし、法定事項が記載されていれば、様式も自由です。
「従来の請求書等の様式に若干手を加えたものが、インボイス」 とイメージしていただければ良いでしょう。
|
|
(3)売手の立場からのインボイス制度
① 登録手続き
インボイス制度導入後、買手は、インボイスを保存しないと原則として仕入税額控除を行うことができません。したがって、インボイス制度導入後は、売手は買手からインボイスの交付を求められることになります。
売手がインボイスを交付するためには、 インボイス発行事業者 として税務署長の登録を受ける 必要があります。
|
|
② システム改修
インボイスには、登録番号、適用税率、消費税額等を記載する必要がありますが、従来発行している請求書、納品書等のうち、どの書類に手を加えて、これらの事項を記載するかの検討を行い、それに応じたシステム改修が必要です。取引先に対しても、どのような形でインボイスとして交付するかについて事前に案内が必要でしょう。
(4)買手の立場からのインボイス制度
① 取引先選定に及ぼす影響
インボイス制度導入後、買手は、インボイスを保存しないと原則として仕入税額控除を行うことができません。
取引総額が11,000円(消費税率10%)の取引をする場合、売手がインボイス発行事業者ならば、10,000円が本体価格、1,000円が消費税です。消費税は仕入税額控除を行うことで精算されますから、買手にとってのコストは10,000円です。
一方、売手がインボイス発行事業者でないならば、買手はインボイスの交付を受けられないため、仕入税額控除ができません。したがって、取引総額の11,000円が買手にとってのコストになります。本体価格11,000円の取引を行うイメージです。
このように、 売手がインボイス発行事業者か否かで、買手が負担するコストが変わってきます。 インボイス制度が導入されることで、買手の立場としては、取引先の選定に大きな影響を受けそうです。
|
|
② ワークフローの徹底
インボイス制度導入後は、各種経費についてインボイスの保存がないと、原則として仕入税額控除が認められません。
したがって、経費支出を行う従業員等に対しては、支出時にインボイスを確実に受領することと、その後のワークフローの徹底が必要です。社内研修の実施やシステム改修の要否についても検討を要します。
(5)必須となる全社的な事前準備
このように、インボイス制度の導入により、 事業者は売手と買手の両方の立場で影響を受けることになります 。仕訳の計上方法にも影響があり、また、納付する消費税額等の計算方法も変更になります。
インボイス制度の開始にあたっては、全社的な対応と事前準備が必要です。
次回は、インボイス発行事業者の登録制度について解説します。
|
◆ 事業者は、預かった消費税額から支払った消費税額を控除して納付税額を計算する。この控除する仕組みのことを「仕入税額控除」という。 ◆ インボイス制度導入後、買手は、インボイスを保存しないと原則として仕入税額控除を行うことができない。したがって、売手は買手からインボイスの交付を求められることになる。 ◆ インボイスは、登録を受けたインボイス発行事業者しか交付できない。 ◆ インボイス制度の導入により、事業者は売手と買手の両方の立場で影響を受ける。全社的な対応と事前準備が必要。 |
|
■ 事業者 ...法人と、事業を行う個人(個人事業者)をいう。 ■ 課税取引 ...消費税が課される取引をいう。 ■ 課税売上げ ...消費税が課される売上げをいう。なお、商品などの売上げだけでなく、減価償却資産の売却収入なども"売上げ"に該当する。 ■ 課税仕入れ ...消費税が課される仕入れをいう。なお、商品などの仕入れだけでなく、各種経費の支出や減価償却資産の購入支出なども"仕入れ"に該当する。 ■ 仕入税額控除 ...預かった消費税額から支払った消費税額を控除して、納付税額を計算する仕組みをいう。 ■ インボイス(適格請求書) ...売手が買手に対し、取引に適用される税率や消費税額等を伝えるために交付する書類(又は電子データ)をいう。 ■ インボイス制度 ...インボイスの保存を仕入税額控除の要件とする制度をいう。令和5年10月1日から開始される。 ■ インボイス発行事業者 ...インボイスを交付することについて、税務署長の登録を受けた事業者をいう。 |
本解説は紙版の週刊税務通信と税務通信データベースの両方がセットで含まれる商品をご契約の方限定で閲覧できる税務通信DBセット限定解説です。詳細は以下をご覧ください。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします